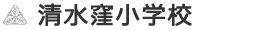令和7年度 2学期
更新日:2025年12月25日
12月25日(木) 終業式
開式後、校長講話では80日間という2学期の学校行事を振り返りました。また通知表に書かれている「良いところ」はさらに伸ばすようにし、家族と話す中で「3学期、来年度に向けて努力していくことを決めてほしい」との話がありました。
続いて2年児童代表のことばでは、学芸会、持久走記録会、SC科見学、算数かけ算九九について振り返り、上級生からの応援、励ましの言葉、家族からの温かい言葉を受けてがんばれたこと、うれしかったことが述べられ、3学期は、より1年生の手本に、また友達を多く増やしたいという力強い言葉が添えられました。
式後には、冬休みの楽しく安全な過ごし方について生活指導主任から以下の4つのことを指導しました。
・感染症から身を守る 手洗い うがい マスク
・事故から身を守る 遊ぶ場所にも気を付ける ボール遊び 凧あげ 等
自転車運転時のヘルメット着用 ライター、マッチ等不所持
・不審者から身を守る 合言葉「いかのおすし」復習 16時30分には帰宅
・規則正しい生活を送る 就寝、起床時刻 ゲーム、スマホ等の利用時間
生活指導主任の話に先立ち、校長からも「学校生活をよりよくするために」ということで本校ホームページ「配布文書」に格納している資料についての説明、指導がありました。いやなことをされたり、いやなことがあったらすぐに家族に知らせること、また「配布文書資料」には、相談窓口一覧や相談シートがあることを伝えました。
12月24日(水曜) 4年 国語「俳句を楽しもう」 他
4年生の教室廊下に掲示している標記児童作品を紹介します。
学校の 最後のそうじ がんばるぞ
大みそか 新年に向け 整える
大みそか こっくりしてたら 朝日差す
地面がサクサク あらしもばしら もう寒い
光さえ 時期を感じて こおりつく
ちらちらと ふるゆきとにた アリッサム
初日の出 海が金色 光る朝
起きたとき 窓から感じる 冬うらら
また、明日の2学期終業式を前に、今日の各学年学級の様子をお知らせします。
1、2年生は冬休みの宿題にもなっている「硬筆かきかた」の練習に取り組んでいました。教室は私語がなく、お手本を真横に置いて1字1字を丁寧に書く鉛筆の音だけが聞こえました。3年生は「毛筆習字」の練習―3年生にとっては初めての毛筆でのかきぞめを机上でまた床で行っていました。4年生は早くも大掃除―仕事分担をして声を掛け合っていました。5年生は学芸会の振り返り、そして6年生はSC科学習の「評価」を行っていました。実験方法は適切であったか、条件制御、比較は適切に行えていたか―等―6年生は各自が「卒業研究」に取り組み、3学期もさらに研究を深めます。また体育館で、教室で「2学期がんばったね会(お楽しみ会)」を行っている学級もありました。
12月23日(火曜) たてわり班遊び
12月12日(金曜)に続いて標記活動が朝の時間に行われましたが、6年生は登校時刻前に教室に入り、諸準備を行っていました。
各たてわり班ごとに校庭、体育館、各屋上に集合し、担当教員が来るのを待つ間、あるグループではリーダーの6年生に1年生が横合いから手を出したり、周囲を駆け回ったりするので「1年生・・・もう、2学期も終わりだから・・・」と笑みを浮かべながらも少々困惑した表情を見せていました。その1年生はドッジボールを投げさせてもらっていましたが、「ボールが大きいんだよな・・・」と言って、投げる動作がストップする場面が何回もありました。
「わたしは外野から頑張るんだー」
「ここからスタートして駆けていくんだー」
「がんばれー その調子―」
「タッチされてから5秒間はダメなんだよ」
・・・・・・
また、開始時に、改めてルール等を確認し、「鬼は何人にした方がいいですか」「チームは・・・」と意見を聞いてから活動を行うグループもありました。
活動が終わって忘れ物を持っていると「この上着は、〇〇さんのだー」と駆け寄ってくる
児童がいました。また活動終了時に「これで今年のたてわり遊びは最後です」「今年はありがとうございました」「来年もよろしくお願いします」と挨拶をしているグループもありました。
12月22日(月曜) 1年 国語「てがみでしらせよう」
これまで、相手意識を明確にもって書く活動として「しらせたいな、見せたいな」の学習を10月に、また「まちがいをなおそう」を、同じく10月に学習しましたが、今回は手紙を書く活動を通して相手に気持ちが届くようによく思い出して、正しい表記で書く学習を行っています。
今日は6時間のうちの4時間目で、書いた手紙を読み返し、書くときに気を付けることを意識して書けているかを確認しました。
児童たちははがき様の画用紙を次々と提出をして、担任から個別に指導を受けました。
・裏面の文章は書けているが、宛名を書き忘れている
・習っている漢字を書かずに忘れている
・表に文章を書いてしまっている
・文末が不適切な表現になっている
・「〇〇さんえ」→「〇〇さんへ」のように表記が誤っている
・「SC科見学」→「SC科授業」の内容と誤っている
・句読点の付け方の誤っている
・複数の出来事が一文でまとめられている
・拗音、促音が適切に使えていない
・縦書きの場合、左から右へと書き進めている
・・・・・
指導を受けている傍で聞いていると、学芸会をはじめ運動会、こどもまつり、給食、SC科等学校でのことや七五三や会食等自宅でのこと、そして各対象は家族、親戚、友達等多岐にわたっていました。
12月19日(金曜) 2年 図工「どうぶつさんといっしょ」
「夢の中で動物、生き物に出会ったときにどのようにして一緒にいるかを大きく詳しく描く」という内容、めあてで学習が進みました。前時からの継続学習のため、授業開始後、間もなく個別の活動が始まったようでした。児童たちはクレパス、水彩絵の具、ペン等を使って作品に向かっていました。児童たちと作品の「世界」について聞いてみると・・・
・「ライオンに乗ってみたかったんだ」
・くまさんといっしょにパンを作っているところ
・猫が横を向いてわたしと写真を撮っているところ
・ペンギンがうちの中に入ってきてくれたところ
・カピバラがリュックを背負って散歩をしているところに出会ったところ
・猫の親子が木の下でお昼寝―私が一緒に遊ぼうとしているところ
・お散歩していてカメと出会って驚いたところ
・海でシャチに出会って背中に乗ると自分の方に鳥が2羽とんできたところ
・うさぎとドライブをして車から降りたところ
・大きい鳥が飛び立つところにいて驚いているところ
・星空の下の公園で猫に乗って遊んでいるところ
・ウサギがもちを搗く満月の夜にサンタがウサギに引かれて飛んでいるところ
・日の出の砂浜でカメを見つけてみんなに教えているところ
・・・・・・・・・・
こどもたちのイメージを膨らませた作品作りの中、次のような会話も聞こえてきました。
「こうしたらきっと(思っていたような色に)できるよ」
「〇〇はちっちゃく描くといいね」
「どうやったら太陽に色になるかな」
「むらさきってどうやって作るんだっけ・・・」
「ここは『仲良し色』(複数の色を重ねる)にするといいよ」
「こうやって(背中を丸めるように)描くと猫らしくなるよ」
仕上がった作品はタブレットPCで写真を撮り、電子黒板に映して学習の振り返りをしました。
12月18日(木曜) 東京科学大学留学生との国際交流会
6月に続いて2回目の交流会となりました。大学では今月、新たな学期となり前回とは異なる留学生15名をお迎えしました。モンゴル、イラン、インド、イギリス、モンゴル、タイ、スリランカ、インドネシア、バングラデシュ、ベトナム、パキスタンと今回も国際色豊かな交流となりました。
昨年度までは全校を2回に分けて行いましたが、今年度は3回に分けて行いました。時間は今回の方が短くなりましたが、1クラス平均3、4のグループに分けて「少人数制」となったため、より密度の濃い交流が行われました。教室を移動する留学生たちからは「(児童たちが)アクティブー」「グー」という言葉や満面の笑みがあふれていました。各教室の様子を覗くと・・・
・「〇〇の旧正月は・・・」「えっ、〇〇の給食・・・」「違う違う、お正月のことー」
・「私の国ではポケモンアニメが人気で・・・」「これは◇◇◇、これは□□□、知ってるー」
・「タイと日本のデザートを合わせたようなものも・・・」「私、甘いもの大好きー」
・「スリランカは島だから海水浴がたくさんできるー」「あー、いいなー」「日本も同じだけどね」
・「モンゴルの料理と似ている料理が日本にもあるよ」「・・・何だろう」「わかったー」
・「イギリスで有名なものは何ですかー」「うーん・・・・紅茶だね」
・・・・・
交流の中で、地球儀を用意したり、地図を用意したり、中には自分のグループに来る留学生の「国」についての本を用意して、気になったところを読んだり質問したりしている様子見見られました。
また今回は、留学生たちが緊張しないようにと、小グループでの交流を考えましたが、中にはBGMを流したり、カルタの遊び方を説明して遊んだり(時間がなくて実施できませんでしたが、歌を一緒にとの案も)している学級もありました。
12月17日(水曜) 4年 外国語 「What do you want ?」
授業前に「今日は何の学習をするのー」と児童に聞くと「今日は(2学期)最後だからゲームをやるって言ってました」との返事がありました。
教科書を使った学習では導入で世界の市場、日本の市場の映像を見てから、様々な野菜や果物の英単語を通して学習が進められ、それらを使ってパフェやピザの作り方を学習しました。
今日は挨拶、日時、曜日、時間、天気を英会話の中で行い、今日の学習ではまず様々なたくさんの色、形、大きさの紙片が用意され、それを使ってグリーティングカードを作るという話がありました。カードづくりでは「画用紙を半分に折り・・・」と説明が始まると「半分に折るって、なんていうんだ」とタブレットPCで調べる児童がいました。そして「お店屋さんごっこ」のように児童同士で会話を進めるための話型が示されるとすぐに隣席の友達と練習をする児童が見られました。
「What do you want ?」「I want ---, please」
「How many?」「――――please」
「Here you are」「Thank you」
自身が作りたいカードの模様、飾りつけに合った色、形、大きさの紙片を伝えなければならないので、中には指を折って数えたり、足踏みをしながら回答を「ひねり」出したりする児童もいました。児童同士で行う会話の様子は、年末の大売り出しの様相を呈していました。
12月16日(火曜) 社会科見学(5年)
5年生は、社会科で日本の工業生産について学習をしています。今回の社会科見学では、川崎市にある「川崎火力発電所」と「味の素川崎工場」の見学に出かけました。
「川崎火力発電所」は、1961年に石炭火力発電所として誕生し、その後、石炭、ナフサ、LNGと、最先端の技術を積極的に取り入れ、首都圏や京浜コンビナートへ電力を供給しています。敷地面積は、28万平方メートル(東京ドーム6個分)、総出力は、342万kWで、一般世帯約98万世帯で使用できる電気を作っています。こどもたちは、発電の仕組みについて、映像による説明や液体窒素を使った実験などを見て学びました。SC科の「エネルギー」の学習と関連付けて、質問をする児童がたくさんいました。また、火力発電所の中や外の設備を見学し、その大きさに驚きました。
「味の素川崎工場」では、スープ工場や包装工場を見学し、商品への工夫・努力、企業や働く人の思い、そして環境への取組みについて学びました。児童たちは記者として食糧生産の様々な流れを取材する形で見学を進めました。そして環境に配慮した、企業の「つくる責任」(SDGs項目12)についても学び、消費者として「つかう責任」とは何かという気づきをもちました。




12月16日(火曜) 3年 理科「太陽とかげ」
まず、前時の学習を受けて、タブレットPCに保存した観察記録写真を確認しました。そして時間経過に沿って写真を並び替えたデータを全員で共有し、「観察の結果まとめ」「考察」「結果」と授業が進みました。
「観察の結果まとめ」では、1つの班だけが、(棒の影が)時計回りに動いたと報告がありましたが、並べた写真の順番が逆であることがわかりました。全班が同じ結果になったと確認するまでに児童たちは、その誤りの原因を見つけるために様々な方法で確認していました。
・お互いのタブレットPCをのぞき込んで話し合う
・身振り手振りで友達に説明する
・教室後方に陳列した観察用具を前にして、観察したときのことを振り返る
「考察」では予想したことと比べて結果はどうだったかを考えました。
棒の影は西から東に動く。なぜなら太陽が反対側にあるから
-太陽は東から西に動いているから
-かげは太陽と反対側にできるから
そして「結果」は児童たちの言葉を集めて以下のようにまとめました。
「太陽と反対側に棒の影ができるから、太陽が東から西に動くとき、同じ速さで影は西から東に動く」
2時間続きの授業でしたが、児童たちは5分の休み時間にもタブレットPCをのぞき込んでさらに考えを深めたり、「次も理科だから、もっと勉強ができるね」と話し合ったりと理科学習に対する意欲を見せていました。
12月15日(月曜) 4年 総合的な学習の時間「福祉体験学習」
大田区福祉部福祉管理課の協力で、視覚障がい者とガイドヘルパー、聴覚障がい者と手話通訳者、足が不自由で車いす利用者それぞれの方々をお招きし、障がい者理解学習を行いました。
まず、障がいのある方々が生活上困っていることや工夫していることなどについての話を伺い、その後はアイマスク・白杖体験、手話会話・空書き体験、車いす体験を行いました。
手話会話・空書き体験後、「たくさん手話ができるようになりました」「手話で自己紹介ができるようになりました」との声がー中には「(手話で)これ何て言ってるんだ」「私の自己紹介を手話ですると・・・」と廊下や階段で呼び止められて嬉しそうに実演してくれる児童たちがいました。また昼休みに車いす体験をした児童たちに話を聞くと「段差で車いすを傾ける(程度)のが難しく、重かった」「車いすに乗っている方も押す方も怖かった」「病院でおばあちゃんを乗せて車いすを押したことがあるけど、今度行ったときは今日のことを思い出してやります」等の声が聞かれました。
「アイマスク・白杖」グループは体験後に会議室で学習の振り返りを行いました。
・何か物があると言われると、すぐそばにそれがあるようで怖かった
・階段では上りよりも下りの方が怖い
・段差があると言われてもどのくらいの段差が、どの辺にあるのかわからなかった
・白杖で壁は大体わかるけど、他のものだとわからない
・ガイドヘルパー(今回は同学級児童)がいなかったら歩くことは難しいと思う
また、多くの質問にもこたえていただきましたー
「趣味は何ですか」「いつから目が見えなくなったのですか」「前にはできたけど、できなくなったことは何ですか」「支えになっているものは何ですか」「悲しかったことは何ですか」「どうしたらガイドヘルパーになれるんですか」・・・
丁寧な回答を聞きながらこどもたちは、視覚障がい者の方々の暮らしぶりを思い描き、自身と比べ、障がいのある方々の心情にも触れていました。
12月15日(月曜) サイエンス朝会「あぶりだし」(酸による化学変化)
封筒の中には手紙が入っているのですが、何も書いていません。しかし、ホットプレートで温めてみると、マークが浮かび上がりました。封筒には、「酢で描きました」とあります。これは、「あぶりだし」ですね。
あぶりだしは、古くから伝わる化学遊びの一つです。昔は、火鉢やストーブなどで熱していたので、火にあぶって文字を出すことから「あぶりだし」と呼ばれました。昔は、年賀状であぶりだしが流行っていました。
酢は、酸性の水溶液です。「あぶりだし」は、酸による化学変化(酸化)を利用したもので、酸が紙の植物繊維(セルロース)に浸透すると、水分が失われやすくなり、熱を加えたときに周りより先に焦げ(炭化)が早く進むことで文字や絵が茶色く浮かび上がります。
オレンジの汁やミョウバンの水溶液も酸性の液体です。
同じように、オレンジの汁やミョウバンの水溶液で絵を紙に描いて、乾かしたものをあぶってみると、絵が浮き出てきました。
さらに、より強い酸性である塩酸を使ってあぶり出しを行ってみると、すぐに文字が浮かびました。
身近な酸性液体で簡単にできる科学実験です。火や熱を使う実験なので、必ず家の人と一緒に行ってください。
12月13日(土曜) 大田区小学生駅伝大会
大田スタジアムで、小学生駅伝大会が行われました。清水窪小学校は第1部に5・6年生の代表選手が出場しました。
11月下旬から始まった毎日の朝練習の成果を発揮し、清水窪小学校の代表として活躍すべく、すべての選手が全力を尽くしました。
結果は入賞とまではいきませんでしたが、最後までたすきをつないだ選手の皆さんに大きな声援が送られました。
選手の皆さん、お疲れさまでした。そして、応援に来てくださった保護者や児童の皆さん、ありがとうございました。




12月12日(金曜) 避難訓練
授業中に近隣で火災が発生した場合の基本行動を理解させ、状況に対する的確な判断と落ち着いた避難行動がとれるようにと5,6年生の
初期消火体験を併せて行いました。
避難の基本行動としてはー
・情報を正しく聞き取る ・避難経路を知る ・教員の指示に落ち着いて従う ・避難の方法を知る
で、毎回訓練で指示する「おさない、かけない、しゃべらない、もどらない、ちかづかない」(おかしもち)の約束の徹底を図りました。
田園調布消防署雪谷出張所から4名の職員が避難訓練の指導に加わっていただき、「今日の避難訓練は97点」という言葉をいただきました。マイナス3点は避難時に非常階段を下りるときにかけてしまった児童がいたとのことでしたので、次回の課題となりました。人員確認後、校長講話で大分での火災、そして最近都内で多発している電気による火災を通してその用心、予防について呼びかけられました。その後、初期消火体験訓練が行われましたが、それに先立ち、避難訓練担当教員からは、話の聞き方についてのすばらしさを褒める言葉がありました。そして最後に署員の方と以下のことを確認しました。
・消火器を悪ふざけで使うと、火事発災時に使えなくなること
・消火器を使うときは初期消火のみで、「3つのステップ」で噴射距離2,3mを保ち、煙を吸わないようにすること
・(火が広がりそうなときは)119番の電話をかけること
12月11日(木曜) 6年 社会科見学
午前中は国会(参議院)の見学を実施しました。今日は見学者が1000名を超えるということで、天皇陛下御休所をはじめ本会議場も立ち止まらず、歩きながらの見学となりました。中には議員の方に声をかけられた児童もいたようですがあっという間に議事堂前庭に出て、日本の各都道府県の木々の小径を通って正門前での記念撮影に向かいました。
「宮崎県の木は・・『ココス』・・・」「神奈川県の木がイチョウ・・・確か東京都もイチョウだよね」「先生の郷里の山形は・・・サクランボーああ、札の奥にあるのじゃないー」「最後は、北海道―やっぱりアカエゾマツだ」
憲政記念館脇の駐車場でバスを待っているときに・・・「アリがいるけど動きが鈍い・・・寒くなったからかなーあっ、小さなアリが近づいてきたけど・・・」「この黒い実は・・・学校の体育館前にある木(トウネズミモチ)と同じだ」―とやはり「サイエンス」の方に目が行く児童たちが多いようでした。
午後は上野の東京国立博物館に行きました。まず、学芸員に方から話を伺いました。「東博について」「博物館の役割」そして最後に「楽しみ方」として「じっくりと観る」「比べて観る」「想像しながら観る」「季節を探してて観る」の4点と鑑賞マナーを教わり、グループごとに計画に沿って見学をしました。
「あっ、これだ!(刀剣に銘文の刻まれたもの)」「これ(銅鐸)鳴らしていいのかな?」「ズレちゃった。唇が・・・(浮世絵スタンプをして)」「勾玉がいろいろな種類があった。色も微妙に違うものが・・・」「(陶器の)器で700文字くらいの文が書いてあるのが1番心に残った」「埴輪は艶があり、いろいろな大きさのものがあった」集合場所の本館前に集まった児童たちからは、「広かったー」「もっと見たかったー」「時間が足りなかったー」という声を多く聞きました。
12月10日(水曜) 2年 道徳「お月さまとコロ」(正直・誠実)
導入で「謝りたいのに謝れなかったことはないか」との問いに、家庭でのこと(宿題をやろうとしたときに「早く宿題やりなさい」と言われたとき 等)、友達とのこと(鬼ごっこで友達を追いかけているときに「一人狙いだ」と言われたとき 等)等、継ぎ早に発言がありました。そして教材文の範読後に、登場人物のコロとギロの心情についてグループで考えたり、発言したり、またノートに書いたりして考えを深めました。
・文句を言ったり怒ったりすると謝れなくなる
・お月様のおかげで歌を歌って元気になった
・謝るのは無駄・・・仲良くなれる・・・どっち・・・
・謝れば戻ってきてくれるかな
・謝っても許せないと言われるかもしれない
・許してくれるかなー何回も謝っても足りない気がする
・謝れないとき、もっと勇気をもたなきゃ
・素直な気持ちになれるかも
・もうちょっと自分をもたなきゃ
・なんで今まで謝まらなかったんだろう
・これからはみんなに本当の気持ちを言おう
・これからは本当の気持ちを言おう
―素直な心で過ごすとどんないいことがあるかー
・嫌われと時もあると思うけど、仲良くなれる
・元気になったような気持ちでいられる
・いままでの友達にも謝まる気持ちに・・・
・何人友達できるかな・・・
12月9日(火曜) 社会科見学(3年)
3年生は、社会科で大田区についての学習をしています。今回の社会科見学では、大田区にある「羽田空港JAL SKY MUSEUM」「大森海苔のふるさと館」「京浜トラックターミナル」を見学しました。
羽田空港JAL SKY MUSEUMでは、施設の紹介ビデオを視聴した後、館内を見学しました。空港で働く人や旅客機の歴史などについて学びました。運航乗務員や客室乗務員の試着コーナーもありました。その後、格納庫で実際に整備士が飛行機を整備している様子を見学しました。間近で見る大きな機体に驚きました。飛行機が着陸している様子も見ることができ、感激しました。
大森海苔のふるさと館では、大田区は約60年前まで海苔づくりが行われていたことを学びました。羽田空港など埋立地が拡大し、大田区での海苔漁業はなくなってしまいましたが、その海苔づくりの技術は日本各地に広がったことも知りました。
京浜トラックターミナルは、首都東京都物流の要であり、国内最大のトラックターミナルです。車窓から見学しました。
どの子も熱心に見学し、見学態度も立派でした。








12月9日(火曜) 4年 東京科学大学研究室訪問
先週に続き今日は4年生が東京科学大学研究室を訪ねました。冒頭、大学(院)の研究とは「誰もやっていないことー最先端の研究を行うところ」「大学生や社会人の人たちが勉強するところ」であり、今回訪問した藤井先生の研究室では、社会、インフラ、社会基盤で特に川や水に着目した研究を35名の年齢、国籍が様々な人たちとチームで行っているという話がありました。そして今日は「川の水などをきれいにして各家庭に安心安全な水を届ける- 安全な水を作る技術やその開発」に沿って講義が進められました。社会科で学んだ浄水場での水のろ過等の話から、実際に活性炭やナノチューブを吸着材として汚れに見立てた液体(アシットブルー、メチルオレンジ)をきれいにする実験を、行いました。吸着剤と液体をよく混ぜてシリンジでろ過すると、それぞれで結果が異なり
(汚れの除去率) = 100-(汚れの残存率)
という式で、汚れの色の変化を数値に置き換えて理解を深めました。
最後に先生は児童たちからの質問に答えていただきました。
「どのようにして吸着剤は発見されたのか」
「鉛筆の芯(グラファイト)も活性炭やカーボンナノチューブの仲間ということだが汚れの吸着以外の使いみちはないのか」
「水資源利用率1位と最下位の国はどこか。」(日本20%、エジプト120%、カタ-ル500%)
「水はどのようにしてうまれたのか」
「汚れの除去技術がなかった時代は、どのようにしていたのか」
・・・こどもたちの科学的な見方、考え方はこれからも深まっていきます。
12月8日(月曜) 全校朝会 -大田区駅伝大会壮行会
今週12月13日(土曜)の大田区小学校駅伝大会に出場する代表児童たちへの標記壮行会が行われました。主に朝の時間を使って練習を重ね、今朝も入校を待つ児童たちの熱い視線を浴びて汗を流した直後の会でしたが、以下のように一人一人が力強くその決意を述べました。
・精一杯走りますので応援よろしくお願いします
・本番は最後まで走りきるので会場での応援をよろしくお願いします
・負けず嫌いなのでいっぱい走って自分の限界を突破します
・最後まで気を抜かずに走るので応援よろしくお願いします
・1分1秒でも速く走れるように最後まで走りぬきます
・同じペースで最後まで走りぬきます
・最後まで頑張って自分の限界を突破します
・最後まで全力で走りますので応援よろしくお願いします
・最後にやり切ったと言えるように頑張ります
・小学校生活最後なので悔いのないように全力で頑張ります
・みんなと力を合わせて1位が取れるように頑張ります
・頑張ります
・清水窪の代表として走ってきますので応援よろしくお願いします
また併せて、運動能力テストの今年度各種目別最高記録の表彰も行われました。
―運動能力テスト種目―
・握力 ・上体起こし ・長座体前屈 ・反復横跳び ・20Mシャトルラン
・50M走 ・立ち幅跳び ・ソフトボール投げ
12月5日(木曜) 5年 SC科 東京科学大学研究室訪問
今年度も標記研究室訪問を行いました。講師は工学院機械系教授岩附信行先生で、スクリーンに「ロボットを動かすメカー歩行ロボットの脚のメカを作ってみようー」が大きく映し出されいるのを見つけると児童たちから「ワー、すげえ、ワクワクしてきた」等の声が漏れていました。導入では例年通り自身が描かれたサインペン画、木工工作(ドールハウス)の話から物を立体的に表すには、またものづくりには「順序」が大切であるというがありました。そしてものづくりではできるだけ資材(今回はモーター)を軽くするための工夫、コストパフォーマンスも必要で今回ロボットを動かすモーターの数について必要な数を割り出す計算式を負い得ていただきました必要な
ロボットを動かすモーター数 = 3×□(運動するリンク数) ― 2×△(関節の数)
という大学で習う数式で、今日作るロボットに当てはめ《3×5-2×7= 1 》とモーター(動力)が1つという答えを導き出しました。そしてその論理に沿って歩行ロボットの脚の動きをPCムービー画でスクリーンに映されると教室内に「ウオ―」という歓声があがりました。今日は脚のメカを工作用紙で動く紙製模型を作るということでまず、はさみで各パーツを切り分ける作業が始まり(左利きの児童用のはさみも用意していただきました)最後にハトメパンチを使い指示通りにパーツをつなぎとめる作業をしました。
「これ、3,4年生でもできますよ。だって回答の写真があるんだもん」
「あっ、失敗した。ここの膝関節にこれもつけるんだった」「えっ、これ上下(パーツ)の重ね方が違うんじゃ・・・」
しかしほとんどの児童がはとめパンチを使った経験がなく、悪戦苦闘する様子が見られました。「やっぱり『順番』だ、順番が大事なんだー」「わたしは足のところから始めた」「ぼくは、真ん中の膝のあたりから・・・」「ハトメパンチが硬くてしっかり止められないー」「これでいいんだよね」・・・と完成する児童が増えてくると、それらの多くの子たちが製作に困っている友達のそばに移動し教え、手伝っていました。中には、帰校、校門の手前で「分かったーここがおかしいんだよ」という声も聞こえてきました。
また学校への帰路、「今日作ったのは脚の部分だけど、体全体の動きを考えて作るのは大変なことだな」「私は空港のラウンジで脚のないロボットが働いているのを見たことがある」等の話が出ていました。
12月4日(木曜) 6年 SC科見学
気象科学館、みなと科学館そして科学技術館で標記の学習を行いました。それぞれの場所では、6年SC科卒業研究を睨んでのグループ活動を行いました。「実験室 創る・探求する」には「浮沈子」「ペットボトルトルネード」に装置があり「これサイエンス朝会でやったヤツだ」の声が上がり、迷わずに実験を進めていました。「わたし」を科学の目で見るコーナーでは、大勢の児童が集まり、反射神経テスト、ジャンプ力測定、動物と足の速さを競い、大いに盛り上がりっていました。また「港区で見られる生き物」では模型、標本を見て「カワセミは、洗足池公園で見たよ」「カミキリムシの模様が白じゃなくて水色のは見たことがあったけど・・・」等の声が聞かれました。科学技術館は先の午前中の施設の数十倍もの体験学習ブースがあり、多くのサイエンスに触れました。
以下見学カードから抜粋
・地震波の伝わり方で専門家はP波に注目して観測することが分かった
・天気予報の仕事は、観測・予測・発信に分かれ、スーパーコンピュータも活用していることがわかった
・降水量の〇ミリメートルというのは、1時間の計測機器にたまった深さを表していることが分かった
・津波とは海底の地震の力が伝わり大きな波が伝わる現象で、水全体が動くのでとても危険であることが分かった
・単子葉植物で維管束の並び方に違いがあることが分かった
・火山のマグマが溜まってくると山が膨らむことが分かった・火山の噴火の前触れは空気の振動で分かることが分かった
12月3日(水曜) OJT研修 4年 特別活動 学級活動(1)
特別活動は、各活動(学級活動、児童活動、クラブ活動)。・学校行事に分かれ、今日行った学級活動はさらに以下のように構成されています。
(1)学級や学校における生活づくりへの参画
(2)日常生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全
(3)一人一人のキャリア形成と自己実現
本時の議題は「2学期がんばったね会をしよう」で、はじめの言葉、計画委員(司会、副司会、黒板書記、ノート書記)の紹介議題の確認、提案理由の確認と進められました。提案の理由としては・・・
「今までいろいろな集会、行事を通して様々なことがあったけれども協力して乗り越えてきたので、一人一人の頑張りに対し互いに労い、会を通してよりお互いのことを知り、さらに絆を深めたい」
ということで話し合いのめあてを以下の通りに設定しました。
・お互いをねぎらい、みんなで楽しむがんばったね会を計画しよう
・話し方、聞き方のめあてを守り、友達の考えや意見を認めよう
決まっていることとしては
・実施日 12月18日(木曜)3,4校時
・場所 教室、校庭(体育館)
内容については事前にグループごとに話し合って決めていた以下のものの中から
・みんなで楽しめるもの
・今学期頑張ったことを振り返ることができるもの
という視点から話し合い、〇印のついて遊びが選ばれました。
王様ドッチボール レンチン鬼ごっこ ドッジボール 〇何でもバスケット 〇だるまさんがころんだ 〇ばくだんゲーム
次にどんな工夫ができるかを考え、以下のような意見が出ました。
・ゲームの中でがんばったことを言う ・黒板に書いてみんなにわかってもらう
・紙に書いて後ろの黒板に貼る ・がんばった様子の映像をみんなで観る ・給食の時間を活用する
最後に係・役割を決めて、担任から本時の振り返りをして児童たちの活動を評価しました。
12月2日(火曜) 1年 生活科「リース作り」
1学期から育ててきたあさがおのつるを使って標記活動をしました。作業は2人ペアで進め、お互いに声を掛け合い、手伝う姿が見られました。
「ここ持ってて」「(二人それぞれ出作ったつるの束の)太さが違っちゃった」「今度はやっと僕の番だね」「ここ持ってー」
「種を取ったけど無くならないように、この(植木鉢)下に入れているんだ」「見てーこんなに大きい種―」
「わー、(つるが)大量に取れた」「広いところでやろうよ、こっち来て」
「ぼくのは茎が赤いのが1本あるからわかるんだ」「私のは蕾がついているんだ」
「〇〇ちゃんは毎日お水をあげていたから、こんなにつるがたくさんだ」(つるを支柱から外すのを)「手伝うよ」「ぼくもやるよ」・・・と2人組が3人、4人、5人と増えていきました。
「ハナムグリがいたー弱っているから水をあげてるんだ」―見ると手のひらにハナムグリと水が数滴―
「この短いの(切り落としたりしたつる等)も集めたら(リースが)できるかも・・・」
終盤になると「大きいー」「完璧にできたー」中には出来上がったリースを頭にのせて見せ合ったり、学芸会の劇中のセリフを言ったり(1年生の劇以外のセリフも)して、「あー、楽しみですねー」とこれからの学習に胸を膨らませている児童も見られました。
11月29日(土曜) 学芸会保護者鑑賞日 ~児童振り返りカード等一部抜粋~
低学年
・今まで練習してきた成果が出て喜んでもらえた ・頑張ったから拍手が大きかった ・みんなに拍手をしてもらって嬉しかったし、気持ちが伝わった ・終わったときにみんなが笑ってくれたので嬉しかった ・これからも6年生を見習って学芸会をがんばりたい ・6年生になったらあのような立派な人になりたい ・みんなと協力すると気持ちがいい みんなで歌うのが楽しかった ・自分が力を合わせて工作や音楽で頑張った成果を発揮できた
中学年
・次が最後の学芸会だからもっとみんなに褒められたい ・この次も1年生の手本になるように頑張りたい ・この次は大きい声でもっと役になりきってやりたい ・本番を終えてやり切った感があってうれしかった ・セリフを言ったら楽しくなった ・この学芸会を生かしていろんなことに挑戦したい ・発表や普段の授業も大きな声で自信をもってやりたい ・大成功にできたことが嬉しかった ・大きな声で楽しんでできた
高学年
・努力の積み重ねにより、恥ずかしさを前よりも和らげることができた ・観客を感動させたいという思いが自分の中にあったので練習はきつくなかった ・気持ちが1つにまとまると個々の力を大幅に超えた大きな力を発揮すると思った ・家族から感想を聞いたとき感動したと言ってもらえてよかったと感じた ・終わった後、達成感がとてもあったが始まる前は「期待」「自信」のようなものがあった ・他学年の演技を見て学ぶことも多く、自分の中でも1番の演技ができた(みんなの演技を見習いたいとも思った)・悔いのない学芸会にすることができたと思った ・みんなで意見を出し合ったことが今日の演技に繋がり、学芸会のおかげでみんなの仲が少しでも深まっていたらいいと思う ・学年かかわらず、支えあっていける清水窪小学校はすごいとも思った
11月28日(金曜) 学芸会児童鑑賞日
・ 1年「ふしぎの国のアリス」
楽曲に合わせて元気な歌声が会場内にーのどが痛くならないかと心配になるくらいの迫力のある響きでした。国語、音楽、図工の授業を通して劇を作り上げてきました。ステージ、ひな壇に整列して開会を待つ間、緊張からか欠伸をする児童が数名。「私のお兄ちゃん〇年生」「私のお姉ちゃんも〇年生」と意気投合し、笑顔で〇年生の劇のセリフを声合わせてー余裕のある様子を見せている児童もいました。
- 2年「あやうし!忍者学園!」
冒頭、「こんにちはー」「○○〇はありますかー」と児童が客席に向かって呼びかけをしますので元気に応えていただけたら嬉しいです。様々な忍法の術を披露する場面では会場が大きな笑い声で包まれました。途中、舞台上で転んでしまった児童がいたときには客席から「大丈夫―」という声が聞こえてきました。エンディングは多分、皆様方もよく知る曲を歌います。どうぞご一緒に。今日は次第に手拍子の輪が広がりました・・・
- 3年「西遊記」
全体の歌声とともに、独唱で頑張る児童たちにも惹き付けられるものがあると思います。ミュージカル調のダイナミックな動き、歌声等も大きな見どころです。途中、小道具のお守りが壊れてしまうというアクシデントがありましたが、うまくやり過ごしていました。滑稽な動作には、特に間近で観ていた1,2年生が思わず立ち上がったりのぞき込んだりしていました。
・4年「寿限無」
皆様ご存じの滑稽噺の1つですが、冒頭これまたテレビでも有名な番組の曲に合わせて登場した「噺家」がそれぞれ小噺風のものを披露します。学校全体としてのものとは別の捲りプロが登場し話が進行します。後半、通路も使って、より躍動感のある動きに会場は大いに盛り上がりました。それにしても繰り返し呼ばれる「寿限無寿限無、五却のすりきれ・・・」
に会場からは「長いよー」の声も。
・5年「まほうをすてたマジョリン」
背景画、小道具づくり、伴奏、照明・・・児童たちが中心となって劇を作り上げてきました。背景を舞台背面スクリーンに投影する学年が多い中、何十枚分もの模造紙に描いた背景画は迫力があり「スゲー」という声があちらこちらから聞こえてきました。また4年生と同じように会場まで飛び出し、ギャラリーも使った演出に悲劇の主人公の様子にに「かわいそう」という声が漏れていました。
・6年「エルコスのいのり」
昨日の校長講評を受け学芸会「本番」を迎えた6年生は通常よりも早めに登校。最後の「出番」まで下学年児童の世話(トイレ、けが等対応)、大道具搬出入、放送、進行・捲りプロ、そして幕間劇等―幕間ではクイズを出したり笑いを誘ったりしますので、ご協力をお願いします。劇中では会場フロアに設置された大道具が登場(実は会の初めから)したり、通路を活用したりして迫力の増した表現に、自然に手拍子が起こったり「ダメー」「かわいそう」えーっ」等の声が聞こえてきました。
11月27日(木曜) 学芸会リハーサル
教員室脇の校庭池付近の防球ネットに学芸会各学年演目のポスターが掲示され,休み時間や登下校時に足を止めてそれらに見入る児童たちが多くいます。
「6年生の劇が楽しみです・・・だって・・・お兄ちゃんが出から・・・」「もちろん自分たちの劇が楽しみー」「準備OK-言葉も動きもー」 ・・・・・
今朝は、たてわり班落葉掃き、区駅伝大会に向けての練習、さらに来週の持久走記録会に向けての2,5年生の練習―校内は朝から活気に満ち、家庭科室では5年調理実習、体育館では1年生から学芸会リハーサルが始まりました。早めに体育館に着いた1年生でしたが朝の「隙間」の時間を使って4年生が・・・整列して待っていた児童たちの傍を歩いていると・・・
「この帽子はケーキになっていて、これ(つば)はお皿なんだ」
「あれ、ポップコーンじゃないーおいしそうーおなか減った」と奥の他学年大道具を見て
「これ、大きいけど手なんだ。ハイタッチしようーイェーイ」」
「足が痛いなー」とその場で駆け足をしながら・・・(緊張が隠し切れない様子で)
「緊張するー」と交差させた腕をさすりながら・・・
「あれー小道具のバナナが多くなったような・・・」
「準備OK-座るところが(段ごとに)互い違いになってるかな・・・」
中には「マスクしているけど、頭、痛いの」―と気遣ってくれる余裕のある児童も
リハーサル終了後は、集合記念撮影―それぞれの衣装や小道具が上手く写るようにと・・・
「昨日より上手くいった」「ぼくが1番声を出したよ」「指のささくれが痛くて・・・」「この手袋の指先のところが冷たいんだよな・・・」
3,4校時は6年生と大森第六中学校の学校説明会に出かけました。その6年生は帰校、給食後にリハーサルをしました。そして」「6年生の劇は面白さを表現するのが難しい。大道具、小道具も少ないので言葉、表情で勝負―」と校長からのコメントを受け、教室に帰ってきた児童たちからは・・・
「間違えてしまったー」「放課後、練習しようぜ」と少し気持ちが引き締まったようでした。そして放課後には明日の学芸会第1日目(児童鑑賞日)に向けての会場準備が行われました。
11月26日(水曜) 学芸会リハーサル前日
昨日、今日と、いつもなら休み時間には元気に遊ぶ児童たちで溢れる校庭が、数えることが出来るのではないかと思えるくらいの児童たちの姿しか見られませんでした。多くの児童たちは各教室等で今週末に行われる学芸会に向けての準備等に追われているようでした。
「先週休んだから小道具づくりが間に合わなくて・・・」
「どうもこの冠が・・・ゴムを付けて固定できるようにすればいいのか」
「これは、私が作った杖。〇〇のはこれー大きくて先に骸骨がついているんだ」
「帽子はかっこいいではなくて、少し傾いていて・・・」
「(衣装の腰ひもが解けず・・・)できたー今度はちょうちょ結びができるように教わっておこう」
休憩時間が終わる数分前に、衣装に着替えて小道具を持って練習会場の体育館へ向かう児童に「休み時間があまり取れなかったね」と言うと「うんー」と元気に明るい表情で答え、体育館での練習が楽しみでならない様子でした。
また学年全員が1つの教室に入り、体育館での舞台練習の様子を録画した動画を見ながら次回のまた本番当日の自分自身、また学年全体の劇についてチェック、振返りをしている様子も見られました。
11月25日(火曜) たてわり班奉仕活動―落ち葉掃き
今月に入ると校庭には落葉が目立ち始め、児童たちは連日用務主事が掃除をする姿を見ながら登校してきました。特に朝の校庭での活動(たてわり班音読会、開校記念集会、持久走練習等)の日は、校庭トラックの掃除を優先して行っていました。その様子を見てランドセル姿の児童たちが素手で落ち葉を集めて手伝う姿も見られました。
今日も早めに集まった児童たちが、率先して校庭隅のシンボルツリー(桜)の周りの掃き掃除を始めていました。集合時刻の8時5分になり、当番1班班長の活動説明に従い、5,6年生は箒を使い、下学年児童たちは軍手をして掃き集められた枯葉を大バケツに入れていきました。
「(バケツの中に枯葉を押入れながら)葉っぱの押しくらまんじゅうだー」
「(下学年がしゃがんで枯葉を集めているので)箒で掃くときに砂を飛ばさないようにー」
「わぁ、葉っぱのにおいがするー」
「このあと持久走練習だから、落ち葉掃きと重なっちゃうときもあるんだな・・・」
活動終了時に再度集合し、バケツにギュウギュウ詰めになるほどの落葉を集めることができました。そしてリーダーの6年生が全員遅刻することなく参加できていたことに、自然と拍手が起こっていました。
本活動は、今日から来月12月19日まで行っていきます。
11月21日(金曜) 1年 SC科見学
「ぞうさんはかせになろう」の学習で上野動物園に行きました。出発式で学年主任から再度話がありましたが、見学しおりの3つのめあてについて児童たちの様子等をお知らせします。
1.ルール・マナーを守って行動しましょう
・出発式後、二人組(バディ)で手をつないで環七通りまできちんと路側帯内側歩行を
・バス配車を待つ間、通りを覗き見ていると「副校長先生、危ないよ」と
・バス運転手に「おはようございます」「よろしくお願いします」と次々に挨拶を
・下車前には担任から挨拶を促されましたが、見送る運転手に笑顔で手を振って
・ぞうのスケッチ中、最前列の児童に「後ろでぞうさんが見えない子がいるよ」と言うとすぐに換わってくれる子が・・・また最前列の児童たちも横に詰めて後ろにいる児童を招き入れたりと
・大きい声を出したり騒いだりしてはいけませんーとの注意を思い出し「くまさーん、こっちこっち」「あー、ごりらだ」の声に「大きい声だしちゃダメでしょ」と
・「混んできたね」「ここは1列になった方がいいね」「〇〇ちゃん、バディ組もうー」と ・・・・・・
2.小泉さんのお話をしっかり聞きましょう
小泉さんは2年生が「キリンはかせになろう」の学習でもお世話いただいている動物解説委員で、1年生は先週オンラインで授業に参加していただき、様々な質問を受けていただいています。
・泥をかけて日焼け止めにするのは本当ですか
・おしっこの量はどのくらいですか・・・おしっこを飲んでたみたいだけど
・鼻をいつも丸めているのはなぜですか
・「パオーン」ではなくで「ブオー」ってバイクみたいな音が出たけど・・・
・アルンはどうして水浴びが好きなんですか、お父さんはいますか
・耳をパタパタさせるのはどうしてですか
・赤ちゃんぞうはどうやってお乳をのんでいるんですか
・ぞうさんはどれくらい寝るんですか どうやってねるんですか
-10分ほどの時間でしたが、深い学びとなりました
3.ぞうをしっかりと観察しましょう
・アルンはオスだから牙がある ・口にすごく毛が生えてる ・あっ、うんち食べてる ・おしっこ出したらのんでる ・砂を掘って体にかけてる ・耳が平べったくてパタパタしてる ・体の色は灰色と茶色 ・あしにつめがある ・おならをした ・おなかなでかい ・水を飲んではいた ・鼻をブラブラ、クルクル動かしていた ・おしっこが白くて泡が出てた ・アルンはおすだからオ〇〇〇ンがある ・・・・・・・
児童たちは、象の前から、横から、後ろから観たスケッチをしながら気づいたこともたくさん記録していました。
11月18日(火曜)、20日(木曜)たてわり音読会
先週13日(木曜)に標記音読会に向けて、たてわり班内でペアを作り、上学年児童が下学年児童に読んでほしい本等の聞き取りを行いました。上学年児童が記録していた「たてわり音読メモ」を覗くと-こわい本、お化けの本、幽霊の出てくる本、血がドバーって出てくる本やサバイバルの本、冒険の本等、どきどき、はらはらする本を希望する児童が多いようでした。他にも、動物の本、○○シリーズの本、字の少ない本、長いお話の本等もありましたが「人生の本」「人間の本」等やや哲学的なものを求めている児童もいて、高学年児童がさらなる聞き取りに頭を抱える姿も見られました。
18日(火曜)―前日が気温20度を超え、朝の冷込みがなかったため予定通り校庭で会を行いました。校庭ではたてわり班班長が班カードを掲げて下級生を待ちましたが、中には音読を行うペアで手をつないで校舎から出てくるという姿も見られました。会が始まり児童たちの様子を覘いて見て回るとやはり絵や写真、漫画の掲載された本が目立ちましたが、希望通りに活字だけの本を読んでもらっている児童がいました。読み始めの様子を見ると・・・
・表紙の絵などを見ながら話の概要等を話している子
・目次を見ながら、読み始めるところを決める子
・巻末の登場人物の絵を見せている子
・初めからページを手繰って見せ、間もなく読み聞かせをする子
等、様々でした。中には図鑑で読んでもらいたいところを下学年児童が開いて指し示す様子も見られました。
20日(木曜)―本日は昨日同様、朝の冷え込みが強いため教室で行いました。欠席者のいるペアの調整等を行い、急遽2人に読み聞かせをしたり、ペアを変更したりと臨機に応じて会が始まると・・・
・「宇宙」の本を見て「この星はこの後、どうなるんだろうね。」
・「おばけ」の本を見て「このおばけ、口が・・・」
と,本文にないことを話したり、クイズの本で問題を出して答えられないでいるとヒントを教えたり解説(説明)を分かりやすく話したりする姿も見られました。また、遅刻をしてきた児童には、少しだけ読んで後は休み時間にーと対応する様子も見られました。
本校の読書週間は10月に終わりましたが、11月、12月と引き続き読書に親しみ、様々な本の世界を訪ねてもらいたいです。
11月19日(水曜) 令和8年度入学予定・入学希望園児・保護者校内見学
今月に入り標記来校者が増えてきました。
校舎内を案内しているときに、保護者の方々が驚きをもって感心されることは・・・
・「算数教室」というのがあるんですね
-学年の算数で習熟度別少人数指導や放課後の補習教室で活用します
・休み時間は長いのですね
-昼・中休みは20分間ですがチャイムが鳴る前に遊びを止め教室に向かいます
・電子黒板があるんですね
-教員、児童のタブレットPCから、また全校朝会等で校長室からのデータ、画像を映し出します
・科学に関する物がたくさんあるのですね
-掲示物、展示物、SC科研究テーマに沿った実験具等が教室内外、廊下、昇降口等各所から科学に目を向ける工夫が行われています。
・学芸会の準備、練習に熱が入っていますね
-来週28日(金曜)29日(土曜)の学芸会に向けて小道具、大道具づくり(休み時間に行う児童たちも)体育館での舞台、フロアを使っての自主的なグループ練習等を行っています
・・・・・・・・・・・
また、うれしい話も聞かせていただきました。
〇公園でうちの子に清水窪の子が話しかけてきてくれた
〇周囲の保護者で、清水窪小学校に入れたいと言っている人がたくさんいる
一方、以下のような質問も受けました
●いじめや学級崩壊はないのか
-毎月タブレットPC上でいじめ調査(・学校生活は楽しいか ・友達に嫌なことをされていないか ・友達がいじめをしたりされたりしていないか 等)を行い、担任による聞き取り、それらを受けての対策委員会を毎月設置しいじめの継続、拡大防止に努めています
●校舎建て替えの予定はないのか
-来年度に体育館鉄部塗装工事が入っていますが、他の大規模工事、校舎改築、建て替えの計画は現在ありません
区域外入学者対象の学校説明会を11月27日(木曜)に行います。詳細はホームページでお知らせしています。
11月18日(火曜) セーフティ教室 1,3,5年
児童の防犯意識を高め、自分の身を守るための基本的な知識と対処の方法を理解することをねらいとして標記学年各教室でゲストティ-チャーとの防犯教室が行われました。
1年「安心して登下校」
登下校中に危険なことにあわないための危険回避の心構えを学びました。合言葉「いかのおすし」の5つの約束の言葉についてグループごとにカードを見ながら考えました。そして「いか」ない、「の」らない、「お」おごえをだす、「す」ぐにげる、「し」らせるの1つ1つについてロールプレイをしました。しかし、「す」ぐにげるでは、「お」おごえをだすということも併せて行うことの難しさも理解しました。また、不意に登場した不審者役の人の「特徴」を思い出して教えるという学習もしました。
3年「安心してお留守番」
留守番をするときの防犯意識を高め「いいゆだなあ」をキーワードに安全に留守番をするために気を付けるべきことを学びました。冒頭「留守番は家に入る前から始まっている」と教えられると聞くと、教室は静まり返り、その理由について考えを巡らせました。「い」えに入る前にカギを見せない、「い」えに入る前に周囲を確かめる、「ゆ」うびん受けの中をたしかめる、「だ」れもいなくても「ただいま」と大きな声でいう、そして「な」かに入ったら直ぐに戸締り ー後半は災害用伝言ダイヤルの使い方について学習しました。この機能について知っていた児童はわずか1名。伝えたい連絡先電話番号の入力が必要であること、また30秒間で必要事項を伝えるロールプレイも行い、細かく評価してもらいました。
5年「安全にインターネット」
インターネットを介した犯罪やトラブルの存在を知るとともに、これらに巻き込まれないための基礎的な注意事項について確認しました。冒頭にインターネットの3つの特徴を押さえ、下記のアンケート後に授業が進められました。
・自分専用の端末(スマホ等)を持っている児童―5割弱
・インターネットをあまり使わない児童―1割ほど
次に「情報を発信(送信)するとき」「知らない人からメッセージが届いたとき」等、SNS、メール、インターネットサイト勧誘、投稿の4つのシ-ンを見ながらグループでその正しい対処法について考えました。そしてインターネットへの書込み、掲載時に注意する合言葉「かきくけこ」、知らない人からのメールを受け取った時の合言葉「あくまでた」について学習しました。
すべての授業の中で、真剣な表情で頷く多くの児童の姿から、学習の深まりが伝わってきました。
11月17日(月曜)開校記念集会
今週末22日(土曜)に開校93周年を迎えることを記念して青空の下、標記集会が行われました。朝の10分ほどの時間でしたが、校長講話、児童の言葉にあったように、清水窪小学校のことをより良く知り、感謝の気持ちを忘れないようにするとともに、「バトンをつなぎ、未来へ羽ばたく」という3年前の90周年のスローガンを想起し、全校児童の気持ちが一つになるような集会となりました。集会では以下のように〇×クイズが4問用意され、清水窪小学校のことを楽しみながら学びました。
- 「SC科(サイエンスコミュニケーション科)は開校した93年前からあった」
・「SC科は清水窪小学校のものだから、きっとあったと思う」
・「(低学年)玄関に確か書いてあったような・・・」
・「たしか(平成)25年とか30年とかだったよ」
正解 × 平成25年度より全学年実施
第二問 「歴代校長先生で『加藤校長』」はいたか
・「校長先生の聞いてみようよ」
・「いた、いたよ。」
・「うーん、多い苗字だから、迷うな・・・」
正解 〇 第22代校長 加藤 康弘先生
第三問「校章にあるカシワの木は清水窪小学校に3本ある」
・「校門(坂門)のそばに一本あるのは知ってるけど・・・」
・「校章には葉っぱが3枚・・・だから・・・」
正解 × 1本
第四問 「清水窪小学校には女の先生よりも男の先生の方が多い」
(周囲の教員の数を数えて・・・)
正解 〇 男11名 女10名
そして集会後に週番から今週の生活目標「話の聞き方を意識して学校生活を送ろう」についての話がありました。児童たちの様子を観ていると、提示された「話の聞き方3つの観点」をさらに深めていこうとする気持ちが、その表情、姿勢から伝わってきました。
11月14日(金曜) 持久走練習
12月の持久走記録会に向けての練習が始まりました。今週は朝業前の時間を使い、2学年ずつ校庭で汗をかきました。
準備運動後、1、2,3年生は1から3コース、4,5、6年生は4から6コースを同時に5分間走りますが、「いいなー〇年生は。」「去年はそっちのコースだったけど・・・」という声が漏れ、「私は1から3コースのどこを走ったらいいんですか」と確かめて来る児童もいました。
トラック内側を逆方向に歩いているとー「よし」「えい」「ふぅ」「暑い」「7周―」等の声が聞こえてきました。また両手で周回数を示したり、笑顔でタッチを求めてきたり「セーター、脱いで来ればよかったな。」という呟きも聞こえました。走っている途中で上着を脱いでトラック内側に投げ込む児童がいて、5分間走った後にその上着を持っていると「それ、〇〇君のだよ」と教えてくれる児童もました。
そして終了の合図で歩いて校庭を1周し、呼吸を整えるときに、上級生が下級生の手を繋いでいる姿も見られました。また「何周走った?私10周」「えっ、短距離走では俺の方が勝ったもんね」「おれ、いいこと考えた。まず走り始めは・・・」等と記録会を睨んでの方策を立てている児童もいました
また完走後に疲れて動けなくなっている児童に声を掛けていると「私も山登りしたときに、同じように苦しくなったことがある」と話しかけてその児童の様子を窺う児童、また病後のため見学していた児童に「ぼくもこの間まで(学校を)休んでいたんだ」と声を掛ける児童がいました。
整理運動を終えて教室に戻るときは、抱きついたり肩を組んだりして「頑張ったね」「あと、1分なら走れる」等の声が聞こえてきました。
休み時間等には「じきゅうそうカード」に練習記録を残し、再来週は再度今回(今週)同様の練習会を実施し本番当日を迎えます。(自宅周辺を走るなどの「自主練」に励んでいるという児童の話も聞きました)
11月13日(木曜) 2年 生活科見学
雲が広がり霧雨の降る中、1校時終了後に2年生は洗足池公園へ向かいました。後半、グループ活動に入る頃から雨は上がり、児童たちは棲息する動物や植物の観察、園を利用する“人”にも着目して生活科の学習をしました。公園に着くと・・・「野球場がゴルフ場になってる」「あっ、池が見えてきた」・・・記念撮影後、」前半は全員で千束八幡神社方面を散策・・・「あっ、かえでがあった」「先生、カエデがすごいね」「こういう景色を見るのも悪くないね」「アオギリだ。今、研究しているヤツだ」「黄色い鯉だ」「みんなーここに(鯉が)たくさんいるよ」「25匹いたー正確じゃないかもしれないけど」・・・
グループ活動となり、7つの「ミッション」を終えると最後に公園入口に待機していた私のところに無事の報告と発見したことなどを話しに児童たちが来てくれました。
「マガモは首のところが緑なんだ。写真を撮ってるおじさんが教えてくれた」「マガモとキンクロハジロはよく来るけど、カイツブリはほとんど来ないんだって」「ギンナンの実があったけど・・・くさかった」「ガマの穂があったけど、ウィンナーみたいだった」「夏ミカンの木があったよ。実は黄色くなってたよ」「赤いカキの実もあった」「犬を散歩している人が多かったな」「鯉は、白、黒、赤、オレンジ、黄、金、銀、銅―はなかった・・・赤と白が混じったのも」「黄色い鯉は泳いでるとバナナみたいだった」「これ、もみじの木のところにあったの・・・でもこの種、ヘリコプターの羽みたいのが付いてないな」「弁天島のところにはもみじの種がいっぱいあったの」
雨がやや強く降ってきたときに雨合羽を着る友達の手伝いをしたり、リュックのチャックが開いている友達に駆け寄って黙って閉めたり、園内駐輪場からバイクが出ようとしていると周囲に注意を呼び掛けたりする児童の姿も見られました。
往路復路とも同じ道路を通りましたが、学校体育館裏のカリンがたわわに実った様子、フェンス越しに校内に落ちた実を見て「取りたいな」「持っていきたいな」との声が聞こえてきました。カリンの実は今月末の学芸会時に希望者に持ち帰ってもらおうと考えています。どうかこれ以上実が落ちないようにと願っています。
11月12日(水曜) 校内研究 6年 SC科「卒業研究」
本時は24時間扱い中16時間目の授業で、ペアグループで自分たちの研究について報告,評価し合う活動を行いました。観点は「わかりやすさ」と「科学的探究」でした。
「わかりやすさ」については表やグラフ、写真や動画を使ってまとめられていたことが中心でした。「科学的探究」については
・確認をしてより正確に答えを出していた
・諸条件が細かく、より正確だったので比較するするのに良い
・そろえる条件、変える条件を方法の方法を示している
・探求サイクル1回目での反省や生かしたいことを示していた
・失敗したことや変化しなかったことなど、詳しく書かれていた
・分かったことだけではなく、分からなかったこともかけていてよかった
・安全で可能で予想が確かめられる実験だったし、納得した
・整理した上で問題点をいろいろな面からみて改善点を講じていた
・結論でうまくまとめまとめ、考察で結果の中から新しい問題を見つけられていた
・・・・・等の意見が出されていました。
今後は、次の探求サイクルの問題についての話し合い、問題の設定を経て実験・観察へと繋いでいきます。以下、児童たちが取り組んでいる研究テーマを列記します。
「立体の金属のあたたまり方は、どうなっているのだろうか」
「水、空気、金属の他に、ものを温めたり冷やしたりすると、そのものは、どのように変化するのだろうか。」
「学校で『電磁誘導の謎!?』に迫る」
「植物のからだや成長と気体の関係について」
「水の量と雲の関係について(モデル実験による検証!)」
「もののとけ方と物質の特徴」
「植物の光合成の二酸化炭素の削減量は、どのような条件により変化するのだろうか」
「様々な植物の道管は、どのように通っているのだろうか」
「場所や環境による微生物の違いについて」
「カイコは、食べるえさによって成長や糸の強度にどのような違いがあるのだろうか」
「環境による蚕の成長の違い」
「こまの軸や円板の素材、円板の形を変えたら、3年の頃よりも長く回るのだろうか」
「4年生で調べられなかった条件で、より遠くに飛ぶ水ロケットを開発しよう」
「水ロケットをより遠くに飛ばすためには、羽や液体などをどう変えればよいのだろうか」
「限界突破 究極の水ロケット開発計画」
「水ロケットを安定した軌道で遠くに飛ばすには、どのような条件がよいのだろうか。」
「生き物の種類と骨との関係について」
「動物の顎の形と食べる物との関係は、どのようなものだろうか」
「生分解性プラスチックの分解実験」
「SDGsから考える自然災害」
「河川の地形や大きさによって水害の被害などは、どのように変わるのだろうか」
「回路のつなぎ方による電流の大きさについて」
「太陽光パネルのつなぎ方による電流の大きさについて」
「より遠くまで飛ぶ最強の紙飛行機を開発する」
11月11日(火曜) 避難訓練
授業中に家庭科室から火災が発生し、延焼の恐れがあるとの想定で校庭に避難した後、北千束児童公園(第二次避難場所)に避難する訓練を行いました。
第一次避難場所の校庭に集合するときは口をハンカチで覆うことになっていたためか私語は無く、校外の第二次避難場所に避難するときも私語は無く、路側帯に沿って整然と移動することができました。第二次避難場所の北千束児童公園の近くでは重機が稼働する音が頻繁に響いていましたが、皆静かに人員点呼、安全確認を待ち、校長講話もしっかりと聴いていました。講話では学校での火災が広がり、校庭への避難に留まらず学校外へ避難することがあるということ、そして火災の発生しやすい時季を迎えるにあたり、空気の乾燥、風等の様々な影響により災害が拡大する可能性があるということが話され、最後に児童たちの訓練に臨む姿勢を観ていて「しっかりとできた」とお褒めの言葉が伝えられました。
時正に「秋の火災予防運動」中ー防火防災意識や防災行動力を高めることができました。
11月10日(月曜) サイエンス朝会「動くこおり、まがる水」(静電誘導)
トレイの上に氷を置き、プラスチックストローを氷に近づけます。もちろん、これでは動きません。
次に、プラスチックストローをティッシュペーパーでしっかりこすった後に再度近づけてみます。すると、氷がストローに引き寄せられるように動き始めます。
この現象は、静電気の働きによるものです。ストローをティッシュペーパーでこすると、ストローの表面にプラスの電気が帯びます。一方、氷の中ではプラスとマイナスの電気が釣り合っていますが、プラスの電気を帯びたストローを近づけると、氷の中のマイナスの電気がストローの方に引き寄せられます。まるで磁石のN極とS極のように、プラスとマイナスの電気が引き合い、氷がストローの方に動くのです。
同じような現象は、氷だけでなく、水でも見ることができます。水道の蛇口から出る水に、ティッシュペーパーでこすったストローを近づけると、ストローの方に水が引き寄せられ、水の流れが曲がって見えるのです。
面白いですね。身近な材料を使ってできるので、ぜひおうちでも試してみてください。
11月10日(月曜) 小中一貫あいさつ運動 始
大森六中校区(他、小池小学校、赤松小学校)では重点指導項目の1つとして「あいさつ運動」に取り組んでいます。本校では来週の月曜日まで3、4年児童が校内4か所に分かれ、登校時間にあわせて活動を行っています。
今日はその初日―早く集まった児童たちが緊張からか落ち着かない様子で「帽子は被った方がいいのかな」「ペアの友達が来ないよ」「ええと、場所は・・・」等お互いに話をしながら集合時刻を待っていました。
担当場所の低学年、高学年昇降口、保健室前、体育館前に分かれいよいよ活動が始まると
「声が大きすぎるのは良くないよ」
「棒立ちでは、何か・・・あいさつするときも棒読みみたいでは・・・」
「ポケットから手を出して」
「もっと笑顔で」 ・・・・・・・等の声が聞かれました。
活動が終わるとグループごと(たてわり班)に分かれて反省会が行われました。
事前に、「・服装を整える ・しっかりと立つ ・気持ちを込めてあいさつをする」等の
指導がありましたが児童たちからは
「はっきりとした声であいさつをする」
「気持ちのよいあいさつをする」
「相手も気もちよくあいさつができるようなあいさつをする」
「相手の目を見てあいさつをする」
「心を込めてていねいにあいさつをする」
等の意見が出されました。
11月 7日(金曜) 指導訪問 1年 算数「かたちあそび」
大田区教育委員会による標記訪問がありました。訪問者は指導主事をはじめ教育相談員、理科指導専門員の方々で、各学級専科の授業を見ていただきました。
1年は標記算数の授業ー前時での気づき「転がる・転がらない」「積める・積めない」を取り上げ本時は形の特徴に着目して考えるように、めあてを「にているかたちになかまわけしよう」として2学級3展開で授業が進められました。
まず、個人で集めた様々な空き箱や空き缶、ボール等をうまく積み重ねていく方法を皆で考え、試してみました。
・大きくて四角いものを下にしたほうがいいよ
・丸いものは重なりづらいので・・・注意しなきゃ
・「かくっ」としているところがあると上手につめるね
・「つるっ」と「まるっ」としているものは積みづらいな
そしてタブレットPCで例題を通して様々な空き箱や空き缶、ボール等を分類し、その結果を伝え合い、さらに分類した形に名前を付けその根拠について話し合いをしました。
・「つつ」 ―何て名前にしたらいいかな・・・つつみたいだから・・・
・「ボール」 ―これはコロコロ転がる形の仲間―ボールの形
・「ぜんぶましかく」―全部同じ四角でできている―さいころの形
・「ながしかく」―縦長四角になったり、横長四角になったりする形
最後に形を見ないで段ボールの中に両手で触ることのみで、それら特徴をとらえ、どの形か考えるゲームをしました。
触ってない人―コロコロ転がりますか ・・・・はい →ボールの形だね
触ってない人―平らなところはありますか ・・・はい →さいころか箱だね。形は全部同じかな
触ってない人―丸いですか・・・はい ―上が平べったいですか -つるつるですか -転がりますか・・・
触ってない人―平らなところがありますか・・・はい ―角がありますか はい ―長四角がありますか・・・
2者のやり取りを見て周囲からは「がんばれー」の声があちらこちらからあがっていました。
放課後には教員が4つの分科会に分かれ、指導・助言等を通して「主体的対話的で深い学び」に向けた授業改善(特にタブレット端末の活用を中心とするICTを用いた授業改善))、教員一人ひとりの授業力向上を図る研修を行いました。
11月 6日(木曜) 4年 SC科「飛べ!水ロケット!」
これまで自分たちで探求してきた水ロケットを遠くまで飛ばす要因について発表し、その妥当性について振り返り、専門家講師(東京科学大学生命科学研究所准教授)に価値付けをしていただきました。
まず校庭で「No1水ロケット 決定戦」で行いました。各学級からは学習経緯の説明し、ロケット実射、そして結果発表を受けての講評がありました。
家庭科室では講師による「ロケットと宇宙と生命」という演題での講演がありました。初めにロケットの燃料について、人類が作った最大級のロケットについての話がありました。次に「月や火星に行けるとしたら、何をしたいか」の問いに児童から次のような答えが返ってきました。
・宇宙から地球を見てみたい
・無重力状態でアクロバットや二重跳び、「宇宙兄弟」みたいに・・・
・何かを持ち帰りたい(岩、砂、水・・・)
-月の岩には地球の岩と組成が同じ物も見つかるかもしれないとその理由について説明があると児童たちは静まり返って話に聞き入っていました。そして講師からの
・1971年アポロ14号アランシェパード船長が打ったゴルフボールを持って帰りたい
との回答から、死と隣り合わせの過酷な宇宙環境で「遊び心」をもつことができること素晴らしさについて言及されました。「ロケットで宇宙に行ってみたい人」との問いに、ほとんどの児童が挙手をしていましたが研究者やエンジニアという道もあるとキャリア教育の話もありました。最後に、講師から児童たちへ次のような熱いメッセージが送られました。
・実際に実験をしてみると予想と違うことがたくさん起こる
・科学で大切なことは試行錯誤である
・失敗をたくさんしてそこから学ぶことが大切である
そして
・時間にとらわれず「やろう」としていることが大切で、そこから理由をもって学ぶ
・教科書を鵜のみにせず、疑ってみてたしかめること
という言葉が付け加わりました。
先の「No1水ロケット 決定戦」が長引き、講演は20分程でしたが、その後教室へ移動しながら、また廊下で、教室でと児童たちからの多くの質問に熱心に答えていただきました。
11月 5日(水曜) 2年 SC科「たびするたねの けんきゅうじょ」 ―校内研究―
この単元の学習は10時間扱いでこれまで以下のような学習をしてきました。
まず国語科「たんぽぽのちえ」で学習したこと(4つの知恵)を振り返り、植物はなぜたくさんの種を作り遠くに種を運ぶのか共通理解し、かぜで旅をする種の形、動きを調べました。そして学校や家庭、SC科見学の上野動物園、研究室訪問の東京科学大学で見つけた種を収集し、今日の授業本時(4時間目)に臨みました。
そして「見つけた種はどのような旅をするのだろうか」という「もんだい」に向けて授業が進められました。
はじめに観察等を通して個人でワークシートに考えを書き(対話1)、次に友達と考え、ワークシートに考えを付けたしました。(対話2)、
・タンポポみたいな綿毛が付いていないから、風の旅ではなさそうだね。うちわであおいでも飛ばない。
・プラタナスの種は丸いけど、一つ一つの種に綿毛が付いている。綿毛を取ると、中には何もなかったー風の旅かな
・種を探しに行ったとき、イノコヅチが洋服に付いたよ。くっつく種は他にあるかな。オオオナモミ、コセンダングサも・・・くっついた種は・・・落ちる・・・
・ドングリは、丸くて転がるよ。転がって遠くまで運ばれると思うよ。ドングリを落としたらどう転がるかなー転がしてみよう。
これらを基に「旅の方法」を発表し、最後に全体交流をして、次時は神奈川県立生命の星・地球博物館学芸員を講師に招き、学びを深めることが伝えられ、振り返りをワークシートに書きました
・ツバキの種はどうやって旅をするのかー旅する種をもっと見つけたい
・風を送っても動かないものがあった。多分、台風の時に飛ぶと思う。次はコロコロ転がる仲間を調べたい
・ハスはひっくり返すと種がいっぱい落ち、プラタナスは踏むと綿の種がでてくることがわかった
・はすのたねは、大きさで浮くか沈むかに分かれるのがわかった
・プラタナスも「ふわふわの旅」をするのがびっくりした。もっといろんな種のことをを知っていろんな人にこのことを教えたい
・次の時間に、栗がどんな旅をするのか聞いてみたい
・ムクロジのことはあまり知らないので、この次の時間に教えてもらいたい
11月 4日(火曜) 学芸会に向けて
11月に入る前から、各学年で演目台本を配布したり、配役を決めるためのオーディションを行ったりしている様子が見られます。或る学年では、台本が配られると皆すぐにページを手繰っていましたが、記名を促し、話の概要と劇を通して皆に伝えたいことについて伝えた後に教師による範読が行われていました。そして児童たちは話のストーリー等を把握するとともに自身の希望する役についても思いを巡らせているようでした。
すでに2回目のオーディションに入ろうとしている学年もあり、第一回目のオーディションにおいて判断基準にした4点を伝え、さらに「主人公はひとりではなく、みんな一人一人が主人公」という話もしていました。
休み時間には、校庭で、屋上に向かう階段でそして教室で台本を開いて読んだり、交互にセリフを言って、評価し合ったりする姿が見られました。
学芸会のしおりは近日中に保護者、地域の方々にお渡ししますが、以下に5,6年生が地域の方々に宛てたメッセージを紹介します。
・学年みんなが一丸となって100パーセントと力を出し切って演じます
・後ろのお客さんにも聞こえるように大きな声を出すので応援してください
・わたしたちは本番に向けてたくさん練習しています。自分の役を責任をもって演じるので観に来てください
・全学年一生懸命に練習しているのでよく観てくださるとうれしいです
・6年生はこれが最後の大行事です。有終の美を飾るために一生懸命頑張るので是非観に来てください
・道具も私たちが作り、ピアノ伴奏も児童がやるので注目してください
・1年生も初めてながら頑張っています。全学年頑張ると思うので観に来てください
・観客の皆さんに笑顔を届けられるように日々練習をしています。ぼくたちの劇を観に来てください
・わたしたちの4年生の頃より成長した姿をぜひ観てください
・今回の学芸会、全力でよかったと思えるような学芸会にしたいので是非来てください
10月31日(金曜) 2年 図工科「すてきなぼうし」「わくわくカッター」
1校時、「すてきなぼうし」の作品作りは既に終了し、各自持ち帰っているために写真画像を電子黒板に映しながら各人の作品の紹介、そして皆からの感想を求めるという「鑑賞」の学習を行いました。児童からは、素敵だと思ったこと、聞きたいことなどへの返答が終わると皆から多くの拍手が沸き起こっていました。
5分の休み時間には、教室後方の棚に並んだ6年生の立体作品鑑賞―「これ、(私の)お姉ちゃんの」「すごい」「上手だね」「サッカー選手が多いな」・・・「軍手、あったかいな」
2校時は「わくわくカッター」―学習の流れの説明が終わると「何かワクワクしてきた」「(用具を)触りたい気持ちをグッと抑えて・・・」という声が聞こえてきました。指導者からは怖いという気持ちを持つことも大切で、皆がけがをしないように安全な使用方法を教えるとの言葉がありました。
【ねらい】カッターの安全で正しい使い方を知り、紙を切ってみよう
1.安全な使い方 2.準備(マット、軍手、画用紙、おぼん、カッター)3.切ってみよう 4.かたづけ
カッターを使ったことがある児童は約半数いましたが、使用時は必ずうちの人が付くということを確認しました。そしてカッターを使うときのルール、コツを児童の考えを聞きながらまとめていきました。
・安全のために利き手と逆の手に軍手をする(軍手は1校時終了時に配布済)
・刃を人に向けない(はさみを使う時と同じ)
・刃は少ししか出さない(使う時以外はしまう)
・持ち歩かない(指定席に座る)
そして切るときは鉛筆を持つようにして上から下に引くようにするーとのことですが
「なかなかうまく切れないな」と呟く児童の手元を見ると横向きに切ろうとしていることが多く、切る方向に合わせて紙を回転させるということが難しいようです。しかし、活動を続けていくと以下のような声が聞かれました。
「切れた」「どう」「こんな感じ・・・」「剣の形になったー」「図工の『図』に切れた」「クネクネ切り行きまーす」・・・画用紙にはさみでは切りにくい小窓を作ったり、星、丸、ラッパ型等の思い思いの切り抜きをしたり、幅2ミリメートルほどの「吹き流し」のようなものを作ったり、切った紙をパーツとして人の形を作ったり・・・・とカッターを使って安全に楽しく学習が行えたようでした。
10月30日(木曜) 6年 家庭科 調理実習
6年生は早くも最後の調理実習ということで、まとめの学習として個人で考えた料理をつくりました。ねらい「見通しをもって順序良く副菜づくりをしよう」ということで机上の調理計画表を見て回ると・・・
・きんぴらごぼう ・ポテトサラダ ・じゃがいもとソーセージのいためもの ・ちくわとピーマンとにんじんのいためもの ・にんじんシリシリ ・ごぼうとにんじんとれんこんのきんぴら
6つのグループに分かれても自分の分は自分で調理しました。手順としてー1.食材を洗う 2.炒めるor茹でる 3.和える、混ぜるーとし、途中で味見をしたり味付けの仕方を確認したりすることを伝えて実習が始まりました。
・たまねぎの皮をむいたけど、この先っちょはどうするのかな・・・
・じゃがいもはかわのままでもいいかな・・・
・じゃがいもの品種が違うと色も違うんだね
・えーっと、ほうれん草は根の方から入れて30秒・・・・
・じゃがいも、にんじん、たまねぎーたまねぎは後からでもいいよ、生でもたべられるから
・ソーセージを切るときは、押すだけじゃだめだよ
・待ってーフライパン、フライパン・・・・油に気を付けて
・きんぴらごぼうは・・・これくらい(炒め具合)でいいかな
・うーん、ウィンナーが・・・野菜の方の味はいいんだけど・・・食べてみますか
・・・・・・・・・
今回は6名の保護者、地域の方々にお手伝いをいただきましたが片付け方が効率よく行え、指導者から褒められていました。昨日までのとうぶ移動教室でも第一日の夕食、飯盒炊爨でのカレーライス作りでも手際よく準備、片付けが行えたという話からも今日のことも納得がいきます。一方、実習中にはやはり移動教室の話題が出て、保護者から「すぐに寝られなかったでしょ」に「はい」という元気な声が。またカレーの味は「甘くもなく、辛くもなく・・・うちのカレーとは違いました」―とのことでした。
10月29日(水曜) 6年 とうぶ移動教室(3日目)
最終日の朝が来ました。今朝も天気が良く、遠くには北アルプスの山々が見えました。朝会の後、最後の朝食です。デザートには「クイーンニーナ」という最近の品種のとてもおいしいブドウが出ました。
部屋を片付け、休養村ともお別れです。閉園式では、お世話になった宿舎の方へお礼の気持ちを伝えました。
雷電くるみの里でお土産を買いました。家族や自分への土産を真剣に選んでいました。でも、最高のお土産は楽しく過ごせたことのお土産話ですね。おうちの人にお話をしましょう。
続いて、鬼押し出し園に向かいました。軽井沢近郊の紅葉が見事です。鬼押し出し園では行動班ごとに、浅間山の噴火でできた溶岩の上を歩きました。溶岩には様々な面白い形のものがありました。天気が良く浅間山がはっきり見えました。また、遠くには、本白根山などの景色も見えました。そして、お弁当も食べ、東京に帰ります。
全行程、天候に大変恵まれ、最高の移動教室になりました。
大田区休養村とうぶの皆様、教育委員会や関連業者の皆様、計画や世話をしてくださった先生方、準備を整えてくださった家族の皆様、そして、楽しく過ごした仲間への「感謝」の気持ちでいっぱいです。
















10月29日(水曜) 1年 タブレットの使い方
児童に配布されている新しい端末(学習用タブレットPC)の使い方を学習しました。
配布された端末のカバーに大田区のキャラクターマスコットがついているのを見つけると「あっ、はねぴょんだ」と児童たちの笑顔が見られました。
―今までの端末(学習用タブレットPC)との相違点―
・液晶画面(タッチパネル)自立式
・キーボード分離型
ということで、動画撮影、写真撮影等に分離するキーボードを落とさないように、また必ず両手で持つ等の注意事項を確認すると「強くなってる」「便利―意外とー」という声が聞こえてきました。
各自に配布されたログインID、パスワード記載カードを基に入力(各数字のみ記入する設定)すると「いったー」「イエーイ」と拍手をする児童も・・・「そうか、さっきは0を一つ多く入れちゃったんだな」皆の学習準備が終わると「まなびぽけっと」の「ミライシード」
「オクリンクプラス」「ドリルパーク」(かんじ、AIドリル、共通)の紹介があり、最後に「カルテ」で各人が努力した成果が見られることも学び、児童たちの学習意欲を高める工夫の紹介がありました。
10月28日(火曜) 6年 とうぶ移動教室(2日目)
移動教室2日目を迎えました。学園から麓を見下ろすと、雲海が広がっていました。
朝会で体をほぐし、朝食です。金平ごぼうがおいしいです。
午前の活動は、飯盒炊飯です。火起こし担当、カレー担当、飯盒担当がそれぞれの役割を果たし、チームで美味しいカレーを作りました。どのチームも手際が良く、10時すぎにはできあがった班もありました。どのチームのカレーもとても美味しそうです。片付けにも丁寧に取り組みました。
午後は、美ヶ原高原ハイキングです。往路の車中からは赤や黄の紅葉がきれいに見えました。標高約2000mの牛伏山に登りました。遠くには八ヶ岳連峰、富士山、南アルプスの山々がきれいに見えました。そして、高原の中を行動班でオリエンテーリングを行いました。美ヶ原高原は清水窪小学校で初めての行程です。担任たちの「美しい景色を堪能してほしいという気持ちが勝った、素晴らしい景色を見ることができました。
午前中の飯盒炊爨の食事が早く終わったので、おなかはペコペコです。夕食をしっかりといただきました。
夜は、キャンプファイアーです。火の神から、勇気の火、健康の火、友情の火を授かり、燃え上がる炎の下、ゲームやダンスを楽しみました。最後は、花火です。一人5本ずつの手持ち花火と、教員による仕掛け花火、ナイヤガラに大いに盛り上がりました。
今日は疲れたことでしょう。ぐっすりとおやすみなさい。






















10月28日(火曜) 業前 4年 スキルタイム(「読み解きタイム」)
本校では読解力向上のために月に1回「読み解きタイム」を実施しています。低学年は絵本等のブックトークや読み聞かせを通して、また中高学年はこども新聞等を活用して、記事を読み、設問に答えたり感想や要約を書いたり、またそれらを読み合ったり、書き溜めて行ったりして読む力、書く力を高めています。
中学年では「28さい市長 海外も注目」という2年前に初当選した兵庫県芦屋市長の話を読み解きました。文章の中には他に米大統領報道官のことも記載されていましたが、「次世代の100人」に選ばれた人名については全員が正解しましたが、現在28歳の市長は、何歳で市長になったかという問いでは誤る児童が15パーセント程いました。
プリントの裏には記事を読んで考えたことを自由に書く欄も設けられていました。
・26さいは、私と16歳しか違わないのにすごいなと思いました。
・若い世代に利益をもたらす改革を優先したのがすごい
・自分が「次世代の100人」に選ばれたないけど、自分の国の人が選ばれたのはうれしい
・他の市長はあまり若くないけど高島崚輔さんは若いときに選ばれてすごいと思いました
・・・・高島さんはすごい・・・私も選ばれてみたいと思いました
・私もアーティストやスポーツ選手に憧れているので、私も(新聞に)出てみたいなと思いました
・全国で最年少なのに選ばれてすごい・・・どんな工夫をしたのか知りたいです
・・・・住民と意見を交わしてとてもいい人だなと思いました
・高島崚輔さんは幼いころから市長になりたいと思っていたんじゃないかなと考えました
ワークシートを仕上げた児童は、読書や漢字練習などをしていましたが、中休みにも続けて書いて仕上げた児童もいました。
10月27日(月曜) 6年 とうぶ移動教室(1日目)その2
夕食は、ハンバーグ定食です。東調布第一小学校の皆さんと一緒にいただきました。
その後は、ナイトハイク。校長からの移動教室にまつわる注意事項の説明の後・・・・(詳細は内緒です)。
一日の終わりは、楽しみにしていた温泉です。金原温泉は、ナトリウムー塩化物・炭酸水素塩弱アルカリ温泉で、体がよく温まります。疲れを癒やしたら、ゆっくり休みましょう。わ一日お疲れ様でした。






10月27日(月曜) 6年 とうぶ移動教室(1日目)その1
今日から、6年生のとうぶ移動教室が始まります。自分のことは自分で、思いやり、優しさをもって「ルールやマナーを守って、最高の思い出をつくりにいきましょう。
バスは、始め少々渋滞に遭いましたが、その後は順調に進み、車内ではバスレクを楽しみました。車窓からは妙義山や浅間山が見えました。
松井農園に到着しました。まず、3人グループでニジマス釣りです。そしてリンゴ狩りでは、紅玉、アルプス乙女、シナノゴールド、秋映、シナノスイート、新世界の6種類の収穫体験と試食ができました。グループごとに収穫し、すべての種類のリンゴの味比べを楽しみました。その後、お弁当と一緒に焼きニジマスを食べました。自分たちで釣ったニジマスの味は格別です。
大田区休養村とうぶに到着です。開園式を行い、支配人や宿舎の皆様にあいさつをしました。今回は、大田区教育長をはじめ、教育委員会の皆様が視察にいらしていました。
児童の宿泊場所は、女子は宿泊棟、男子は古民家です。みんなワクワクしています。
宿舎では、まず、レクリエーションをしました。しっぽとりや進化じゃんけんなどを楽しみました。



















10月27日(月曜) 全校朝会 キャリア教育について(キャリアパスポートに照らして)
キャリアパスポートとは、小学校から高等学校までのキャリア教育に関わる諸活動について、特別活動を中心として各教科と関連付けながら自らの学習状況やキャリア形成を見通したり振り返ったりしながら自身の変容や成長を自己評価できるポートフォリオのことで令和2年度から始められました。
現在、各教室には「2学期のめあて」が掲示されており、今後は本日から3日間行われる6年生移動教室、また来月の学芸会に向けての目標、取組み、振返り等を重ねていきます。そしてキャリアパスポートには「なりたい自分」のイメージもつための工夫が施されています。
今朝は以前全校朝会で「AIに抗う棋士」という話の中で登場した藤井聡太名人の「将棋以外」の生身の人間像について、児童たちに問題を出したり、考えを促したりしながらキャリア教育の話を進めました。
・後悔について - やろうと思ったことを先延ばしにするのが癖。しかし大きな選択において後悔ということはないと思う・・・
・苦手な食べ物 - キノコ(細かく刻まれているものは問題ないが・・・)
・好きなこと - 「乗り鉄」―タイトル戦の移動でも独自にルートを選び、チケットを自ら購入(先の名人戦の会場―東京・大阪・大分・茨城・愛知・山形―)
・最近購入したもの - そんなにない(去年パソコンの部品の組み立てを・・・)
・今の夢について - 将棋を面白いと思えることが「夢」に向かっての原動力だったので、今後もそうありたい、面白いと感じることを大切にしたい
今日の話を通して藤井聡太名人の棋士としての職業「仕事」、大谷翔平選手のプロ野球選手としての職業「仕事」に向かう姿をどのように感じ取ったことでしょうか。小学校の段階は社会的・職業的自立にかかる基盤形成の時期とされています。「自分らしい生き方の実現を目指して」お子さんの「よいところ」「得意なこと」「好きなこと」「夢中になっていること」について話題にし、取組意欲の向上を図り、見守り、励まし等をともに行っていきましょう。
10月24日(金曜) 5年 SC科見学
「プラスチックとわたしたちの未来」の学習で、東京湾に流れ着くプラスチックゴミについて情報を集めるために葛西海浜公園での実地調査等を行いました。
バスを下車し、公園に向かう路上の会話―
「海のにおいがする」「海のにおいの元ってなんだか知ってる」「また(伊豆高原学園)移動教室に行きたいな」「ぼくは、プラスチック(利活用)賛成派―」「私も・・・だって(プラスチックは)生活に欠かせないもの」「でも、先生が小さいときは・・・弁当箱はアルマイトという金属、箸は木製、お菓子の入れ物はプラスチックだったかな・・・」
現地での学習は、葛西臨海公園職員(レンジャー)の指導のもとに進められました。浜辺、湿地は平成30年にラムサール条約湿地と認定され定期的に清掃活動が行われ、ごみ等は見かけることがありませんでしたが、その浜辺に打ち上げられた魚の骨についての話から始められました。
海浜での実地調査活動では、学校から持参した調査キットでマイクロプラスチィック等を採取しました。
「やったーナノプラスチック見つけた」
「これ、あの(レンジャーさんの話にあった)人工芝じゃない・・・」
「これ校庭のあみ(防球ネット)だよ」
「これは棒付き飴のやつだ」
「これらの貝のかけらは、あの鳥たち(スズガモ)が食べたからじゃないかな」
「これは(食品トレー)元の形、大きさがわからないね」
「アルミホイルも見つけたよ」
葛西臨海公園職員(レンジャー)の講義の後に質問を受けてもらいました。
・マイクロプラスチックをヒトが食べてしまう可能性はあるか
・有害な物質は、プラスチックが大きいほどヒトへの影響も大きくなるのか
・海のマイクロプラスチックごみは、再生できるのか
・プラスチックごみを増やないようにするには、どうしていったらいいのか
・顕微鏡で見なければ見えないプラスチックごみについて教えてほしい
・プラスチックごみがこの浜辺にくる理由は何か
午後は隣接する葛西臨海水族園を見学し、海に棲息する様々な生命を見つめ、その生態と見つめる中で環境浄化、環境保全等の必要性を学びました。
10月23日(木曜) 2年 SC科 東京科学大学研究室訪問
「キリンはかせになろう」で、10月2日(木曜)の上野動物園SC科見学の学習も踏まえ、「自分で選んだ動物に、どうして長くなったところがあるのか調べよう」というめあてでグループごとに調べ学習をしてきました。そして今日は更なる疑問や考えを東京科学大学生命理工学院准教授に伝え、キリンをはじめ各動物の生態や進化についての「授業」を通して深めました。
はじめに「どうしてキリンの首が長いのか」という疑問に対する児童たちの見解が発表されました。
・首の1本1本の骨が長くなっている ・遠くにいる「敵」の動物がよく見えるように長く伸びた ・生まれたときから長いからそのまま成長した ・はじめは短かったけど進化して長くなった ・・・・・
これらを受けて、「進化」について以下の生物を通して生物多様性の「授業」が続けられました。
・アフリカ産シクリット(熱帯魚) ・ハリネズミ ・透明なまず ・古代魚ポリプテルス
そして「授業」は大学生に行う「講義」と内容的には何ら変わるところがないーということが告げられると児童たちの表情が引き締まったようでした。
キリンに一番近い動物は児童たちも調べ学習で「オカピ」と理解していましたが、さらに「オカピ」に近い動物としてインドの地中から発掘された「シバテリウム」が紹介され、結論から言うと「どうしてキリンの首が長いのか」に対する答えは「・・・まだ・・・ない・・」ということでした。だからみんなが勉強して教科書にその答えを書く人になってほしいーとの話がされました。以下、都合上児童からの質問のみ列記します。
・キリンは何でバレリーナみたいにかかとが上にあるのか
・キリンが生まれた時の足の速さはどのくらいなのか
・キリンの腹の骨はどうなっているのか
・キリンが生まれたときにもう大きくなっているのはどうしてか
・キリンの爪がスリッパみたいになっているのはなぜか
・・・・・・
・ヘビに足がないのはなぜか
・テナガザルの腕が長いのは枝から枝へ移るときに便利だからか
・フラミンゴが片足で立っているのはどうしてか
・ハシビロコウは本当に絶滅危惧種なのか
・・・・エサのことでメス同士 戦うことがあるのか
最後に児童から以下の感想が発表されました。
・オカピの前のキリンの祖先の動物がわかってよかった
・先祖がヒトにもキリンにもいることをもっと調べたい
・キリンを調べることがもっともっと好きになりました
10月22日(水曜) 3年 国語 習字「土」
筆遣いに気を付けて縦画をかくというねらいの標記学習が行われました。
前回は筆遣いに気を付けて横画をかくというねらいで「二」という字を通して学習をしたので、横画の復習をしながら縦画を学びました。
初めに動画を視聴し、空書き、墨なし筆で練習後、毛筆での学習に移りました。
・縦画をかくリズムは ー「トン(始筆)・ツー(送筆)・トン(終筆)」
・適量の墨汁をすずりに出し、筆先を整え、肘は上げて、筆は立てるように
・姿勢合言葉は「足はペッタン、背中はピン、おなかと背中にグー1つ、紙を押さえてさあかこう」
「難しいな(縦画が)曲がっちゃう」「ゆっくり筆を運ばないで、スーっとだね」
「トン(終筆)が上手にできたね」「(トンは)最後だからしっかりやらないと思って・・・」
「書き順、間違えたけど、うまくかけたー」「字が、三角形になるように・・・」
「筆先の動きがきちんと残っているね」「字をもう少し下にかいたら最高傑作だったのにな」
「名前はまっすぐにかけたけど・・・」
「〇〇さんと□□くんが上手。トン・スー・トン・・・特にスーがうまい」
教室には2学期のめあてカードが掲示してありました
・字を丁寧にかく
・字をきれいに書けるようにがんばる
・宿題をきれいな字でやるようにする
・もっともっと漢字をきれいにかく
・漢字ドリルできれいな漢字をかく
・字がきれいになりたい ・・・・・・・・
毛筆習字のほか、硬筆でも「上」「下」等の字で今日の学習を生かしていきます。
10月21日(火曜) 音楽朝会 4年 連合音楽会 壮行会
今週23日(木曜)の大田区区民ホールアプリコ大ホール標記音楽会に向けての会が行われました。4年生はこれまで、休み時間そして音楽室、体育館での合同学年練習、各家庭での自主練習と練習を重ねてきました。
今朝諸準備のために他学年よりも早めに教室に入ってきた児童たちは、皆慌ただしく朝の学習準備、着替えを行っていました。
「衣装どうしよう・・・どっちがいいと思う・・・」
「私もリボン付けた」
「あっ、靴履き替えるの忘れた」
「私はうちの〇〇から借りてきたけど・・・似合うかな・・・」
体育館では早めに整列し、保護者、他学年児の入場を待ちました。
「私、緊張しない・・・でもやっぱりしてきた・・・」と呟く児童もいましたが、ほとんどの児童は無言でリコーダーや鍵盤ハモニカの運指を確認したり、学習振り返りカードと一緒にファイルに挟んだ楽譜を胸に抱いてリズム、音階を辿ったりする姿が見られました。
発表する曲は 合唱「すてきなともだち」と合奏「ソーラン節(ロック調)」―初めの言葉で児童が言ったとおり、アルトパートにつられないように、また漁師の動きを取り入れ「一つの風」となる堂々とした発表となりました。
そして最後に6年生代表児童から「アプリコホールは広くて大きいから、しっかり」とアドバイス、励ましの言葉を受けました。
10月20日(月曜) 3年 理科「音のせいしつ」
本校では校内研究の研究主題に迫る3つの取組の1つとして「清水窪学びの10のプロセス」を掲げています。「10のプロセス」とは 1.自然事象への働きかけ 2.問題設定 3.予想・仮説の設定 4.検証計画の立案 5.結果の見通しの把握 6.観察・実験 7.結果の整理 8.考察 9.結論の導出 10.振り返りと活用 です。
本時の授業は前時の復習から始まりましたが、「考察」の「予想と比較して結果をもとに考える」という意味が児童には難しいようでしたが、2名の児童の発言から「考察」の理解を深め、9.結論の導出 10.振り返りと活用 につなぎました。
そして前時の実験で使った様々な楽器に皆空洞があるということ、またトライアングルには空洞はないけれども、どのようにして音を伝えているかを考え、1.自然事象への働きかけ 2.―「音の大きいときと小さいときとではもののふるえ方はどのようにちがうのだろうか」という問題設定を行いました。
そして音を伝えるためには「もの」が必要だということから様々な声が聞こえてきました。
「机に耳を当てて脚の部分をたたくと音が聞こえたということは・・・脚から順に伝わって・・・」
「『もの』がなかったら音が聞こえないのだから・・・宇宙とかに行ったら・・・」
「プールなどの水の中だったら・・・」
「寒くなると息が白く見えるから、見えない空気でもわかるかも・・・」
「さあ、問題(2.)がはっきりしたから今度は予想だね。」
「理科はやっぱり問題が大事だね。」
10月17日(金曜) 1年 生活科見学
標記学習のために多摩川台公園に行ってきました。最寄り駅の多摩川駅までは徒歩、電車と友達と手をつないで―10日の全校遠足では6年生に手をつないでもらいましたが、今回は・・・配布したしおりには「やくそく」として道路歩行、電車車内、集団行動の3点が記され、事前にも指導が行われました。道路等は2人から3人の「バディー」(プールでの学習で既習)のままの歩行で、先週の全校遠足と同じく6年生と手をつないで行動したように上手に行えていました。電車内では「僕も座りたいよ」という声や、早々に気分の悪くなった友達に「袋あるよ」と声をかけたり、身を乗り出して座っている友達を制止したりする姿が見られました。
今回の見学では、拾って持ち帰るものを「宝」と呼んでいましたが、多摩川台公園について間もなくの四季の植物園公園散策では、早速「宝を1つ見つけた」と教えに来たり、花弁を拾ったり、「何か黒いものがいた」と空を見上げる子がいました。
次の水生植物園での児童たちの声を拾うと・・・
「ここにザリガニいるんだよ」「あの赤いのがザリガニ!」「こわい・・・」「あっ、魚!小さいからメダカかな」「陰にならないように、日が当たるようにすると見えるよ」「あそこにカエルがいます!」「鮒がいた!めちゃめちゃでかい!」あれはアカタテハだよ」「♪開いた開いた、何の花が開いた、ハスの花が開いた・・・」「ハラビロカマキリ発見!」
そして管理事務所前広場(古墳展示室)でのクラス写真撮影前後からは、ドングリ、かさ(殻斗)枯れ葉、枯れ枝等の「宝」をたくさん拾いました。
「見て、見てーこんなのー」「みどり、ピンク、クリーム色も」「私はエメラルドグリーンのを見つけたいな」「私のはつやつや」「新品だね」「生まれたてなんだね」「よく見ると、たくさん落ちてるね」「こんなつやつやの石を見つけた」「この石は小さいけどおにぎりみたい」「2つのかさ(殻斗)がついてる」「私のは2つのかさ(殻斗)が互い違いに付いてる」「大きいドングリ見つけた」「どっちが大きいかな・・・」「この(松の)枝、リュックに入るかな・・・ポキッと折れば・・・」
袋いっぱいに「宝」を入れてさらに「宝」を探していると、いつの間に「宝」が足元に広がってしまった様子を見て、「宝」集めを一緒に手伝ってくれた友達も・・・また一人の児童が鉄柵の向こう側に大きなドングリがあるのを見つけて、初めは小枝を使い腕を伸ばして「格闘」していましたが、それを見ていた児童が策の間から足を伸ばし入れて「格闘」・・・次第に「格闘」する児童が増える中、私のほうを見て、「・・・そのネクタイは・・・」の声も。帰りは鉄柵裏の歩道を通ったため、子どもたちが「格闘」していた大きなドングリがたくさん拾えました。
今日は気温がかなり上がったようで、セミの鳴き声が聞こえると「エー」「おかしい、おかしい」「何でー」という児童たちの反応が、また、ある児童が多摩川を挟んだ丹沢山系の向こうを指さして「小さな富士山だー」と叫ぶと「ヤッホー」「ヤッホー」と大勢の声が響きました。暫くしてある児童がポツリと「今日は天気が良くてよかったね」と呟いていました。
帰校し、5時間目の1年生の教室では持ち帰った「宝」を使って早速、学習が進められていました。
10月16日(木曜) 4年 道徳 「相互理解・寛容」
「このままにしていたら」という教科書資料を使い「みんなの場所」で気をつけなければいけないことはーという問いで授業が始まりました。資料の中で「レジ袋が飛んでしまった」様子を見た時の登場人物の心情についての考えでは・・・
・きっと、だれかが拾ってくれるだろう
・1つくらい・・・
・もう使わないから・・・いいんだよ
・(あんなところまで取りに行くのは)めんどうくさいからな・・・
そして「自然と仲良くゴミは持ち帰り」という看板が次第に大きくなるような気がしてくるーという文章から、改めて「みんなの場所」で気をつけなければいけないことーについて隣席の友達との話し合い後に発表をしました。
・「みんなの場所」ではやはりルールやマナーを守るということが大切になってくると思う
・話し声などの音量にも気を付ける。(校外学習のときなど)興奮しても落ち着き、道路は広がって歩かない。
・電車の中では、しゃべらない、走らないーお年寄りとかいろいろな人がいることを考える
・自然のもの(葉や花等)をとることもいけない
・人の歩いているところを自転車でこがない
・遊具では独り占めをしないで、ゆずる気持ちをもつ
・場所をたくさん取りすぎないように、必要な分だけの場所を使う
・たとえは野球をしていたら、野球をしている人たちと同じルールやマナーを守る
・どこでも礼儀正しくするようにする
10月15日(水曜) 6年 保健 薬物乱用防止教室
本校薬剤師をゲストティーチャーに招き、標記の授業が行われました。
まず自己紹介として日頃、プールの水質検査、教室の照度検査、保健室の衛生検査等をしてくださっていることを話し、次いで薬、酒、たばこ、麻薬の順で身体に及ぼす害について講話をしていただきました。
薬は3つに分類(内服薬、外用薬、注射薬)、体内で主に胃や小腸で吸収、さらに作用としての主作用、副作用の話から処方薬は処方された人以外は服薬してはいけないという話になると「お母さんが、自分の薬を人にあげたらダメと言っていました」と発言する児童がいました。
酒については、各人のアルコール分解酵素量の違いがあるものの、その作用として集中力、判断力の低下、性格が変わる、意識がなくなる等、脳に影響を与える一方、20歳までは脳細胞が増え続けることの話がありました。そしてアルコールにより委縮した脳と正常な脳の比較写真が示されると、皆、息をのんで画像に見入っていました。
またタバコについては精神安定、リラックス作用があるものの、ニコチンには中毒性があり、体に害のある成分が200種類以上あることを学びました。そしてタバコの煙を水に溶かしていくと水が黄色から茶色に変色していく様子が示されると、学習メモを取っていた児童たちの手が止まりました。
さらに最後の麻薬については、幻覚、幻聴の出現、脳はもちろんのこと、歯、胃、心臓等様々なものに影響を及ぼすこと、そして薬物については身近な人、モノそしてSNS等を通じて
誘惑の手が伸びていることを学びました。以下、児童の感想から・・・
・友達から誘われても薬物を使ってはならない。薬物を使ったら心や体、社会に大きな影響を及ぼす。
・心身を守る強い心を、薬物で壊すのはよくないことだし、もったいないと思う。
・幻覚、幻聴・・・心も体も壊れてしまうと同時に周りの人たちも傷つけてしまうことがわかった。
・薬物をやると気持ちよくなるだけだと思っていたけど、体に悪い影響を与えると知った。
・薬物乱用は、自分のこと以外にだれかに迷惑をかけることだとわかった。
・悩んでも薬物に対する「怪しい」という気持ちを消さず、誘われても「怪しい」という気持ちを再確認することが重要
・医薬品であっても危険だということを学んだ。使い方を確認してから使うように注意したい。
10月14日(火曜) 2年 体つくりの運動遊び「いろいろなうごきあそび」
低学年の体つくりの運動遊びは「体ほぐしの運動遊び」及び「多様な動きをつくる運動遊び」で構成され、体を動かす楽しさや心地よさを味わうとともにのびのびと体を動かしながら、様々な基本的な体の動きを身に付けることを主にねらいとする運動遊びです。
準備運動では5名の係が掛け声をかけながら皆を先導しました。そして初めの運動遊びは床に大の字になり,仰向け姿勢から、指導者の合図で素早く起きあがる運動を繰り返しました。誰が早く起きれるかを指導者と見学児童で見ていましたが、それらの児童に早く起きるコツを聞くと・・
・起き上がろうとするときに、床を強くたたくといいんだ
・起き上がるときの手はなるべく体の近くの床に力を入れる
・足は少し開いておいた方がいいみたい
・足をグッと腰のところにもってきて体を小さくする
次に1メートル程の間隔をあけて2人組で背中合わせに体育座りをして、指導者の合図でその中央に置いた紅白帽を取るという運動遊びをしました。そしてまた児童たちに動き方コツを聞くと・・・
・帽子をつかんだら横に取るようにする
・先生の合図は耳を澄ましてよく聞く
・始める前に帽子の置いてある場所を確かめておく
・足で床をけって、おしりをうまく滑らせる
最後に2つのボールを使ったドッジボールを行いました。学習の振り返りでは、
・逃げ方が上手くなりあまり当てられなくなった ・ボールにいっぱい触れるようになった ・いっぱい当てられた ・上達した ・・・等の発言がありました。
10月10日(金曜) 全校遠足 (都立林試の森公園)
校庭に全校児童が集まり、出発式では6年生は昨年度の6年生の姿を思い出して頑張り、5年生は6年生をできるだけサポートするというこれから始まる全校遠足への意気込みを皆に伝えました。そして式後の出発まで、低学年児童のトイレ等の付添や、公園でのゲームについての打合せをしたり、いたずら等をする児童へ注意、仲介、また下級生にゲームをセッティングしてやらせたりと6年生を中心に早くも上級生が活躍する姿が見られました。
電車の中では「どこで降りるんだっけ」「武蔵小山だよ」「混んできたから、次の駅では1度降りた方がいいかもしれない」「公園では6年生がいろいろなゲームとかのお店をやってくれるんだって」「わー、楽しすぎて時間がわからなくなっちゃうかも」という会話が聞こえてきました。以下、公園での児童たちの会話、呟きをランダムに記します。
「セミかチョウの羽を見つけちゃった」「これは形から見るとトンボだな」
「カブトムシの角・・・みたいな枝を見つけた」
「どんぐり、いっぱいだね」「(同じ班に人に集めるのを)手伝ってもらったんだ」
「(二又の30センチ程の枝に)殻付きのどんぐりだ」「これはレアだね」
「つるつるな葉っぱがあった」「これは今どきめずらしいね」
「プラタナスの実、2つつながっているのは珍しいね」「プラタナスの実、東工大にもあったよ」
「両足、蚊に刺された」「(養護教諭の)山本先生、あそこにいるよ」
「落とし物・・・〇野□子・・・「1班、◇◇先生が担当だね」「届けてくる」・・・「〇野□子さん、初めて知った」
「(ケイドロ中手に大きめの葉っぱを持って)暑くなったらこれで扇ぐんだ」・・・・・
帰校式では、高学年児童から来年度に向けての熱い決意が述べられました。
10月9日(木曜) 3年 社会科 消防署見学
電車を利用し、田園調布消防署までの校外学習を行いました。
車庫に並んでいる指揮車、はしご車、ポンプ車の順で説明を受け、後半庁舎内でパワーポイントを使っての内勤(毎日勤務)等の説明、そして事務室、仮眠室、食堂を見学しました。
説明を受けているとちょうど指揮車が帰庁し、業務の様子を見ることができました。はしご車は強風のため伸ばした様子(30m)は見ることができませんでしたが近くで見学することができました。
ポンプ車についてはどのようにして消火するのか、また消火以外の機能等について詳しい話がありました。ポンプ車1台に長さ20mのホースが30本も積まれていると話があると「えーっ」という驚きの声が上がりました。ホース5本だと20m×5で100m、積んでいるホース全部つなぐと20m×30で・・・そしてポンプ車には1000リットルの水を積んおり、1分間で200リットルほど放水すると・・・1000÷200で・・・と計算の勉強になりました。そして防火服を2名の署員が素早く身に着けるパフォーマンスがあり、1名がやや遅れていると「がんばれー」の声援が続きました。防火服20キログラムに酸素ボンベ10キログラムそれに9m伸ばせるはしごやホースを持って現場に向かうとすると・・・児童たちの頭の中で今度は足し算が始まりました。
交代制勤務員(3交代制)に出勤後の業務で「大交代」に続いて「点検」の話を聞く前に、偶然帰庁した先の指揮車の車輛「点検」を見ることができました。すると「そういえば、ぼくも自転車の点検をするよ」「ブレーキとかが利くか確かめるよ」「・・・ベルは余り確かめないかな・・・」という声が集まってきました。
児童たちからは
・車庫奥の壁面に掛けていたボートを見つけて、その用途が洪水、河川・池等事故対応で用意していること
・消防署が火事になった場合について疑問をもち、消防署でも避難及び救助訓練を行っていること
等、よく気づき、またよく考えた質問が多く出ました。
3年生にとっては、明日の全校遠足で1,2年生を引率する事前学習もできました。




10月8日(水曜) 「笑顔と学びの体験活動プロジェクト」
東京都教育委員会が提供する標記活動で、今年度は劇「ちぇんじ 図書室のすきまから 彩花の背中を押した図書室の魔法」を全校児童で鑑賞しました。早朝から来校した劇団関係者の方々が、多くの大道具、各種機材等が会場の体育館に運び込む様子を、登校後入校を校庭で待つ数名の児童がじっと見つめていました。1年生の中には観劇するということが理解できず、「今日、何かが来るんだよね」と言ってくる児童もいました。
3校時、すっかり準備が整った会場に1年生から順に前方から詰めて座っていきました。ここでもまだ「観劇」「学芸会」がどのようなものか分からない児童たちがいて、「皆が前のような舞台に立って劇をするー『お遊戯会』のようなもの」と言うとほとんどの児童たちにわかってもらえましたが、中には「やったことない」という児童もいました。
舞台は、本棚を模した何枚もの大道具の上からランダムに配置されたひらがなの文字をじっと見つめ、「『あ』が2つあるー」「あ・・・じ・・・」「・・か・・・る・・・」―「さあはじまるよ」「あいさつ」と変化していく文字を児童たちは口にしていきました。
児童たちは劇の話の中にすっかり入りこんで・・・
・感じたことを口に - 「えっ、そういうのって」「家にもあるよ」・・・
・役者への語り掛け - 「何で話さないの・・・」「後ろだよ、後ろ」・・・
・座り方の変化 - 体育座り ー 正座 ― 膝立ち ー
・自然と拍手 - 初めの言葉が終わり、いよいよ劇が始まろうとする時
挿入歌に合わせて踊る役者さんに向かって
終末にはこの劇が、人見知りや大人しい性格の克服から自分を嫌いにならないこと、さらに自分の好きなものをもち、大切にすることをテーマにしていることが述べられました。そして演目にあるように、劇中には主人公の好きな多くの本が登場しました。
「はだかの王様」(アンデルセン)
「ムーミン」 (トーベ ヤンソン)
「ドリトル先生」(ヒュー ロフティング)
「蜘蛛の糸」 (芥川龍之介)
「私と小鳥と鈴」(金子みすゞ)
終了後、学年ごとに退場するときに役者さんに皆が笑顔で手を振りながら退場していきました。そして6年生は座っていた椅子を片付けながら「学芸会、頑張ります」という言葉を伝えていました。
劇団の方々からは、児童たちがいきいきとして温かい雰囲気の中で演劇ができたと話していただきました。そして戴いた寄書き色紙を早速各学級用にカラーコピーをして配布しました。
10月7日(火曜) 5年 SC科「プラスチックと私たちの未来」
身の回りのプラスチック製品についてのメリット、デメリットを整理し、それらが引き起こす環境問題について目を向けさせる授業が行わえました。
プラスチックのイメージとして・・・
・軽い ・硬い ・便利 ・ないと不便 ・お店でよく売っているものに使われている
・身近なもの
プラスチック製品についてのメリット
・加工しやすい(形を変えやすい)
・生活の中では必須と言っていいほどあちらこちらにある(野菜を包んでいる袋や消しゴムも)
・生活の中でいろいろと活用できる
・プラスチックがないと生活が限られる
・ペットボトルとかはリサイクルできる
・自然分解するプラスィックが開発されている
・水に強い
プラスチック製品についてのデメリット
・マイクロプラスチックを海の生き物たちが食べてしまう(ニュースをよく聞く)
・漁獲高が減っているというのに、ますますマイクロプラスチックで影響を受ける
・マイクロプラスチックは回収が難しいいわれている
・環境に悪いし、ゴミとして多く出る
・地球温暖化がますます進むと思う
・プラスチック製品ではない代用できるものがある
・きちんと処分ができているか、不安なところがある
この学習は、10月24日(金曜)のSC科見学につなげていきます
10月6日(月曜) 3年 国語科「ちいちゃんのかげおくり」
この教材は、第二次世界大戦中の日本を舞台に、空襲で家族を失った少女(ちいちゃん)が、最後に一人で「かげおくり」をする物語です。明るい家族での「かげおくり」から始まり、空襲で家と家族を失い絶望的な状況のなかで一人「かげおくり」をすることで未来を奪われた子供の悲しみを表現しています。
そして本時はちいちゃんの心情を考え、グラフに表した上その理由をワークシートにまとめグループで伝え合いました。まず、心情とは何かという質問が出ましたが、心、思い、・・・等意見が出る中で「気持ち」という言葉に置き換えて考えていこうということになりました。(中には「心情の『情』は『なさけ』と読むんだよ。」と周囲の友達に伝えている児童もいました)
本時の学習範囲の第一場面を振り返り、出征するお父さんについて、
・戦争に行こうとしていたお父さん ・戦争に行かされたお父さん と表現したり、
「かげおくりをしたちいちゃん」について
・かげおくりをしているちいちゃん ・かげおくりを教えてもらったちいちゃん ・かげおくりをしたことがあるちいちゃん
等、表現したりする中で場面の様子を適切に捉え、ちいちゃんの心情に迫りました。
今回は、ちいちゃんの気持ちグラフ「マイナスー(悲しい感情)」の理由についてのみ記載します。
・戦争でおにいちゃんとかげおくりが出来なくなったから
・おとうさんが戦争に行き帰ってこれるか心配だから
・体の弱いお父さんも戦争に行かなければならないので心配だから
・かげおくりをした空は楽しいところではなく、こわいところに変わったと書いてあったから
・かげおくりをしたときにちいいちゃんが「すごおい」と言っていたのにできなくなってしまったから
・お父さんが戦争に行ったことをちいちゃんが知ってしまったから
・」お父さんが戦争に行って会えなくなり、かげおくりができなくなったから
10月4日(土曜) 学校公開 引き取り訓練 防災訓練
学校公開2日目。今日は特別時程で普段より15分早く始業しましたが、朝から多くの保護者の方々が来校されました。そして1年生合同体育「マットあそび」、2年生図工工作「すてきなぼうし」、3年生外国語「What do you like」、6年生音楽「和音のひびきや重なりを感じ取ろう」社会「室町文化―墨絵にふれよう」等、1校時から児童たちの学習活動量の多い授業が展開されました。
中休みは朝の放送で「・・・今日の天気は晴れ、気温22度、気圧1018ヘクトパスカル。今日は涼しいので中休みは校庭で元気に遊びましょう」という放送委員の呼びかけが皆に届いたのか、大勢の子どもたちが校庭に出て、保護者の間を縫うように鬼ごっこをしたり、ボール遊びをしたり、固定遊具で遊んだり地面を掘って虫などの飼育の準備をしたりする姿が見られました。
中休み前後の廊下の様子はいつも以上の混雑ぶりで、児童たちの気分もかなり高揚した状態で休み時間、授業に入って行きました。そして中休み前後は教室に入れないで廊下で参観していただかなければならない状況になってしました。
そして4校時は警戒宣言の発令を受けての引き取り訓練を行いました。下校時には校長講話にあったように、発災時を想定して多くの話し合いがされたことと思います。
午後には地域防災訓練が行われ、防災倉庫の物品確認、発災時避難所居住スペースの設営および雨天の中、応急給水栓の操作確認も行いました。
10月3日(金曜) 学校公開 道徳授業地区公開講座
サイエンス朝会から学校公開が始まりました。今日のサイエンスは「ダイラタンシー現象」について、片栗粉と水を使った実験をしました。地震による液状化現象、砂浜の砂も同じ原理と考えられているようですが、混合物に(割りばし等で)力を加えると硬化したり、暫くすると自然に軟化したりする不思議さに児童たちは各学級の電子黒板の映像に釘付けとなっていました。中休みになると早速、校長室前の実験コーナーで朝の実験の再現をしている児童たちの姿が見られ、5,6年生が下級生に実験のやり方を教えたり、話をしたりしていました。
中休み頃には、全校3分の1以上の保護者、地域の方々の来校を受け、多くの方々にチャイムが鳴る前に時計を見て3校時の授業に向かう児童たちの様子も見ていただきました。、ジャングルジムに上っていた児童たちは「そろそろ教室に戻るんじゃない?」と周囲の「気配」を感じ急いで教室に向かっていました。休み時間には、遅れてきた友達を快く仲間として迎えたり、多くの児童たちに囲まれながら昨日捕まえたという「幼虫」を入れた飼育ケースを大切に運んでいたり、体育倉庫から借りたボールを2人で責任をもって片付けに戻ったりする児童たちの姿も見られました。
午後は全学級「特別の教科道徳」の授業および道徳授業地区公開講座が行われました。
5校時は各教員が本年度の「特別の教科道徳」重点指導目標「善悪の判断、自立、自由と責任」「親切、思いやり」「生命の尊さ」「自然愛護」から1つの項目を選択して授業を行いました。
6校時の道徳授業地区公開講座は保護者、学校運営協議会委員をはじめ地域の方々、そして3,4,5,6年生が体育館に集まり、「命の大切さを学ぶ教室」というテーマで講演がありました。お子さんを交通事故で亡くされて9年たった今、漸く明るく振舞えるようになったという講師の話は、何度もステージから降りて児童たちに語りかけるなど、正にテーマの「明るく、正しく、美しい交通安全」に相応しいものでした。
・より、交通安全を大切にしていきたい
・これからは、横断前に左右を必ず確かめます
・交通事故でだれも死なせないようにしたい
・この取り組みが全国に広がっているのがすごい
・1パーセントでも「危険」があったら確認したり、工夫したりしたい
・信号が青になってもすぐに渡ろうとしない
・辛いこともあったのにそれを乗り越えてすごい
等、会の終末に児童や地域の方から多くの感想が出されました。
10月3日(金曜) サイエンス朝会「片栗粉(でんぷん)の不思議」(ダイラタンシー現象)
来週の月曜日、10月6日は中秋の名月です。この日に団子をお供えする風習があります。
みたらし団子の餡は、砂糖と醤油と水と片栗粉(でんぷん)で作ります。
片栗粉に水を入れると、どろどろとした液状になります。
この液状のものに力を加えると、硬くなりますが、力を抜くと、元の液状に戻ります。
これは、ダイラタンシー現象と呼ばれるものです。ダイラタンシー現象とは、水に片栗粉のような粒状の固体が混ざった混合体が、ゆっくりと力を加える場合は液体のように振る舞うのに対し、強く素早く力を加えると固体のように硬くなる現象です。この現象は、強く力を加えると粒子の隙間が水で埋められ、粒同士が密に並ぶことで固体化することによって起こります。
この性質を利用して、次のようなことができます。
プラスチックコップに水と片栗粉を混ぜたもの(水100mlに対して片栗粉を200g混ぜたもの)をプラスチックコップに入れます。そして、割り箸をゆっくりと差し込みます。
割り箸をゆっくり抜くと抜けますが、早く抜くとプラスチックコップが持ち上がります。これは、摩擦力という力が加わって、固体のように硬くなったためです。
校長室前に置きますので、試してみてください。
10月2日(木曜)2年 SC科見学 上野動物園
2年生はSC科で「キリン博士になろう」に取り組んでいます。事前に上野動物園動物解説員とのオンライン授業を通して今日の見学の意欲を高めていました。
今日は清々しい秋晴れの中、キリンと、体に長い部分がある動物を中心に観察しワークシートにスケッチや気がついたことを熱心に書き込んでいました。
・キリンの脚は細くて真ん中が膨らんでいる。
・キリンのしっぽは先が黒くて筆みたいにふさふさしている。お腹ら辺のところまで届いて虫を払っていた。
・レッサーパンダのしっぽは長い、思ったより大きい。
・イグアナの頭が小さいけどしっぽは長い。オオサンショウウオのしっぽも長い。
・フラミンゴは足が長くてお腹が小さい。
・ワニは尻尾は長くて歯がギザギザ。
など様々なことに気づいていました。
最後に動物解説員の方に質問をし、丁寧に答えてくださいました。
今日のたくさんの学びをまとめ、キリン博士を目指します!








10月2日(木曜) 5年 家庭科「ミシンでソーイング」
「下糸と上糸を準備して安全にぬおう」というめあてで本単元2時間目の授業が行われました。前時は糸を使用せずに「空縫い」を、今日は下糸と上糸を用意して直線縫いと「折り返し縫い」(直線で螺旋状に)を行いました。
5,6年の家庭科実習では、清水窪わくわく応援隊のお声がけで毎回、保護者、地域の方々に実習支援をお願いしていますが、今日は5名の方に御来校いただきました。
授業では、ミシンの基本として以下のことを確認しました。上糸が下糸をすくう様子を目の当たりにすると教室内は「あー、マジック」「マジックだ」という驚きの声があちらこちらからあがり、糸切り器がミシンについていることを知ると、その機能の良さに「ワォ」「ホー」という声が洩れました。
そして、「ミシン学習の基本」として以下のことを確認しました。
・針棒の正面に座る ・縫う時以外は電源をOFFにする ・押さえは静かに、最後に(針→押さえ) ・はずみ車はいつも手前に
さらに「友だちは見るだけで、手は出さない」という「大原則」を守ることも確認しました。
「手、近いよ、近いよ。」「もうちょっと手前かな・・・」「指、指、指―」「電源切るのが先―」「止まれー」 「フゥ」「ありがとう。」
めっちゃズレちゃったー「ズレてもいいよ。どうしても直したい人は少し戻してからやるよ。」
先生、変な音がー「調子が悪いからミシンを交換しましょう。」
「あっ、糸が抜けちゃった」「電源切って待ってよう」「ここ・・・切ってもいいよね」―「うまいーその調子」「添えるのは指先だけー」
実習が進むと、いろいろな声が聞かれ、懸命に取り組む児童たちの様子が見られました。
10月1日(水曜) 6年 体育「バスケットボール」
本時のめあて「パスを出し合ってゴールを決めよう」を確認後、準備運動を経てチームごとに決めた練習を行いました。
準備運動、そして「チャレンジタイム」では、めあてに向けてのチームの考えをまとめ、これからの練習内容を話し合いました。そしてチーム対抗のゲームでは、パスをつないでゴールを決めるためにはどんなことが大切か考えて学習に臨みました。
そして「チーム内で声を掛け合いながら、協力してパスを出していく」という点では「その言葉かけはよくないよ」と注意されることもありましたが、児童たちからは、元気な声でまた指導者のねらい通りに思いやりを大切にした言葉が聞かれました。
「オー、ナイスカバー、ナイスシュート」「あー、ごめんごめん、大丈夫、大丈夫」
「攻めること、優先」「OK、OK、そのまま、そのまま」「シュートー惜しい」
「やばいと思ったら後ろにパスして」「ヘイ、マイボールこっちからだよ」「〇〇(さん)来るぞ」「ドリブルしてーシュート」「〇〇(さん)マーク」「守れー攻めさせるな」「マーク、マーク、取れるよ」・・・
指示する言葉かけが多くなりましたが、ゲームではフェアなプレイで皆、良い汗をかいていました。
以下、授業中に書いた学習カードからー
〇本時で学んだこと
・相手のパスを取るときに意外と痛くないことに気づいた
・速いパスだとあまりカットされないことが分かった
・2回目の作戦会議が生きて、パスをもらうことができた
・初めてゴールに入れられた。コツがつかめてきた
・前方でフリーな人にパスを出すことができた
〇次時の学習に向けて
・パスばかりしてシュートをしなかった。次はパスを受ける側になりたい
・視界が届かない後ろも見るようにしたい
・もっと積極的にボールを取りに行き、またパスしやすい位置に動きたい
・相手がいないところに行けなかった。次は相手がいないところに行きたい
・次はシュートの練習を中心にしたい
9月30日(火曜) 午前中の1年の学習から・・・
1校時の1年生の教室に近づくと元気な歌声が聞こえてきました。また歌唱と鍵盤ハモニカを交互に使う「なかよし」の練習も行い、アップテンポの校歌のメロディーが流れると児童たちは一斉に片づけを始めました。また隣の教室では「カタカナ大作戦」と銘打ってグループ代表児童たちが黒板に様々なカタカナを使った言葉を書いていました。そして電子黒板のタイマーが「0」に近づくと児童たちは声を掛け合って急いで自席にもどり、良い姿勢で担任の言葉を待ちました。3校時は算数「10よりおおきいかず」で2学級を3クラスに分けて丁寧な指導が行われました。そして4校時は両学級とも学級活動で、初めての係活動ポスター作りをしました。カタカナは今学習しているのでひらがな中心で・・・(中には漢字を使いたがる児童もいましたが・・・)
・よみきかせががり 早速、昼休みから行うと、本も準備してやる気満々
・マジックがかリ 「まだやらないんだ。練習してから・・・」
・ダンスがかり 「練習中、邪魔しないでください。踊ってほしい曲を紙に書いてこの箱に・・・」「かっこいいのとかわいいのが混ざったダンスをします」
・ニュースがかり 「みんなの誕生日紹介―学童に紙が貼ってある!アンケートも取ります」
・こうさくがかり 「作ってもらいたいものを言ってください」「今、ロボットを作っているので、空き箱を持ってきてください」
・ほんやさんがかり 「作った本は、葉っぱや、石などのお金で買うように・・・」
・しゃしんアルバムかかり 「学校の写真や、みんなが笑った顔の写真をタブレットPCで」
・クイズががり 「当てた人に景品を作ります」
・おわらいがかり 「中休みや昼休み時間に・・・」
・おりがみがかり (もうすでに製作を始めて、籠の中に・・・)
なお、係名の「みんなわらえる」「かわいい」「かっこいい」等の言葉は省略しました。
9月29日(月曜) 3年 音楽「リコーダーと友だち」
初めに「校歌」「大切なものは」の歌唱後、9月11日(木曜)の講習会で見せてもらった、リコーダーに息を吹き込まずに「穴」を塞ぐだけで音を出す練習をしました。まだ人差し指1本で1つの穴を塞ぐ「シ」の練習ですが、個人練習の成果を皆にきいてもらい、「シ」の音が聞こえたら挙手をするということを全員一人ひとりが行いました。
そして「みんなが気持ちのよい音色でふこう」というねらいで授業を進めるということを伝え、「みんな」には友達は勿論、自分も入るということを確かめ、そのためにはどのようなことに気をつけたらいいかを考えさせました。
・息の量 ・タンギング ・リコーダーと体の角度 ・手の構え方 ・・・等、多くの考えが出て、適切な「息の量」を自身の手のひらで感じ取る練習等を経て、最後に「シ」のみの曲「ちょっとまってね」を演奏しました。
ワークシート「ふりかえり」から・・・
〇思い通りの音が出せたか
・タンギングのトゥートゥーを工夫してできた
・息の量を変えるだけで音が変わることに気が付いた
・トゥートゥートゥーとしゃべるように吹くとはっきりした
・友達の息と自分の息の量が同じになるように調整した
・角度が変わると音も変わるとわかった
・気が付いたことは息を使いすぎないこと・・・
〇これから自分で気を付けたいことを考え・・・
・前よりタンギングが上手くなったけど、まだ完ぺきではないので次回頑張りたいです
・次はタンギングを二重丸にしたいです
・リコーダーの持ち方で少し注意されたので次回は気を付けたいです
・もっと穴の大きさを考えてリコーダーをふきたいです
授業が終わると、リコーダー管内部をきれいに拭った児童から個々に「ありがとうございました」等の言葉を残し退室していきました。
9月26日(金曜) こどもまつり
校庭遊びの行える日が続くようになりましたが、ここ数日は内遊びをする児童が目立ちました。内遊びといっても、そのほとんどが今日のこどもまつりの準備をでした。「これ、転がらないよ。どうする・・・」「できたの、どこ置いとこうか」・・・
校庭の防球ネットに掲示した各学級のポスターに見入る児童、友達と下校中、「明日、めっちゃ楽しみ」「『コリント』って・・・」「これ私たちのクラスの」という声が聞こえてきました。また「明日こどもまつりだから、(今日)いろんな先生たちが(学級に)来たー」「明日、〇年◇組に来てくださいー」と話しかけてくる児童もいました。
●各学級の店名
1年1組 すいかわり 1年2組 さかなつり
2年1組 なげたものはなんでしょうクイズ 2年2組 しゃてき
3年1組 いんせきゲーム 3年2組 コリントゲーム
4年1組 ザ・ムービングターゲットショット 4年2組 ピックアップバイポイ
5年1組 もぐらたたき 5年2組 くぐるクイズ
6年1組 脱出ゲーム 6年2組 でぐちをさがせ 6年3組 くじびきやと VSたかはしぐみ
本日は多くの保護者、近隣保育園園児、幼稚園園児たちの来校を得て、大いに盛り上がりました。ありがとうございました。
9月25日(木曜) 3年 SC科「めざせ!こまキング!」
来週10月1日(水曜)の校内研究会に向けて標記授業が進められています。
・円盤の形は、円とする ・配られた割り箸を中心にさす ・割り箸はボンドでとめる
と条件制御をしてこまの試作に取り組みました。「ボンドでとめる前に試してみたい」との声もあがりましたが、試作品からいろいろと改良をしていくということで学習が進められました。
「よく回るようにするには・・・」「円盤は小さい方がよく回ると思う」「大きい円盤の方がバランスよく回ると思うけど・・・」
「ぼくは、遠心力を生かして回るようにしたい」 各自が工作用紙にコンパスを使って「私は4センチ」「・・・7センチ」「ぼくは18センチ!」 3年生は現在、算数の「円」の学習でコンパスの使い方を学んだばかりのため後でそれぞれ「(わたしは)半径2センチ」「・・・半径3.5センチ」「(ぼくは)直径18センチ!」と言い直しました。
また、円の中心を割り箸に固定する場所について「真ん中くらいがちょうどいいと思う」「下にした方が・・・」と思い思いに描いた円盤を割り箸に固定して、紙コップに立てかけて乾かした後に試しに回す児童たちもいました。
今後、児童たちは工夫を重ね、東京科学大学の協力も得ながら学習を深めていきます。
9月24日(水曜) 校内OJT研究授業 6年 図画工作科「ドリーム ドリンク」
本校では年間を通して、SC科にかかわる校内研究会(授業)と併せて標記研修会を行っていますが、今日は図工担当教員の授業を通して研修を深めました。
授業は、指導計画6時間のうちの1時間目で、本単元の内容を知り、各自で作りたい「新商品ドリンク」の構想を練り、「企画書」を基に話し合い発表をするというものでした。「企画書」にはイメージを描くとともに、考えたことを整理するために思考ツールの1つである「熊手チャート」を使い、ドリンクの効果、ターゲット対象、色・味、キャッチコピー、商品名を書き込みました。
ドリンクの効果としては・・・
・さわやかな気分になれる ・疲れが取れる ・イライラがなくなる ・楽観的になる
・元気になれる ・金持ちになれる ・瞬間移動できる 人の言葉が話せる(動物用)
・記憶力がよくなる ・・・
個人でワークシートを仕上げ、グループ交流後には数名の発表があり、最後に授業の振り返りをして次時からの造形学習につなげました。
授業を行うに当たって教員の授業観察の視点として「思考ツールの活用について」「対話について」「アイデアを考える際の教材の提示について」を挙げ、授業後はグループ協議、発表後に講師の区指導課指導主事から指導を受けました。
9月22日(月曜) 6年 特別の教科道徳「クジラとプラスチック」
自然を大切にするということを考え、それを実践していこうとする意欲を育てるという
目標の標記授業が行われました。
教材文には国際的環境団体がフィリピンの企業と共同制作した長さ15mのプラスチィッ
クごみでできたクジラのオブジェが波に打ち上げられている写真が掲載され、授業の冒頭
本文を読み終えると、「えっ、それからどうなったの・・・」という声が聞こえてきました。
そして制作者たちは私たちにどのようなメッセージを伝えたかったかを、児童たちは「今」
「未来」「一人一人に」「みんなに」という4つの視点から考えました。
・プラスチックによって苦しんでいる生物がいる
・プラスチックの使用を減らすことが大切。次世代の人たちが困らないように今、なん
とかする
・国や企業においてももっとプラスチック対策に関心をもち、なるべく環境に良いものを作
ったり、売ったりしてもらいたい
・定期的に「環境ウィーク」「環境月間」を開催する、また定期的に家族で話し合う
そして最後に、プラスチック問題に向き合うときにどんな心がけが大切かを考えました。
・少しずつ、一つずつ・・・まず自分ができることをさがす(最初は慣れるまで大変だけど)
・プラスチック問題とはどのような問題なのかを知り、日常と関連付けて考えていく
・私たち人間が勝手に作ってそのせいで他の生物に迷惑をかけている―人間が始めたの
だから終わらすのも人間―
・プラスチック問題を常に自分事としてとらえ、歯磨きをするのと同じように習慣的に考え
るようにし、また常に情報収集をする
自然愛護という観点から授業を深めましたが、本授業は、次回以降の命の尊さについての授
業につなげていきます。
9月22日(月曜)サイエンス朝会「ビタミンC」(還元反応)
ビタミンCには、皮膚や粘膜の健康維持を助け、体の調子を整える働きがあります。
薄茶色をしたうすいヨウ素溶液(うがい薬)にビタミンCを加えると、還元反応によりヨウ素が無色透明なヨウ化水素に変化します。
市販のビタミンCの入った粉末を水に溶かし、薄めたヨウ素溶液10mlにスポイトで加えると、わずか1滴で透明な液体に変化しました。ビタミンCが濃いことがわかります。
市販のジュースにもビタミンCが入っているものが多くあります。ビタミンCが多く含まれているのはどのジュースでしょうか。
ジュースA(きりっ・・・)は、スポイト11滴で、ヨウ素液の色が透明に変わりました。
ジュースB(リアル・・・)は、スポイト3滴で、透明になりました。ジュースAよりも多くビタミンCが含まれていることが分かります。
ジュースC(・・・1500レモン)は、なんとスポイト2滴で透明になりました。
ジュースD(ポカ・・ト)は、30滴たらしても色が変化しません。ビタミンCがほとんど入っていません。
4本のジュースの中で、一番ビタミンCが多く含まれているのは、ジュースC(・・・1500レモン)ということが分かりました。ラベルにもレモン70個分と書いてありました。
他にも、ビタミンCが含まれているジュースがたくさんあります。校長室前に置きますので試してみてください。
ビタミンCをとって、元気に過ごしましょう。
9月19日(金曜) 避難訓練 (Jアラート)
突発的な自然災害等が発生した場合の総務省消防庁からのJアラート放送へ対応するために、弾道ミサイル飛来を想定して建物の中にいる場合の退避の仕方を事前指導したうえで訓練を行いました。
・できるだけ窓から離れる
・カーテンを閉める(窓ガラスの散乱によりけがをしないため)
また、訓練後の講話では学校以外にいるときの退避行動について考えさせました。
・屋外にいる場合
・室内にいる場合(今回の教室等にいる場合に準じる)
・電車内にいる場合
・車内にいる場合
また、Jアラート放送は他にもチャイム音の「緊急地震速報」、サイレン音の「大津波警報」、同じくサイレン音の「津波警報」そして、警報音なしで音声メッセージでの「噴火警報」「噴火速報」「気象等の特別警報(大雨特別警報)」等があることを話しました。
6年生はSC科「自然災害から身を守る 清水窪子供プロジェクト」の学習で火山噴火、地震、津波、洪水の仕組み等についての学習し、その内容が廊下に掲示していることも伝えました。以下に児童たちが以下の学習に取組んだ理由の一部を紹介します。
洪水 ―近年洪水が増加し、大田区にも多摩川があるので、洪水が起こる前の対策が人命を落とすことの減ることにつながるから
津波 ―東日本大震災、能登半島地震等の被害の様子を知って衝撃を受けたから
火山噴火―日本の火山噴火は100年に1度くらいの頻度なので猶予があるうちに自分や周囲の人たちの命を救うことになるから
地震 -東日本大震災、能登半島地震等から学んで、地震が起きた時に落ち着いて行動できるから
9月18日(木曜) 5年 社会科「わたしたちの生活と食料生産」水産業のさかんな地域 ~魚食出前授業
愛媛県愛南町ぎょしょく教育協議会ぎょしょく伝道師(本校給食食材卸会社社員)による「出前授業」が行われました。愛南町は水産業が盛んで、特産品のひじき、真珠、ヒオウギ貝、カキ、カツオに扮したゆるキャラ紹介がありました。ゆるキャラには他に台風、赤潮、ごみと水産業を行う上で問題となっているものもありました。
まず日本の水産業について漁獲量が20年前と比べると50%近く減少し、漁師の高齢化が進み、近年60歳以上の方が55.3%、毎年約6000人が離職していると話があると「エー」「ヤバ」「ンー」等の声とともに驚きの表情が広がりました。また、水産業漁獲高(約9兆円)が農業生産額(約1.5兆円)の約6分の1、海での「獲る漁業」と「育てる漁業(栽培漁業)」の割合が57%と35%等のデータを含め、話や電子黒板の映像を見聞きしながら一層懸命にメモを取る児童が多くいました。
「獲る漁業」ではカツオを通して、その回遊ルートが黒潮をはじめ4ルートあること、黒潮の海洋における働きのこと、また産卵から成魚になるのは10万分の1の確率であることなど様々なことを教わりました。そしてカツオの魚体特徴について、また魚体の大きさに合わせて、何十本もの様々な釣り竿を用意していることを映像、画像で学んだ後に代表児童によるカツオの一本釣り体験が行われました。
「育てる漁業」ではマダイの養殖について、その施設、行程の説明の中でその工夫や苦労について動画や実物を使って説明がありました。そして生のマダイを観察したり、触ったりしながら、「天然もの」と「養殖もの」の違いについて考え、最後に日本の水産業が抱える課題について学びました。(以下、児童の学習ワークシートから抜粋)
「漁業はいろいろな意味で命がけなことにおどろいた。」
「自分たちで調べた一本釣りのことよりも専門家に聞いた方がわかりやすかった。」
「本物のタイを持ったらすごく重くておどろいた。
「水産業に関わる人は米農家と同じような悩みをもっているんだなと思った(高齢化、生産額)けど、協力して問題を解決しようとしているところがすごいなと思いました。」
「(仕分けのために)魚を持っただけで何キログラムかわかって、すごいなと思った。」
「愛南町で育てたタイと他の場所で育てたタイに違いがあるのかと思いました。」・・・
9月17日(水曜) 5,6年 体育・健康教育授業地区公開講座
大田区から委託された地域スポーツクラブ管理栄養士による標記公開講座が行われ、冒頭、本区は生活習慣病の罹患率が23区内中ワースト1ということから講話が始まりました。
6年保健科では、「生活習慣病の予防」で心臓病、脳卒中、高血圧症、虫歯と歯周病、がんについて教科書を中心に学習を行い、講演では日頃の生活習慣が多くの疾病につながっていくという観点から睡眠、運動、食事の大切さについて話が進められました。
・睡眠 小学生に必要とされる睡眠時間は、9時間~12時間
10時、11時台に就寝と挙手した児童は、3分の2程と一番多かったです
(睡眠不足による弊害の指摘 ・精神不安 ・身体成長抑制 ・風邪等の疾病・・・)
・運動 1日に1時間以上、週に3時間以上すると答えた児童がほとんどでした。
(また運動とともに、太陽の光を浴びることの大切さも)
・食事 好き嫌いをしない バランスよく、3食決まった時刻に食べる
(おやつ≠おかし 「ペットボトル症候群」から糖尿病の話へ)
教科書で、糖尿病については「主な生活習慣病」に列記されていますが、心臓病や脳卒中の原因になり、生活習慣の見直しをすることによって改善、予防可能、早期発見、早期治療の重要性を指導することになっています。
講演後には児童たちから以下の質問が出ました。
「『食事』のところに出てきた『BMI』の数値の出し方を教えてほしい。」
「化学調味料に含まれているアミノ酸は生活習慣病に関係してくるのか。」
「ぼくは、運動をよくするけれど食べ物の好き嫌いが多いことは、大丈夫か。」
「ビタミンをしっかり摂っていれば、いつまでも走ることができるのか。」
「しっかりと食事をとり、休養をとれば自分で健康年齢をのばせるのか」
また、感想として以下の発言もありました。
「私は睡眠時間を9時間とらなくてはいけないと思うので、9時には寝ないといけないことがわかりました。」
9月16日(火曜) 2年 生活科 「大きくそだて わたしの野さい」
冬にできる野さいから、その育て方や収穫後の野さいの調理の仕方までを考えたり調べたりする学習をしました。この学習は13時間扱いの2時間目の授業で、前回は冬野菜の種類や野菜の特徴(実は白色が多い、土の中で育つものが多い等)を見つけ、自分が育てたい野菜を決めました。
児童たちが育ててみたいと考えた野菜は、ニンジン(10名)、カブ(6名)、ネギ(3名)、そしてダイコン(2名)、そしてキャベツ、ブロッコリー、コマツナ、ホウレンソウ、シュンギクがそれぞれ1名でした。そしてそれぞれのグループに分かれ(ダイコン以下1名から2名は1つのグループに)タブレットPC、図書、プリント等を使い、「種をまく時期」「収穫時期」「育て方」「作ってみたい料理」についてこれからの計画を表にまとめました。
「ニンジングループが多いのは、(料理としての)使い方がいろいろあるからじゃないかな。」
「ニンジンのたねまき・・・この表の見方がわからないな。」「たねまきが4月、7月、9月・・・ということは・・・いけるね」「ニンジンは根が土から出ていると緑色になってまずくなるんだって。」「じゃあ、毎日よく見ていないとだめだね。」「1週間したら間引き・・・」
「ミニトマトでも芽欠きをしたよね。」
「キャベツはプランターで育てる・・・こんなに大きく育つかな。種より苗の方が育てやすいんだって」
「ネギはにおいが強いので虫が付きにくくて育てやすいんだって。」「でも普通のネギは育てるのが難しいって書いてあるので、ワケギにしよう。」
「シュンギクは気温が15℃から20℃くらいが育ちやすいんだって。でもこれから涼しくなってくると丁度いいね。」「でも種まきのために・・・3週間前にやること、1週間前にやることがあるんだ。」
各グループの発表内容を担任が一覧表にまとめると、ほとんどの野菜の種まきが9月ということに気づき、「急いで準備をしきゃ。」という声が多くあがりました。
9月12日(金曜) ふれあい給食会
36名の地域の方々をお招きし、全学級に分かれて本校自慢の給食を召し上がっていただきました。本日の献立はーキャロットライスのクリーム掛けとコロコロサラダーキャロットライスは鶏ガラスープから炊き込み、コロコロサラダは、ジャガイモ、キュウリ、ニンジンを賽の目に切り、トウモロコシの彩を添え、ドレッシングで和えた逸品でした。
まず、ご招待した方々を各学級代表の児童たちが図書室に迎えに行き、教室まで案内をしました。教室の黒板には歓迎のメッセージが描いてあったり、話をしやすい座席が工夫してあったり、電子黒板には、話を盛り上げる質問やクイズ、そして動画(学習の発表の様子等)が用意してあったりと各教室はいつもとは違った雰囲気でした。
各教室を回ると、昨日の激しい雷雨についての話が多く聞かれ、お子さんが小学生の頃の話、食べ物の好き嫌いの話、給食のお代わりの仕方等、多岐に渡っていました。そして坂門下までお見送りすると皆、笑顔で以下のようなことを話してくださいました。
「いろいろな話をして、子どもたちからパワーを貰いました。」
「みんな良い子たちで、いろいろとお世話してもらいました。」
「おいしい給食でした。私たちの頃とは、全然違いました。」
「牛乳パックやストローの片付け方を丁寧に教えてもらいました。」
「賑やかで元気いっぱい。大勢お代わりをするので驚きました。」
「質問に答えると、さらに質問をして、熱心に話を聞いてくれました。」
「去年1年生で今年は6年生たちと・・・6年間で随分と大人っぽく、しっかりとしてくるんだなと思いました。」
9月11日(木曜) 3年 音楽「リコーダーのひびきに親しもう」~リコーダー講習会
テレビやスーパー、コンビニエンスストア、ハンバーガーショップ等で馴染みのある曲がリコーダーで演奏されると、児童たちの表情が一斉に緩み、リラックスした雰囲気で授業が始まりました。今日は東京リコーダー協会から講師を招いて標記学習があり、テンポの良い指導で実に多くのことを学びました。
リコーダーの学習では「3つの準備運動」があるということで、少々難しい内容もありましたが、わかりやすい言葉で実技を通して楽しく学習をしました。
- タンギング
舌の動かし方に気を付けて、エアコンの空気の流れる音のように息を吹き込むー具体的には「カ行、タ行、ラ行」の言葉を言うように・・・「トットリ」「トラック」「トトロ」「タラコ」等の言葉で強弱を付けて、繰返し練習し、講師が「ダブルタンギング」を示すと「すごい」という声がたくさんあがりました。
- 息
「リコーダーは、鍵盤ハモニカよりも小さいので息があまり入れられない」という話を受けて、吹く時間の長さ表現のレベルを3段階に分け、恐さ、眠さ、美しさ、滑らかさ等の変化をつけて、適度に息を入れ続ける練習をしました。途中で息が切れて、顔が赤らんだり、喘いだりするする様子が見られました。
- 指
リコーダーでは、指を鍛えてほしいートーンホール(音穴)をしっかりと塞ぐことが大切だと教わり、指でオーケーマークや「キツネ」を作り親指と他の指を打って音を鳴らす練習をしました。そしてリコーダーは息を吹き込まなくても、「穴」を塞ぐだけで音が出ると「きらきら星」の演奏を聴くと拍手とともに驚きの声が沸きおこりました。
そして様々な曲を披露していただく前に、演奏時の姿勢を体操のようにして、また距離感も具体的な体の部位を使い分かりやすく教わりました。披露していただいた曲はアニメ主題歌が中心で、ソプラノリコーダーをはじめ、アルト、テナー、バスと続き、1m以上あるものや、6cm程のアクセサリーで曲が奏でられると、身を乗り出したり、体を揺らしたり、手や脚でリズムを取って踊るようにしたり、両手や両足で音を出したり、口ずさんだり・・・と皆、笑顔でリコーダー演奏の楽しさを満喫しているようでした
9月10日(水曜) 4年 体育「水泳」~プール納め
4年生は昨日の疲れも見せず、1時間目から水泳学習を行いました。厚い雲で覆われた空からは時折日が差す程度で昨日来の暑さはなく、児童たちの学習の合間を縫ってトンボがプールの水面に姿を現しました。
今日は今年度最後の水泳指導でプール納めの前には検定試験を行いました。
「ゴーグルを忘れちゃったけど、大丈夫かな。」
「10級から8級にー合格しました。」
「フー、ハー、やったー」
「途中で息ができなくなって・・・」
「・・・ウーン・・・」
見学者が級や段を表示したマジックテープの受け渡しに追われていました。
「8級がもうないよ。」「3級を8級に書き換えたら・・・」「でも、3級はテープの色が赤になるから・・・」「新しいテープで作ろうよ」「教員室に行ってくる」「あっ、7級に合格した人が8級のテープを返してきた」
見学児童の中には、テープの受け渡しだけでなく、新しいテープを頭(額部)に貼ってあげる姿も見られました。
以上で、今年度全学年の体育「水遊び」「水泳」の学習を無事に終えることができました。
9月 9日(火曜) 4年 SC科見学
1学期に理科「動物のからだのつくりと運動」で、骨や筋肉のはたらきに注目してそれらを関係付けて人や他の動物の体のつくりと運動とのかかわりを調べ、理解を深める中で観察などの技能を身に付ける学びを行いましたが、今日はそれらの観察する技能を高める学習のため、国立科学博物館、上野動物園の標記見学を行いました。。
まず国立科学博物館では1,2年生のSC科で学んだゾウやキリンの骨格標本を前に、特に足の骨の太さ、長さ、形、数、関節、爪に注目してスケッチをしながら気づいたことを記録しました。
展示会場に入ってくる児童たちからは驚きの声があがりました。
「うわーっ、すごい。全部スケッチしたい。」
「写真撮るぞー、でも暗いな。まあ、夜の野生動物ということで・・・」
「(剥製標本群を見て)これ、全部生きていたの・・・」
「もし、これらすべての動物に命を宿したら・・・」
(・・・以下、ゾウについてのみの児童たちの気づきの幾つかにご紹介します)
・ゾウの骨が思ったよりも細かった
・骨のつくりでは「爪先立ち」をしているようだった。足が冷えないようにしているのか・・あれであの体重を支えているのか・・・
・爪先立ちだけど、かかとをぺったりと地面に付けて歩いていた
・さすがに人間よりも太くて大きかった。だけど形は似ているものが多い
・前足よりも後足の方が長い
・人間と同じ関節があったけど、かなり太くなっていた
・長い鼻には骨がなかった
・ゾウがなかなか近くに来ないな・・・タブレットのズーム機能を使えばいいんだ
・大発見しましたーゾウは後ろに歩けるけど、横には歩けないようだ
最後に先日の上野動物園動物解説委員オンライン授業に続き、児童たちからの多くの質問に答えていただきました。ゾウやキリン以外の動物の観察からの質問も出され、「多くの質問から、いろいろな動物を細かく観察してくれたことが分かりました。」との言葉をいただきました。帰校式では、4年生の話の聞き方を褒めるとともに、生き物を愛護する態度も身についていくように願うと伝えました。
9月 8日(月曜) 夏休み自由研究展 始
標記の展示を、本日8日(月曜)から12日(金曜)までの15時15分から16時30分まで各階廊下にて行います。先週、展示作品に児童たちの夏休みの過ごし方や学習への取り組み方を思い描きながら見て回るとさすがに清水窪小学校、サイエンス関連の研究が目立つような気がしました。これらの作品については来月の学校だよりで一部紹介することをお約束し、以下にサイエンス関連以外の作品名を幾つかお知らせします。
図画工作科 「海の中に入った黒ねこ」「ヤモリの切り絵(切り絵の歴史)」「海のとけい」
「土偶づくり」「滝の鯉」「絵の説明・口座」(+スケッチ集)「貝がらシーサー」
家庭科 「手作りティッシュポーチ」「リメイクして作ったシャツ」「マヨネーズを作ってみよう」「お母さんの家事1日体験」
「働くお父さんの1日」「キクラゲの作り方」「スイカはどの味が合うか」「蕎麦、最高!」「カレーライスの歴史」
音楽科 「ギターを始めました」「作曲できるオルゴール」
保健体育科 「筋肉モリモリ計画」「プロ野球について」「ストレスの解消方法」
社会科 「日本歴史に刻まれた災害」「日本服装の歴史」「青森県いろいろな旅」「伊豆大島の海と椿」「日本・世界建築物」
「地球温暖化―大田区を涼しくするヒント」
言語 「アメリカとイギリスの英語」「方言について」「ウチナーグチって何?」
他にも昨年度の道徳授業地区公開講座を受けての登山体験を交えての研究「御巣鷹山と命について」、6年間の夏休み自由研究のまとめとしての「うずらの卵の変化について」等の力作をはじめ、多くの作品が保護者、地域の方々のご来校をお待ちしています。
9月 5日(金曜) 1年 SC科「しゃぼんだま けんきゅうじょ」
児童が1番作りたいシャボン玉を考えて計画書を書き、グループごとに学習してきたことをまとめ、今日はそれを他のグループの児童に実験を通して理解してもらう授業が行われました。
児童用机の2倍以上もある学習ボードにグループ皆の「計画書」を貼り、他のグループの人たちに説明をするときに「話し合いをしてからみんなに言うんだよ。」「1番目は・・・2番目は・・・」等と相談した後に、実験を行う廊下に大きな学習ボードを運び出しました。
廊下では各グループがお店やさんごっこのように「色が付きますよ。やってみてください。」「楽しいですよ。」「シールを貼ってください。」等の声があがり、実験を通してグループの説明が理解できたら「なるほどシール」がボードが貼られていきました。
・はちみつベタベタチームのは、ずっと浮かんでいた感じがした
・シャボン玉を触ったら、形が変わって小さくなった
・ゆっくり吹いてチョンチョン触ると丈夫になると思った
・丸いシャボン玉しかできなかったけど大きなのができた
・優しく吹くと大きいシャボン玉がたくさんできた
・水が多いと薄くなって出ないと思ったけど意外と出た
授業のまとめで、失敗してもそれも大発見なんだ!と児童からの声があがり、これからのSC科の勉強でもいろいろな発見をして行こう!とする姿勢が身に付き始めました。
9月 4日(木曜) 6年 図工「かがやけ!未来の私」
未来の自分を想像して、作りたい場面や動き・ポーズを考え、絵や言葉で表すという学習活動が始まりました。まず「私」の基本的な骨格を意識したスケッチの一斉指導を行いました。
腰→大腿部→下腿部→足→背→上腕部→前腕部…と描く中で、各関節の正しい動きも(4年SC科「骨から考える…」と併せて)考え、動きのある素描を仕上げた後、未来の自分を「将来の仕事」「趣味」「自分の時間」「その他」に分けて言葉で書き、先の素描を参考に作品作りに向けてのイメージを描きました。
「将来の仕事」 ・イラストレーター ・ジャズダンサー ・エンジニア ・工業デザイナー
・絵師 ・宇宙飛行士 ・プログラマー ・図書司書 ・各スポーツ選手・・・
「趣味」 ・野球 ・サッカー ・バスケットボール ・バレーボール ・お絵描き
・お茶のみ ・睡眠 ・読書 ・キャラクター収集 ・・・
「自分の時間」・食事 ・犬と遊ぶ ・読書 ・旅行 ・ゲーム ・工作 ・自然観察
・会話 ・お絵描き ・小さい子に趣味のことを教える ・・・
そして以上の中から、将来の自分の姿を中心としたひと場面を選び、構想が固まった児童から紙粘土工作が始まりました。
9月 3日(水曜) 2年 道徳「黒ばんがにっこりするかな」
昨日、学級係活動担当者を決めたことをもとに、「仕事をするとどのような気持ちになるか皆で考える」というめあての学習が行われました。当番の仕事は大変なことばかりではなく楽しいこともあり、「黒板がにっこり」しているかは仕事をしている人しかわからないのではないかという意見も出ました。また、資料中の「先生に褒められたときの気持ち」及び「これからどんな気持ちで仕事(係、当番活動等)をしていきたいか」について考えましたが、発表のあとには、周囲児童たちから自然と拍手が沸き起こりました。
教室内に掲示している「二学期のめあて」を目をやると以下の文章が見られました。
・係、当番活動を頑張りたい
・チームワークよく皆を楽しませたい
・友達を助けたい
・後のことまで考えて当番の仕事をしたい
・皆が楽になれるように頑張りたい
・係活動で、皆の意見をいっぱい聞いて行きたい
3つの学級目標のうちの1つ「協力して仲良く笑顔」に結びつく考えがたくさん出てきました。(2年では担任による道徳交換授業を行っています。)
9月 2日(火曜) 4,5年 国語「詩を味わおう」
2学年が同じ単元名の詩の学習が始まりました。
4年生は「ぼくは川」(坂田寛夫)「忘れもの」(高田敏子)のうち1編の詩を選び、グループごとに音読発表会を行っていました。今日、学習したばかりの詩をほとんど暗唱しているのには驚きました。その後、誌を画用紙に視写(手本となる文章などを見てその通りに書き写すこと)し、文章構成や文章表現技法の理解、語彙力、集中力の向上を図り、学習を深めていきます。また5年生は「かぼちゃのつるが」(原田直友)、「われは草なり」(高見順)の2編を読み、それぞれの詩の特徴をまとめるとともに、くり返しの表現方法がある等、共通する点にも目を向けていました。
「くり返しの言葉から、たくさん成長してもらいたいという願いを感じる。」
「人も植物も同じ一日を大切に生きる命があるということが感じられる。」
「命や成長は見えないけれど、それらは確かにあるものなので、見えないからこそ大切にしてほしいという願いが感じられる。」
等の発言、発表等があり、児童たちの感性が作者の感性と響き合い始めました。
9月 1日(月曜) 始業式 ~
久しぶりに全校児童が一堂に会した体育館は、当初賑やかで明るい雰囲気でしたが、式が始まると皆の気持ちが引締まりました。校長講話後、5年代表児童の言葉で1学期を振返っての2学期の目標、及び自身で成長したいことについての発表がありました。そして式後に転入生6名の紹介に移ると体育館はまた賑やかで明るい雰囲気となりました。最後に看護当番から今週の目標(『自分から笑顔で挨拶をしよう』)についての話がありましたが、会場から教室に向かう児童たちを出入口付近で送り出していると多くの児童たちが、「おはようございます。」「こんにちは。」と挨拶をしたりお辞儀をしてくれたりしました。
1校時の各学級の様子を見て回ると、今日1日の予定を担任と確認したり、転入生への自己紹介を兼ねて一人一人がスピーチをしたり、グループごとに夏季休業中の話や自由研究について発表しあったりする姿が見られました。また授業中や休み時間(本日は内遊び)に教室の中に入っていくと、会釈をしたり、笑顔で応えたりする児童たちもいました。
3校時、1年生は初めて使用する理科室で、来週のSC科研究授業に向けて早速「しゃぼんだまけんきゅう」の個別学習課題を立てていました。