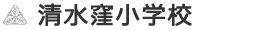令和6年度 2学期
更新日:2024年12月25日
12月25日(水) 終業式
今回も児童たちは私語もせず、整然と並ぶ体育館で終業式が行われました。校長講話では「今年の漢字」として「行」(様々な学校行事への取組み)「科」(研究発表会に向けての科学の学習等)「仲」(学級、学年での児童間の仲の良さ、たてわり活動等)と3つの漢字を通して今学期を振返りました。また冬休みの過ごし方として式後に生活指導主任から安全、健康について4つのことを指導しましたが、校長からも「学校生活をよりよくするために」ということで本日配布したプリントについての説明、指導がありました。
また2年生からの児童代表のことばでは2学期に頑張ったことから3学期の学校内外での活躍についての抱負をしっかりと発表しました。
12月24日(火) 4年 学年集会 書き初め練習(毛筆)他
4年生は毎月学年集会を実施し、今日は全員でゲームをして楽しもうと担当係児童が朝早くから準備を行っていました。ゲームの名前は「おでんづくりゲーム」―「これ私が描いたんですよ!」「急いで準備しなくっちゃ!」―まだ昨夜からの冷気で暖まっていない体育館でしたが他の児童たちが校舎に入ってくる前から活気にあふれていました。
その後の授業では教室の床に新聞紙や習字道具を広げて「美しい空」という作品に取組んでいました。また他の教室を覘くと、SC科の学習のまとめをしたり、大掃除をしたり、3学期の展覧会会場に飾る作品作りをしたりと、学期末の残りの時間で計画的に学習をしていました。
12月23日(月) 1年 書き初め練習(硬筆)、SCかるた
書き初めの練習では先週、字の形に気を付けて書き、今日は字の大きさに注目して書きました。児童たちは前回書いた作品と見比べながら集中して1字1字丁寧に書いていました。隣の学級ではかるた遊びのやり方を教わり、本校で作製したSCかるたで楽しみながら学習を進めていました。
12月23日(月曜) サイエンス朝会「音の不思議」(音の性質)
カリンバという楽器には、いくつもの細長い金属がついています。その金属をはじくときれいな音がします。長い金属をはじくと低い音が、短い金属をはじくと高い音が出ます。
いくつかの長さの異なるラップの芯を用意しました。芯は筒になっていて、片方を手の平でたたくと音がします。長い筒は低い音が、短い筒は高い音がします。
ストローで笛を作りました。ストローの先をつぶし、その両側を少しだけ切り取ります。すると、ストローの先が木管楽器のリードのようになり、吹くと音が出ます。ストローの長さを短くしていくと、より高い音が出ます。
リコーダーも長さによって音の高さが変わります。一番短いソプラニーノリコーダー、小学生が使っているソプラノリコーダー、中学校で習うアルトリコーダーと、楽器の長さが長いほど低い音が出ます。
12月20日(金曜) こどもまつり
遊びを創造することを通して協力する態度を養い、異学年交流を深めることをねらいとして、今日まで計画委員会を中心として各学級で計画、諸準備を行ってきました。
児童たちは、中休み、昼休みの時間も使って打ち合わせをしたり、様々な物を作ったりしてきました。また登下校時には多くの児童たちが教員室外脇の防球フェンスに掲示された各学級のポスターに見入っていました。
1年1組 いろいろつり 1年2組 ボーリング 2年1組 にんげんまちがいさがし
3年1組 ボールおとし 3年2組 はこのなかみ 4年1組 はんにんをさがせ 4年2組 ジャングルからだっしゅつゲーム
5年1組 しゃてき 5年2組 わなげ 5年3組 もぐらたたき
6年1組 アスレチック エッシーに届けクリスマスプレゼント 6年2組 たいいくかんへGO おおだまボーリング
各教室、体育館は明るく熱気を感じさせる雰囲気でしたが、廊下でも時間を気にして小走りになったり、次に行こうとしている所の情報をしおりで確かめ合ったり、呼び込みのプラカードなどを掲げて(中にはタブレットで画像を見せながら)行き来する児童や来校者の方に声をかけたりと活気に満ちていました。中には一緒に廻っていた友達とはぐれて上級生が話を聞いている場面が数回ありましたが解決するまで対応していました。
12月19日(木曜) 2年 SC科 学習発表会
2年生が「きりんはかせになろう」の学習のまとめとして10グループに分かれ、それぞれが「舌」「首」「体の模様」「ひずめの形」「目」等のテーマで3年生に発表をしました。
発表が終わると、3年生からは「まだ見たかったー」という声が聞こえてきました。また振り返り活動では「去年勉強したけど、知らないことも調べていた」「模型がすごかった」「クイズが多くて楽しかった」「大きい声ではっきりと発表していた」との感想が、2年生からは「アドバイスをたくさんもらった」「熱心に聞いてくれたので話しやすかった」との発言がありました。
そして最後に2年担任から3年児童たちに対して「2年生は『きりんはかせ』になれましたか?」と問われると、皆拍手を返していました。
12月18日(水曜) 4年 SC科「飛べ!水ロケット!」 国際交流
7月18日(木曜)に5年生が東工大研究室訪問でお世話になった藤島晧介先生をゲストティーチャーとしてお迎えしての標記授業が行われました。前半は4年生学級対抗の水ロケット対決―今までの学習から各学級で1番飛距離の出た結果をもとに、
・粘土の重さ ・羽の位置 ・先端の形状 ・ペットボトルに入れる水の量 ・発射角度
についての発表がありました。快晴で風もほとんどなく、湿度も低いという好条件の下、どのロケットも50~60m程と各学級とも「新記録」を達成しました。ここ数年、本授業に関わっていただいている藤島先生からも今までにない好記録だとほめていただき、児童たちは大喜びでした。
後半は教室に戻り、藤島先生から「ロケットと宇宙と生命」という演題で、まずは目を宇宙に向け、「木星のガリレオ衛星の4つの星―」というと「イオ」「ガニメデ」とすぐに回答があり、火星のサンプルの一部が日本にあるという話になると児童たちの目は一層輝きました。
そしてロケットは大きいもので300フィート、小さいものでは鉛筆大と様々で、形状からスペースシャトル計画を取りやめた理由や、新たなアルテミス計画についてと話が広がりました。途中、藤島先生から「ロケット(本物)を飛ばしたら何をしたい?」という質問に「月を近くで観てみたい」「宇宙ステーションで・・・寝る」「火星に行って生命体がいるか確かめる」「ブラックホールを観たい」という返答がありました。
藤島先生の研究室、宇宙生命研究所(ELSI)は30%が外国の方で、研究室内はすべて英会話とのことー偶然にも今日は東京科学大学留学生との交流会もありました。
12月17日(火曜) 5年 社会科見学「羽田税関・味の素川崎工場」
5年生は、社会科で。暮らしを支える工業生産やそれを支える運輸や貿易について学んでいます。今日は、東京税関羽田税関支署と味の素川崎工場に行き、実際の工業生産や運輸に関わる税関について学んできました。
東京税関では、税関の仕事についての話を聞き、羽田空港内にある施設を見学しました。麻薬探知犬のラブラドールレトリバーが実際に働いている場面も見ることができました。
味の素川崎工場では、スープ工場や包装工場を見学し、品質管理における工場の工夫や努力について学びました。
5年生の児童はとても熱心に見学し、メモ用紙いっぱいになるまで記録していました。見学態度もよく、最高学年に向けた気持ちの高まりも感じました。








12月17日(火曜) 1年 こどもまつりじゅんび
めあて「みんなを楽しませて なかよく ハッピーにする」を確認後、3日後に迫ったこどもまつりに向けて今日は何をしたらいいかを聞くと、
1 リハーサル 2 お店の場所決め 3 受付について
が出されましたが「リハーサルはまだ早いかな・・・」「受付について考えるのが一番じゃない?」「二番目は・・・」と自然と話し合いが盛り上がっていきました。また担任は先月の「あきまつり」を想起させ、今回は1年生だけではなく全校児童対象で規模が違うことを伝えて考えを深めさせていました。受付を教室入口1か所にするかグループごと4か所にするかーでは「1か所だと、お店に集中できる」「受付が多いと混乱して喧嘩が起こるかもしれない」「1か所だと入口が混む」等様々な意見が出ましたが、皆で確認して多数決をすると各グループで受付をつくるということで準備を進めることになりました・・・・・人気のあるお店にするにはーでは、「きれいな字で看板をかく」「客寄せをがんばる」「目立つ服を着る」「(お店の人だけ)バッチを作る」そしてチラシを作るという意見も出ましたが、ポスターも描いて貼り出すので行わないことになりました。
そして後半は「動物・虫」「たべもの」「海のいきもの」「しみずくぼ」の4つのグループに分かれて「いろいろつり」のお店準備を進めていました。
12月16日(月曜) 2年 図工「つないでつるして」
標記の造形遊び活動を行いました。材料はリサイクル紙(プリントしたものの裏紙)を短冊にしたものをセロファンテープで思い思いに繋いでいきました。来年1月の展覧会に出す作品が完成していない児童は遅れて各グループ活動に参加し、授業が終わるころは思うように行き来できない程の作品が広がりました。
「どこまで続くのかわからない!」「ここに頭を出したらアウト!」「私たちは猫の顔を作ったんだ!」
初めはグループごとの机で作られていた作品が隣の机や流し、乾燥棚等に繋がれてグループごとの作品が「合体」されるところもありました。そして繋がれた作品を跨ごうとして短冊が切れても誰一人嫌な顔をせずその修繕を行い、それまでは作品の下を潜ったり腹ばいになったりして通っていたところを「潜れないようにしよう!」と“壁面”を作り出すグループも現れました。そして途中から天井にロープを吊るして繋げるところが増えるとさらに児童たちの目が輝き、より意欲的に活動に取り組んでいました。
「テーブルの周りジグザグの模様にしました!」
「坂を作って・・・こういうふうに行くんだ!」
「電車を作って(細長い短冊を巻くように円筒形等にして)通れるようにしたんだ!」
「ここは重なっちゃうから橋みたいに浮かせたました!」
最後に工夫したところを発表し合うと、せっかくの作品でしたが教室は元の通りに片づけられました。
12月16日(月曜)全校朝会「小学生駅伝大会 表彰」
12月14日土曜日に、大田スタジアムで、小学生駅伝大会が行われました。清水窪小学校は第2部に5・6年生の代表選手が出場しました。
12月から始まった毎日の朝練習の成果を発揮し、清水窪小学校の代表として活躍すべく、すべての選手が全力を尽くしました。素晴らしい選手の走りぶりに大きな声援が送られました。
結果は33分12秒。昨年の記録を大幅に更新し、8位以内に入賞しました。
これは、11月から持久走月間として、朝や体育の時間に走り込み、体を鍛えた、清水窪小学校の全員のこどもたちの成果だと感じています。
選手の皆さん、お疲れさまでした。そして、応援に来てくださった保護者や児童の皆さん、ありがとうございました。
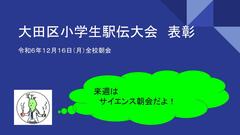



12月13日(金曜) 生命尊重週間 ―人権について考える―
人権問題を正しく理解するために必要なものの見方や考え方、人権を尊重する豊かな心を育成することをねらい、本校では下記の取り組みを行いました。
・低学年「こどもの人権 みんなえがおでいるために」
・中学年「こどもの人権 九匹九色~ちがうっていいこと?わるいこと?」
・高学年「こどもに関する条約等から考える『こどもの人権』について」
「性的マイノリティの人権『らしさ』って何だろう?」
6年生では、「こどもの権利条約」について理解を深め、学んだことからよりよい学級にするために自身でできることについて考えました。
【第2条】差別に禁止 【第3条】こどもの最善の利益 【第6条】生きること・育つこと、命を大切にされること 【第12条】こどもの意見の尊重
・性別、考え方で差別をしないようにしたり、人の考えをちゃんと受け入れるようにしたりする
・友達の意見を否定、無視せずまたつぶさず、よく聞き、自分もよく意見を言う
・人にやさしく接し、自分や相手のこどもの権利を尊重する
・いじめや差別されている人がいたら助け、みんなに平等に接する
・いやなことはいやと言い、止めてくれなかったら大人に相談する
・みんなとかかわりをもつ
・こどもの権利のことをしっかりと知って、知らない人がいたら教えてあげたり、平等に接したりする
・何も考えずに言葉を出さず、相手がいやな思いをしないか考える
並行して大田区小・中学校人権啓発作品展が行われ、本校からは6人の作品(ポスター、標語、習字)を出展し、現在その作品を改めて校内に展示しています
12月12日(木曜) たてわり班遊び(2)
12月10日(火曜)の「たてわり班遊び(1)」同様、青空の下,遠く富士山を望む屋上では「タグ取りゲーム」が行われ、ほぼ休みなく走り回る児童たちからは寒気を吹き飛ばすような歓声と笑顔が溢れていました。体育館では「ドロケイ」―帽子を被った仲間を助けようと“牢屋”のマット置き場に“ドロボウ”が果敢に走り込んでいました。ドッチボールではチームの力の差がありそうだという声があがると「1回やってみようか。」という6年生の声でゲームが始まり、「(コートの)線はこの色だよ。」と言ってしゃがみ、指でさして教える姿も見られました。
その他「フリスビードッジ」「増え鬼」「タグ取りゲーム」「だるまさんの1日」と朝の10分余りの時間、異学年交流での遊びを楽しみました。
12月11日(水曜) 3年 理科「音のせいしつ」
問題 「音が出るときに、物はどのようになっているだろうか」
予想 「音が出るとき、物はふるえているだろう」
実験方法 ・糸をはじいて音を出す ・声を出してのどをさわる
考察 「予想通り、自分の予想は正しいといえる。つまり音が出ているときには物はふるえている」
結論 「音が出ているときには物はふるえている」
今日は上記の2つの実験を行いましたが、その実験を通して気づいたことを発表し、次時の実験に結びつけていました。
・実験中に音程が変わることがあった
・ひもを引っ張っていないと音が鳴らなかった
・小さい声や音を出したときはふるえていなかったように思う
―次時の実験―
「音の大きさが変わるとき、ふるえ方はどのように変わるだろうか」
12月10日(火曜) 5年 東京科学大学訪問 「ロボットをうごかすメカ」―歩行ロボットの脚のメカを作ろう―
今年も講師は工学院機械系教授岩附信行先生で、自身が芸術家であることの自己紹介から、作品制作の苦労、工夫の話から標記本時の学習内容についての工夫に繋げました。今回は紙工作だけれども3次元としての金属での製作となると様々な工夫が求められることの説明に続いてロボットを動かす部分のモーターの数が3か所(腰、膝、足首)となることを計算式で表すなど、論理的な思考を深めました。(詳しい内容については大学で学ぶレベル)そしてその論理を図で解説する中で小学校算数「平行四辺形」の性質が用いられ、モーターの回転に連動したロボットの脚の動きをPCムービー画でスクリーンに映されると教室内に「オ―」という歓声があがりました。工作用紙を切って関節部分をハトメでとめる時に「てこの原理」を使わないと上手く繋げないことも学習しました。終末、回転運動が脚の歩行運動に変わる様子を不思議そうに楽しそうに見ている児童の中に、そのハトメの穴に鉛筆の芯を入れて、その軌跡を確認している姿も見られました。今回の学習では研究生の学生2名も支援して下さり、時間内に何とか「形」にすることができました。
12月 9日(月曜) 4年 外国語 「What do you want?」
初めのウォーミングアップは全体で、また個人で繰り返し挨拶を交わした後に、今日の天気、日時を確認して授業が始まりました。今日はALT外国人講師の入らない授業でしたが、動画やチャンツ、ゲーム等を挿入しながら活気のある学習展開となりました。まず、八百屋での買い物を想定して「What do you want?」「I want ー please .」「How many?」「ー please .」「Here you are.」のフレーズの練習をしました。動画視聴では音楽のリズムに乗って思わず足で、手でリズムをとりながら学習する児童が多く見ら教室が賑やかな雰囲気となりました。しかし、「買い物」の場面の学習ということで各国(韓国、ミャンマー、タイ、イタリア、ペルー、ケニヤ)の市場の様子を映し出すと、児童たちの真剣な視線が電子黒板に集まりました。学習動画では野菜や果物の種類や形、色の表現も付けて徐々に発展させていきました。そして、ゲームを楽しみ本時の学習の振り返り(学習目標に対する自己評価、感想)を書いて終わりました。
12月6日(金曜) 持久走大会
朝の時間を使った持久走月間、体育の授業で行った5分間持久走等で練習を重ねてきた成果を発表する標記大会が行われました。今までの練習では「走ると、目が乾燥してくる」「私は8周した」「ぼくは8周と4分の3くらい・・・」「最後にラストスパートしたんだ」「ぼくは…(小声で首を横に振って)」中には、走りながら・・・「だめだ。何周走ったか覚えてないー」という児童が多くいました。昨日、一昨日には周回数を教える「ペア」の児童をつくりました。6年生は1年生とペアを組みますが、打ち合わせ後にはお互いに手を振って会場を後にする姿がありました。
第1部では2年生、3年生が走り、5年生が記録を取り、最後に5年生が走りました。(5年生の記録は学年内で)そして第2部では1年生、4年生が走り、6年生が記録を取り、最後に6年生が走りました。(6年生の記録は学年内で)
最後に1~4年児童のタイムトライアルが終わり、教室に戻るときに校庭を挟んで5,6年児童の「お疲れー」の声に「ありがとうございました。」と応えていました。
12月5日(木曜) 2年 国語「お話の作者になろう」
教科書の挿絵に沿い、まとまりに分けてノートにお話を作りました。次時にはカードに清書をすると伝えると「もう、清書ができるような気がする。」という児童や、書き上げた作品を見直してストーリーを変える児童もいました。学習の目当てや学習内容の確認後、教室内は近隣の児童が書いた内容を見せ合ったり、感想を言い合ったりして少々賑やかな雰囲気の中、腕組みをして身動ぎもせずにノートを見つめる児童、「悩むー」と声をあげ、天井を仰ぐ児童、黙々と鉛筆を走らせる児童がいました。しかし「どんぐりを見つけた時の様子や、二人で帰るときの様子も詳しく書いて」と言われると教室はしんと静まり、児童たちは自身の活動に集中していました。
「振り返り」では「文の書き方が分かってきたので、今度は隣の人に読んであげたりしたい。」「友達と話せなかったけど、学習の順番でお話ができた。今度は友達と話したり、先生に聞かせたりしたいです。」等の発表がありました。
12月4日(水曜) 4年 福祉体験学習
視覚障がい者や聴覚障がい者、足が不自由な方との交流、体験学習が体育館、昇降口、廊下等で行われました。まずそれぞれの方々から講話をいただきました。
視覚に障がいのある方は、主に音や声によってまず方角を確認するということで児童たちが目を瞑った状態で音の出た方向を指さすとういう聴覚だけで判断するという体験をしました。音や声のほかに点字、点字ブロックの便利さとともに街中では自転車走行、歩きスマホ、放置自転車等に対する困り感を訴えていました。聴覚に障がいのある方は目で見て確かめることが大切で「筆談」「空書」「口話」「身振り」「指文字」「手話」の中から手話で「わかりました」「ありがとう」「どうぞ」という表現の仕方を教えていただきました。そして街中では緊急車両のサイレン、クラクション等の音が聞こえないために不安感をもったというお話を聞きました。そして話が終わり皆から拍手が送られましたが、後に視覚による手を振っての挨拶に代えました。
そしてすべての方が、街中で障害のある方に“気づいたら” 「何かお困りですか?」「大丈夫ですか?」「何かお手伝いできることはありませんか?」等
まず声をかけてほしいと訴えていました。困っているときに声をかけられると助かるし、「やったー!」という気持ちになり、「そういう助け合う世の中が広がっていったらいいな。」という言葉が児童たちに向けられました。
後半はアイマスク・白杖体験、手話体験、車いす体験をグループごとに行いました。体験学習は選んだ1つのみとなりましたが、事後、教室で学習の報告会が行われます。
12月3日(火曜) 6年 狂言教室「柿山伏」
今朝から5,6年代表児童の駅伝大会に向けての練習が始まりました。それを見ていた6年生との話の中で、今日の狂言については学級で動画視聴をしたので「知っている」とのこと、また「歴史に興味があるから楽しみ」という声も聞かれました。
狂言教室は体育館で行われましたが、児童たちと同じフロアでしかも間近かで鑑賞することができたため、初発の言葉を聞くと児童たちがその迫力に頭が後方に引かれ姿勢が正されるのがわかりました。そして650~700年もの間に途切れることなく伝わり、当時の言葉が今でも理解できるということ、当時使われていた古い面を今も使うことを大切にしているということ、そして喜怒哀楽を表現するワークショップからは「笑い」が世の平和や人々の幸せな生活に結び付くことなど様々なことを学びました。
最後に児童たちからの多くの質問に答えていただきました。
・「衣装を着るとどのくらい重いのか」
-衣装は7~8キログラム。それに綿入れを着るのでものすごく暑い
・「自分で可笑しくなってしまうときはないのか」
―真剣にやっているので・・・昔は位の高い人の前で演じたのでセリフ一字一句間違えられなかった
・「狂言は2人でやるものなのか」
-「1人の演目から、40から50人というものもある」
・「狂言をやっていて嬉しいことは」
-人と人が“繋がる”瞬間 舞台と客席 国や地域を超えての繋がり 昔の人たちとの繋がり
授業が終わって片づけをしていると、いつの間にかその作業に加わっているこどもたち、演者の方のそばに行き、改めてお礼の言葉を言うこどもたちの姿がありました。
12月2日(月曜) 1年 ひきざん「かあどをつかって」
ひき算の計算能力を伸ばすために「たしざん」でも使用した計算カードを使った学習をしました。前時のひき算の計算の仕方を定着させるための段階を踏んだ学習の上に今日はその習熟を行うグループ、同じ答えのカードを集め、並べることによって関数的な見方の素地を育てるグループ等、1年生2学級を3グループ3名の教員で指導を行いました。
同じ答えのカードを集め、並べることによって気づいたことー
・たて 前の数が1増えると後ろの数も1増える。答えは同じ。
・よこ 前の数は同じで、後ろの数が1増えて、答えが1減る。
・ななめ 前の数が1減って、後ろの数は同じで、答えは1減る。
―以上のことを児童たちは自分たちの言葉で一生懸命に説明をしていました。
そして以下のことに気づき、感じ、理解させようと粘り強い指導が行われていました。
・たし算でも学習したように、カードを順番に並べることのよさ
・並べたカード縦や横にみるときまりが見つけられることの驚き
・さらに計算をしていくことの楽しさ
12月2日(月曜)全校朝会「人権週間」
12月4日から12月10日は、「人権週間」です。1948年12月10日に国連総会で「世界人権宣言」が採択され、その前の1週間を人権週間としています。
「人権」とは、一人ひとりが生まれた時からもっている「自分らしく生きる」権利のことです。『だれもが幸せに生きる権利』があり、自分にも みんなにも 人権があります。
みんなそれぞれ違ってい、全部が同じ人は、一人もいません。一人ひとりの違いを認めたり、自分やお友達のよいところを見つけて、それぞれが大切な人であることを知る、一週間にしましょう。
・じぶんのよいところを見つけ、のばそう。
・友達のよいところをみとめ、はげまそう。
・ほかの人がいやがることは、ぜったいにやめよう。
そして、清水窪小学校では、12月4日から12月10日を「生命尊重週間」としています。人権を守ることは、命を守ることと同じです。自分を大切に、友達を大切に、そして、動植物も大切にしましょう。
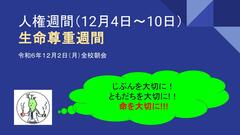
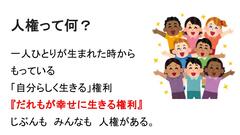
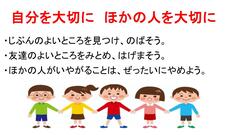
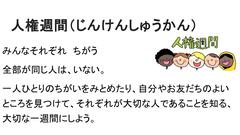
11月29日(金曜)6年 総合「旅立ちプロジェクト」
「個性と協力を忘れずに メリハリをつけて 最後の1年間を 笑顔で過ごそう」
「夢に向かって 動き出す あきらめずに いどみ続ける」
以上は6年生各学級に掲示している学級目標です。
その6年生が標記の学習に取り組み始めました。学習の進め方としてはー
- なりたい職業 興味ある職業
- (1)を選んだ理由 きっかけ
- 内容 メリット やりがい デメリット 大変さ
- なるための道のり(資格 能力 適正)
- 「働くとは」(自分の考え インタビュー 等)
児童たちは独りで黙々とタブレットPCにまとめたり、調べたことやそれに対する考え等をお互い話したり、本やインターネット等を何回も見たりしていました。
美容師 アナウンサー 将棋棋士 野球に関する仕事 自動車整備士 飲食関係 医師 薬剤師 電車運転士 保育士 国会議員・・・様々な職業名が上がっていましたが、児童間からは次のような声が聞こえてきました・・・
「◇◇になるのって難しんだよね」「家族が大きな病気をしたときに助けてくれたんだ。だから・・・」「習い事で続けてきたから」「ちょっと『ブラック』みたいだけど・・・」「そういえば学校にもこの(職業の)人たち来てるね」「月給が〇〇円だと・・・ちょっときついかな」「グラフィックデザイナー、ユーチューバー、声優・・・決まらないけど共通することを考えて進めて・・・」
1月には大森第六中学校の生徒が1学期の職場体験学習で学んだことを6年生に伝える学習があります。今回学んでいることと結び付けていくことと思います。またPTA広報誌に今年度も各人の「将来の夢」について掲載する予定と聞いています。
(その6年生は家庭科で各人思い思いの副菜おかず作りに取組みました。炒め物が多かったですが、中にはひじきを水で戻したり、泥付きのごぼうやカボチャ、ニンジン等の堅い野菜を使ったりする児童もいました)
11月28日(木曜) 2年 生活科見学 ー洗足池公園―
雲一つない青空の下、洗足池公園に生息する動植物の観察のほかに公園を利用する“人”にも着目して生活科の学習をしました。眩しい程の日差しを受けて公園に向かう途中、暑さで上着を脱ぐ児童もいましたが、園内の木陰は空気が冷たく、はじめは「気持ちいい!」と言っている児童がいましたが暫くすると「じっとしていると寒い!」と上着のチャックを上げる児童が目立ちました。
まずクラスごとに後の活動のためにトイレの場所、活動区域また集団行動での約束について確認しながら園内を散策しました。列になって歩いていると紅葉した枝葉に飛びつこうとする児童もいましたが、活動中に収集してよいものは「落ちているもの」のみとの約束が伝えられました。池の葦の間に泳ぐ色とりどりの鯉を指したり、池に隣接する水生植物園ではスイレンの蕾を見つけて「あっ、あれ咲きそうだよ!」と思わず声をあげたりする児童もいました。また殆どの水鳥が杭に乗って休んでいる様子を見て「鳥が自分のおなかを食べているように見える」また「あの鳥は動いているよ」等の声が聞こえてきました。
次の活動は、グループごとに分かれて事前に提示された8つの“ミッション”に取り組むものでした。最後のチェックポイントの集合場所で行き来する児童たちの様子を見ていると「大変!あと10分しかない!」「急いで!」と小走りで観察場所を探す姿が見られました。
・虫 イモムシ アブ シジミチョウ トンボ (セミ幼虫の穴) ・・・
・魚(鯉)の色 黒 白 黒白 オレンジ 黒オレンジ 金 クリーム ・・・
・鳥 「名前はわからなかったけどたくさんいた。」「渡り鳥がすぐ近くを飛んで行ったんだ。」
・植物、実、種 「こんなモミジの葉っぱを見つけたよ。」「私のはまだ(葉が)ピンとしている」
「タケノコみたいな小さい松ぼっくりを見つけた!」「ふつうはここが開いているのにな。」
「ふさふさがこんなに小さい猫じゃらしを見つけた。」「(葉が)まだ緑色なのに・・・落ちてたの。」「裏が白い葉を見つけたよ。でもこうして日に透かして見ると黄色になるんだ。」
「この草は何かな?」「すすき?」「ラベンダー?」「木の実は何の実?」「調べてみよう!
その他、出会った人たちは数多・・・中でも時間を追うごとに増えてきた園児たちには「ハイタッチしたんだ。」「手を振ってくれたよ。」と様々なことを報告してくれました。
11月27日(水曜) 1年 「あきまつりをひらこう」
1学年で標記活動を行いました。まず全員が1組教室に入るとオープニングで音楽隊の演奏が賑やかに行われました。楽器は生活科見学で行った多摩川台公園の木の実や枝等で作ったマラカスが中心でマスターによる一人一人の紹介がありました。すると「(マスターの)自分の紹介を忘れているよ。」と声が上がり教室内の雰囲気が和らぎました。演奏が終わり「どうでしたか。感想などをどうぞ。」と発言を促されると「一つ一つ音が違ってきれい」「おまつりみたいだった」―そして「題は何というのですか」という問いには「とけいです。」との回答でした。暫くすると教職員のほかに2年生も来て一層活気のある「あきまつり」となりました。まつりのお店としては・・・
・クレーンゲーム ・どんぐり虫とり ・けん玉 ・やじろべえ ・かざりアクセサリー
・どんぐりおみくじ ・しゃてき ・どんぐりこま大会 ・どんぐりさがし ・わなげ
・どんぐりとばし ・チャレンジ ・クイズ ・どんぐりすくい
と多岐にわたり「パスポート」カードに参加ゴム印を押してもらってお店をめぐっていました。中に1か所だけ印を押してないカードをもって座っている子がいたので理由を聞くと「自分のお店だから」との返事。それを聞いていた子が「やってもいいよ」と準備を始めていました。2年生の中からは「去年より楽しいかも・・・」という声も聞かれました.1年生からは「もっとやりたかった。」「またやりたい」との声が上がりましたが、来月には全校で「こどもまつり」が計画されており、今回以上に張り切って準備をしていくことと思います。
11月26日(火曜) 落ち葉掃き週間 始
たてわり班による標記朝活動が始まりました。校庭中央に登校してきた児童たちが集まり出した頃、集合時刻前にもかかわらず上級生が落ち葉を拾う様子を見て、下級生も真似をしている姿が見られました。6年生から「1,2,3年生は落ち葉を拾い、4,5,6年生は掃除用具を使ってやります。」との説明後、教員室脇の桜の木周辺を中心に清掃活動が始まりました。長い柄の箒の持ち方を教えましたが、葉の元の部分などが地面の隙間に引っかかり思うように掃けないその様子を見て、登校してきた児童が「下手だなー」と冷たい言葉を掛けました。すると「難しいんだぞ。」と言い返して黙々と作業をしていました。活動が終わりに近づく頃、1年生が「ぼくも箒を使ってみたいな。」というので箒を渡すとぎこちなく落ち葉を集めていましたが、いつの間にか上級生が塵取りで受けてあげていました。最後に集合して「これだけ葉っぱが集まりました。」と本日の“成果”を確認して終わりました。
今夕からは雨が落ちてくるとの予報―明日以降も活動が続きます。
11月25日(月曜) 6年 セーフティ教室
「スマホ、携帯―正しい知識で賢くこなす」というテーマで通信会社の出前授業が行われました。より身近になったインターネットがメールやゲーム、音楽の他に海外では無人運転タクシーの運用も行われ、その実体験の話になると児童たちからは思わず感嘆の声があがりました。その他、遠隔操作、キャッシュレス決済、生成AIの話ではその精度、レスポンスの速さの向上から将来はそれらを上手くこなせる力も求められると、キャリア教育にも触れていました。
そして3本の動画を観てグループでの話し合い、感想の発表に続いてそれぞれの問題点について詳しい話がありました。
- 友達とのオンラインゲームでのトラブル
言葉の暴力(誹謗中傷)→ 侮辱罪、脅迫罪等の罪の可能性 → 将来(就職)等への影響 ← 冷静になる(深呼吸) よく考え想像する 思いやりの心を大切に
- メール等による書き込み閲覧
見続けたくなる、やり続けたくなるなる仕組み → ネット依存 睡眠時間の不足
← ネット依存度チェック表の活用 ルール作り(相談、可能な範囲で)
- 知らない人とのオンラインゲームでのトラブル
ボイスチャットルーム ← 知らない人とのやり取りはしない 疑うこと 会わないこと 最悪の状況を考えること(誘拐、殺人等)
動画を見つめる児童たちの眼差しはインターネットの「怖さ」を感じ、微動だにしない様子からその真剣さが伝わってきました。講師の方からは真剣に物事を考えられる、素直な子たちで授業を進めやすかったとお褒めの言葉をいただきました。
追記メモ ・「デジタルタトゥー」について知っている児童が半数以上
・課金によるトラブルの平均額が33万円で、トラブルに巻き込まれる半数は小学生
・厚生労働省が示す小学生の睡眠時間は9~12時間
・すべての人にある「肖像権」への配慮
11月 25日 (月曜) サイエンス朝会「浮かぶチョウ」 (静電気)
今月のサイエンス朝会は、静電気の性質を使った実験です。
電気にはプラスの電気とマイナスの電気があります。
ポリエチレンの袋にチョウの形を書いて切り抜きます。それをティッシュペーパーでこすります。すると、ポリエチレンはマイナスの電気を帯びます。
膨らませた風船もティッシュペーパーでこするとマイナスの電気が帯びます。
どちらもマイナスの電気なので、ポリエチレンのチョウと風船は、反発しあいます。
この性質を使って、チョウを飛ばすことができました。
休み時間に校長室前に遊びに来た子たちも上手にできていました。


11月22日(金曜) たてわり音読(8班~13班)
今朝もまだ校庭の地面が湿っていたため、教室での音読会となりました。教室に集まり始めると児童たちは「その本知ってる。とっても怖いんだよね。」と話したり、近隣の上級生が持っている本の表紙をのぞき込んだりしていました。開始時刻になるとまず出欠席確認をし、6年生が人員調整をして急遽3人組となったり、相手を変更せざるを得なくなったりするペアも出てきました。下学年児童を椅子に座らせて自身は片膝をついている6年生がいたので椅子を差し出すと笑顔で「大丈夫です。」との返答でした。児童たちは本の向き、高さ、傾け方等を考えながら読み聞かせをしています。早く終えて2回目の読み聞かせをする児童、学級文庫の中からリクエストをしてもらっている児童もいました。読み聞かせをしている様子を観ていると、表情豊かに、また工夫した読み方をする児童、下学年児童のつぶやきに応えたり、場面の様子を指で差したりして丁寧に読み進める児童もいました。
読書週間が来週11月26日(火曜)まで続きます。より多くの児童が本に親しむ時間を持てるようにしたいものです。
11月19日(火曜)には1班から7班が実施しましたが、気温が10℃を下回る北風の吹く朝だったため、本日同様教室で行いました。(・・・早く読み終わったペアは、下学年児童の好きな場面を開いてその説明をしたり、同じようなペア同士で本を交換して読み聞かせをしたりする様子も見られました。また先週の打ち合わせに欠席した児童に、読書中の下学年児童を尋ねて打ち合わせをしている様子も見られました・・・)
11月21日(木曜) 1年 SC科見学
「ぞうさんはかせになろう」の学習のためバスで上野動物園に行きましたが、薄く低く広がる雨雲の下、退園する頃に漸く雨合羽を仕舞うことができたという1日でした。
正門を抜け、間もなく突き当りの象舎を見つけると駆け寄って「アルン!」と子象の名前を叫ぶ児童もいました。そして担任から「アルンとウタイは裏側にいます」とアナウンスされると「そうか、じゃあこの象はスーリアだ。」と今週火曜日にオンラインで授業をしていただいた同園動物解説員の方の話を思い出して様々な会話が児童の間で弾みました。児童たちは象の足、耳を中心に観察しスケッチをしました。珍しく土山に横になっている様子から「まつ毛があった!」「おなかがピクピク動いた!」「大きなウンチがたくさんあった!」
という声が聴かれ、また近くの解説プレートを見ながら「ウンチが出てくるところはどこだ?」「ここ、肛門と書いてるところ!」「心臓は大きいんだね」「象も人間と同じで『進化』して来たんだね。」「『進化』って知ってるの?」「ポケモンで出てくるもん!」というコミュニケーションをとりました。
観察、調べ学習が終わった後に同園動物解説員の方に児童たちからの質問を受けてもらいました。
・スーリアが体を擦り付けていたのはなぜか
・寝ているときに体がもぞもぞ動いたのはなぜか
・どうして口からゆげが出ていたのか
・ウタイが奥の部屋に行ったり戻ってきたりしたのはなぜか
・どうしてスーリアだけ別にするのか
・アルンはなぜタイヤを運ぼうとしたのか 等々
「お弁当」の時間が近づいたのを感じ取ったのか「お昼ご飯はいつ食べるのですか?」「今日は何回ご飯を食べたんですか?」という質問も出ましたが、解説員の方から「どの象が?」「どこで?」「どこが?」「どのように?」等々の切り返しの質問がありました。
退園する前には10分ほどの自由行動の時間が取れ、象舎に限った観察を再度行い、帰路につきました。
11月20日(水曜) 1、3、5年 セーフティ教室
警備会社社員15名による標記教室が6コマ行われました。
1年生は登下校中の危険回避の心構えを「いかのおすし」のキーワードで講師、担任とのロールプレーイングが主体の学習を行いました。終盤では不審者役の社員が登場して児童たちの学習の成果を確かめ、「すぐにげる」の学習では逃げる場所(家、交番、学校等)逃げ方(人のいる、明るい方、相手が車に乗っていたら、車の後ろの方向等)等具体的に、また理由も考えながら学びました。最後に児童からの質問に答えていただきました。
「家が遠い人はどうしたらいいのか」「捕まりそうになった時はどうしたらいいのか」「足とかを縛られてしまったらどうしたらいいのか」―こどもたちの真剣さが伝わってきました。
3年生は留守番をしているときの防犯意識を高める学習をしました。まず留守番は帰宅して家に入る時から始まっているという気持ちでいることを学び、5つのことを確認しました。そして留守中に訪問者があった場合、大地震や近隣で火災が発生した場合の対応、行動
について学びました。訪問者に対しては扉を開けなかったり、応対しなかったりとすぐに挙手をしたり回答したりできていた児童たちも、地震や災害が発生した想定ではじっと講師の話に聞き入っていました。今日のすべての学習を通して言えることは、いかに日常からいろいろな危機意識をもって家庭で話し合ったり準備をしたりしておくことが重要であるかということでした。
5年生はインターネットを使うには「疑う力」も必要であるとういうことを、以下のことから考え、確かめました。
・世界中の人から見られていること ・相手の本当の“すがた”が見えないこと ・書き込んだことはずっと残ること
そして「SNS利用時」「メールが届いたとき」「写真や動画でみんなを喜ばせたいとき」「インターネットを見ているとき」の4つの事例漫画から“危険を見つける”グループ学習、発表を行い、学びの深まりが各所で見られました。
「取り敢えず、これが怪しいかな・・・」「そういうことか!」「連絡って・・・誰に」「付いていくって・・・人によるよね」「個人情報が抜き出されてない?」等等
11月19日(火曜) 5年 SC科「プラスチィックとわたしたちの生活」
企業ゲストティーチャーを招き、前半に生分解性プラスチック開発の経緯や製品に込められた願いについての講義があり、その後児童たちからの質問を受けてもらいました。まず生分解性プラスチックが製品として使用されて4~5年、研究自体は30年前から行われており、製品表示(バイオマス由来の素材、生分解する素材、生分解性バイオマスプラスチック等でも身近なものとなっていることの説明がありました。そしてポリプロピレン、木、生分解性プラスチックで作ったスプーンを水中、土中で分解させる実験の様子が写真で示されると児童たちの熱い視線が電子黒板に注がれました。また木も、作るために大量の水や諸エネルギーを使うため環境やコストを考えるとプラスチックよりも“良い”とは一概に言えないという言葉に自身の考えを深めているようでした。
児童からの質問・・・・・
「1つのプラチック片にどのくらいの微生物が必要なのか。」
「どうして本社の大阪の工場で、その微生物が見つかったのか。」
「生分解を効率よく行うためにはどうしたらよいか。」
「生分解性プラスチックなら、ウミガメとかが食べてしまっても大丈夫か。」
「海に『微生物』を撒けば、プラスチックごみ、マイクロプラスチック問題も解決するのではないか。」
・・・・・中には、過日、東京科学大学で教わった時のことと比べて質問をする児童もいました。
11月18日(月曜) 4年 野球教室
日本プロ野球団の小学校体育支援事業として、団直営スクールアカデミーのコーチによる4年生体育「ベースボール型ゲーム」授業がありました。授業前の休み時間に校庭で準備をするコーチたちに校舎3階から手を振ったり、挨拶をしたりとこどもたちの学習への期待の高まりが感じられました。前半は自己紹介、準備運動に続いて野球についての基本的な話がありました。野球には4つの動きがあり、今日は特にバッティングについての指導が中心で「合わせて、引いて、振る」を唱えながら行うことの良さを教わりました。そして大谷選手も10回のうち3回ヒット等を打って“世界一“になったことから10回のうち7回は失敗しても大丈夫だという話がありました。すると代表児童が打撃の練習を全員の前でやるときに「失敗しても大丈夫だよ。」「がんばれ」等の励ましの声があがり、打った後には拍手が起こりました。
冒頭、野球を観たこともない児童が3割ほどいることがわかりましたが、ゲームが始まるとボールの行方に集中し、また児童たちの歓声が途切れることなく楽しく“野球”の勉強が行えました。そしてコーチの方々を見送り、去られる姿を教室から見つけると挨拶や感謝の言葉が“飛んで”きました。
11月16日(土曜) わくわくスクール「シャボン玉教室」
今日の土曜わくわくスクールは、1.2年生対象の「シャボン玉教室」です。
くらりか(東工大OB)の6名の皆さんによる講座です。
まず、初めに表面張力について学びました。一円玉をそうっと水の上に乗せると、一円玉は水の表面を少し凹ませながらに浮きます。これは表面張力の働きです。その水に、少量の洗剤液を付けたつまようじの先をつけると、あっという間に一円玉は沈みました。さらに、水に発泡スチロールの船を浮かべ、そこに同じように洗剤液を付けたつまようじの先をつけると、船が進みました。表面張力の働きがなくなったからです。
次に、ストローと針金で作った正四面体や正六面体の枠にシャボン液に浸すと、不思議な膜の形になることを学びました。
フラフープを使って、人がシャボン玉に入る体験や、様々な形の枠でシャボン玉を作る活動をしました。
こどもたちは、とっても楽しく学んでいました。






11月15日(金曜) 3、4年 図工 ~展覧会に向けて~
3年生は「へんてこ山」(水彩画)と「シール版画」を机上に並べて展覧会に出す作品を各自で選びました。中には、「(片方の)作品がうまくできなかったから」「深海の様子が上手く出せなかったから」と消去法で考える児童もいましたが「ここのグラデーションのところがいいから」「奇妙なところが出せたから」「山が噴火して雷も鳴っているところが迫力あるから」「この部分が色を何色も重ねられたから」「カラフルにできたから」「かわいい猫ができたから」とアピールポイントを教えてくれた児童もいました。その後グループ作品「ばんざいロボット」(立体作品)についてタブレット機能を使って、作品名、特徴、お気に入りポイント、頑張ったところを話し合いながらまとめました。
4年生は「きらめき」(平面作品)「木」(水彩画)を机上に並べて展覧会に出す作品を各自で選びました。不採用にした理由としては「ゲームキャラクターを真似したから」「影のつき方を失敗したから」という声が聞かれました。また選んだ理由として「海に行ったことはないけど、キラキラ光っている様子がいいから」「ユニコーンが雲の上にいるところがかわいいから」「ハリーポッターのイメージが出て、特にふくろうの目が上手くできたから」「木が伸びていく様子が描けたから」「紙を継ぎ足して大きな木が描けたから」「葉っぱだけで7色も使って描いたから」とお気に入りの作品を説明してくれました。後、これも完成している「ひみつのすみか」(立体作品)をタブレットで写真に撮り、解説文を付けていました。
11月14日(木曜) たてわり音読準備
来週のたてわり音読会に向けて朝の時間に標記活動を行いました。6年生は登校後間もなく1年生を迎えに行ったり、諸準備をしたりと慌ただしい学校生活のスタートとなりました。基本は上学年1名と下学年1名のペアで話し合っていきますが、児童数の違いから上学年2名で下学年1名に“聞き取り”をしているところもありました。
下級生の希望を聞くと「お化けの話」「面白い話」「動物が出てくる話」「科学についての本」・・・中には書名を伝える子、作者名のみ限定の子と様々でした。そして「動物は何が好きなの?」「コアラ」「パンダは好き?」「うん。」「この中で1番読んでほしいものは何?」「〇〇〇〇〇」「2番目は?」・・・等の上級生の質問が続き、早々に“終わった”ペアの上級生の中には「たてわり音読メモ」の裏側に、似顔絵を描いてあげる児童もいました。
休み時間には、一昨日にお知らせした秋の読書週間の中、本貸出の手続きを受ける児童の列が図書室後方まで伸びていました。
11月13日(水曜) 二階堂研究所訪問
東京科学大学准教授、二階堂先生の研究室を訪ねました。先生の研究テーマは、DNAや生物等の進化です。今回は2年生で初めて東京科学大学に訪問し、キリンの体のつくりや暮らしを調べた中で、分からないことや詳しく知りたいことについて質問し、お話しいただきました。
「人間は2足歩行なのに、キリンはなぜ4足歩行なのか。」
「キリンの細胞の数はいくつあるのか。」
「キリンの赤ちゃんは生まれてすぐに草を食べるのか。」
「キリンという名前はどこからきたのか。」
「この世の中にキリンはどうやって現れたのか。」
「キリンの体でいろいろなところが長いのはなぜか。」
等、たくさんの質問がこどもたちから出ました。人間の祖先はチンパンジーであるが、キリンの祖先は、「オカピ」と同じであるということ。それは、アフリカで見つかった骨から分析されたが、オカピとキリンが似ている理由は、途中で遺伝子が分かれたからであること。高い木の葉を食べようと思うと背が必要となるため、キリンの首や足が長くなることで競争世界に勝ち残ってきたこと等、こどもたちに合わせてお答えいただきました。こどもたちは一生懸命メモを取っていました。
二階堂先生でも未だに分からないことがたくさんあるようで、「自分なりにいろいろなことを考えるのが『はかせ』なんだよ。」というお言葉もいただき、また1歩「キリンはかせ」に近づいた2年生でした。
11月13日(水曜) 「ハルちゃん(うさぎ)ふれあい週間」
今週の月曜日から飼育委員会による標記“ふれあい週間”を行っています。内容としては2,3名ずつエサやり体験をするのですが、待機している間は飼育委員児童がクイズ等で楽しませています。そんな中、当番ではない児童が「(当番人員が)足りてる?」と声をかけていく姿も見られました。
ハルちゃん(うさぎ)は人が小屋に入ると警戒して棚の奥に行ってしまうことが多いのですが、運よく棚から下りてきたときに当たったグループは「緊張した!」「もふもふしてた!」「かわいかった!」とやや興奮した様子で帰ってきました。エサやり後に流し場で手洗いをしている児童たちからは「1年か2年の時は、逃げ回ってえさをやることができなかったけど、今日はあげられた!」との話も聞かせてもらいました。休み時間が終了となりエサやりができなかった児童は、19日(火曜)以降の“予備日”に再度来てもらうように伝えていました。
11月12日(火曜) 秋の読書週間 始
本日から11月26日(火曜)までの読書週間に、より多くの児童に読書に親しみより多くの本を読んでもらおうと図書委員会が計画を立てて諸準備を進めてきました。今回は本を1冊借りると双六かルーレットに参加でき、ゴール後輪投げゲームの結果によって様々な“もの”がもらえるというものです。その“もの”とは・・・手作りしおり、読みたい本の予約券、「よみよみくん」(リーディングトラッカー)です。
これらは中休み、昼休みに実施されますが、他の委員会活動や、昨日から行われている「ハルちゃん(うさぎ)ふれあい週間」の他に、次時の授業のために教室移動を早めに行う学級もあり、図書室に向かうには計画性をもっていかなければならない児童たちがいます。
中休み早々に図書室に行くと「3時間目が調理実習だから委員会の当番の仕事をどうしようか」と担当の教員を待っている児童がいました。暫くすると次々に児童が本を仮に来ました。「えっ、2冊借りても双六は1回しかできないの?」(なら・・・1冊ずつ借りたら・・・2回できるんじゃないの?)となかなか・・・児童たちの読書意欲の“高まり”を感じました。
11月11日(月曜) あいさつ運動 始
本日から来週の月曜日まで3,4年生が中心となり、標記の活動を行います。当番児童たちは他の児童たちが登校する前から打ち合わせ、諸準備を行いました。その後校内各所定の場所に1、2名ずつ立番し、大勢の児童を前にして皆緊張感しながらもしっかりとやろうとする様子が窺えました。そして活動の振り返りをするために再度集まると「120名に挨拶をした!」「僕は123名!」と笑顔で報告してくれました。
一方、放送室では朝のアナウンス原稿の確認、飼育小屋では今朝、小雨が降っていたのでいつもより早く登校して(「雨降りだと活動中に傘を差したり閉じたりして時間がかかるから」―と)うさぎのハルの世話、校庭では上下の確認をしながら丁寧に校旗の掲揚―と朝早くから児童たちの活動が始まっていました。
11月8日(金曜) 全校遠足 ~都立林試の森公園~
本校の特色ある教育の1つである、たてわり班での標記活動を行いました。出発式では計画員会の6年生が司会進行し、遠足で気をつけること、守ること、自覚することを確認し、駅に向かいました。大岡山駅から武蔵小山駅までは時間差をつけて分乗しましたが、車内でも上級生が下級生の手を握ったり、肩を抱くように支えたりしていました。また電車が揺れる前に手摺に導いたり、「扉が閉まるから気を付けて」と下級生を見守ったりする姿も見られました。
午前中は6年生が企画した遊びの各ブースを回って様々なクイズやゲーム等を楽しみました。移動中に木の幹にいたオオカマキリや地中の甲虫幼虫、角張った変わった石を見つけたと教えてくれる児童がいましたが、一方でグループから遅れたり、はぐれたりしてしまう児童がいて上級生を悩ませていました。ブースによっては「来客」がなく、呼び込みをしたり、急遽、看板をかいたりするグループもありました。また、フリーで巡回している教員相手にやって見せたり、他校の児童を呼び込んでやらせたりもしていました。
昼食もたてわり班ごとにまとまり、食後のおやつも美味しくいただきました。途中大きな蜂が、ある児童に纏わりつきましたが微動だにしない冷静な対応で「あれは外来種のマル・・・スズメバチだと思う」と呟いて周囲の児童たちを唸らせました。またレジャーシートの間からトカゲが姿を現し一時騒然となりましたが、ある児童がトカゲを捕まえて離れたところに逃がしてあげていました。
午後は、たてわり班ごとに5日(火曜)の全校遠足事前集会で周知した遊びを行いました。
「だるまさんが転んだ」「おにごっこ」「ドロケイ」「インベーダーゲーム」「ドッジボール」「フリスビードッジボール」―午前中は、多くの小学校、幼稚園、保育園が来園していましたが、午後は3つの広場を清水窪小学校が悠々と使うことができて児童たちも大満足の様子でした。
11月7日(木曜) 健康・体力の向上に向けて ~持久走月間等~
昨日から朝の時間を使って、持久走月間が始まりました。今日は2、5年生が実施ということで校庭に出始めた児童たちは朝の冷え込みに加えて折からの北風に、自然と日なたに集まっていました。準備運動後に各学年が前後半に分かれて5分間走をしましたが、2年生は1,2,3コース、5年生は4,5,6コースに、そしてスタートの位置も5か所に分かれて行いました。スタートの合図があると走者を見守る児童たちの応援の声が響き、デジタルタイマーの表示に合わせて終了10秒前からは大きな声でカウントダウンが起こりました。
中休みには多くの児童たちが校庭に出て青空の下、ドッジボール、バスケットボール、最近流行りだしたバレーボール、縄跳び、鉄棒、アマゾンジャングル、ジャングルジム、倒電柱等の遊びを元気に行っていました。
また授業では1時間目に6年生がマット運動、2時間目は持久走、ボッチャ、3時間目には5年生が縄跳び、ベースボール型ゲームを行い、午後には5時間目は4年生がハードル走、6時間目には6年生が、鉄棒、持久走を行います。
11月6日(水曜) 6年 社会科見学
午前中は参議院特別プログラムの学習、午後は国会議事堂見学をしました。“プログラム学習”では「自動車リサイクル」に関する法案について提案する委員会での話し合いから始まりました。予め大臣、副大臣、政務官、委員、委員長、議長役に決められていた16名(長野県上田市の児童たちと分担)が委員会席に着き、実際の議事録(簡易版)に沿った審議を始めました。そして委員会で可決された法案を参議院議場でさらに審議し、会場にいる児童全員を議員と見立てて、ボタンによる採択(現在は非採用)結果がモニターに表示されると会場には少し緩んだ空気が広がりました。委員会席で発言等をした児童は「緊張して何が何だかわからなかった」と漏らしていました。そして議場の傍聴席に向かう赤絨毯の敷かれた廊下に並ぶ背の高い扉の上に掲げられた「第□□委員会室」という札を見ながら議事堂内を急ぎ足で見学しました。
皇居外苑で昼食を取りながら話をしていると、児童たち全員が初めて国会議事堂に来たのだろうと思っていましたが「2回目」という児童がいたので驚きました。
午後は上野の東京国立博物館に行きました。まず、動画「東博とは」等を使って学芸員に方から話を伺いました。そして最後に「楽しみ方」として「じっくりと観る」「想像しながら観る」「比べて観る」「季節を感じて観る」の4点を教えていただき、グループごとに計画に沿って見学をしました。
「これ、かんざしだね。」「こんな大きい硯がある!」「あっ、これだ!(動画で見た頼朝座像を見つけて)」「これ(銅鐸)鳴らしていいのかな?」「(浮世絵スタンプをして)ズレちゃった。難しいな。」
集合場所の本館前に集まった児童からは、
「(足を摩りながら)痛くなっちゃった。」「時間がなかった!」「はにわ展を見たかったけどチケットがなかったので入れなかった。」等々の声が聞こえてきました。
11月5日(火曜) 全校遠足事前集会
今週8日(金曜)の全校遠足に向けて朝時間を使い、各教室にたてわり班ごとに集まって事前確認等を行いました。連休明け登校直後の活動ということもあり、特に1年生を迎えに行ったり、会を進行したりする6年生が、廊下を小走りに急ぐ姿が多く見られました。
まず、オンラインで担当教員から全校遠足のめあてに沿って話がありました。大集団での行動、活動となるために、集合した時の話の聞き方、高学年として、また低学年としての姿勢について、そして特に電車や公園等公共の場でのマナー、ルールについて確認しました。その後各教室では6年生が会を進め、移動時のペア児童決め、班遊びの内容、ルールの説明そして校帽(1年生は黄色の帽子)にリボンを付けました。集会が終わると、班ごとの色とりどりの校帽を被った児童たちが各教室に戻ってきました。そして中休みには黄色の帽子に様々な色のリボンを付けた1年生たちが、自然観察、縄跳び、固定遊具、クラス遊びドッジボール等の遊びに興じていました。全校遠足の準備は大方終了―後は体調管理に気を付け、大きめの水筒、弁当、おかし等の忘れ物がないようにー
11月1日(金曜) 1年S C科「ぐるぐるかざぐるま」
前時(昨日の研究発表)の児童ワークシート「羽の数を少なくしたらどうなるか調べたい」から「羽の数を変えてよく回る風車を作ろう」というめあてで標記授業が行われました。ワークシートの図(丸と四角)に羽の切込みを書き入れながらどのようにしたら“よく回るか”を考え、後に数名が皆の前でそれを発表しましたが、丸、四角の紙を選んだ児童はちょうど半数ずつとなっていました。風車づくりが始まると児童たちの腕が上がり、1回目でよく回る風車を作れる児童が次々と現れ、担任は驚きの声を上げていました。
「今までで1番よく回ってる!」「ぼくのは、軸がないからぐらぐら回るんだ」
「うーん、折り方を変えると早く回るかも・・・」「(送風機から離しても)まだ回ってる!」
「ここまで離したら回らなくなった」「(羽の)ここを折ったらいいんじゃない?」・・・
こどもたちはいろいろなことを話しながら幾つもの風車を作っていましたが、折らずに丸めたり、作った風車を2つ重ねてみたりと様々な工夫をしていました。
午後は3年生がSC科「めざせ!こまキング」の学習をします。
10月31日(木曜) 大田区教育研究推進校研究発表会
「今日が本番だからね。」と言われて思わず表情が緩む児童が多いのは、緊張する気持ちからなのか、今までの学習の積み重ねで自信があるからなのか・・・授業が安全にまた快適な環境で行われ、確かな学力が身に付いたか・・・授業後3つの研究分科会で学校側から研究内容の説明、参加者との質疑応答を経て体育館での研究全体会が行われました。研究全体会では本校の研究を支えてきてくださった文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官 有本淳先生、元昭和女子大学特任教授 小川哲男先生、東京工業大学 現東京科学大学名誉教授 鈴木正昭先生を交えてのパネルディスカッションが行われました。
本研究発表会では、19名もの保護者の方々がボランティアとしてお手伝いしてくださり、また清水窪応援隊の方々には事前の準備、打合せ等からお力添えをいただきました。お陰様で、大田区内をはじめ、大田区外都内近県から多くの先生方、地域、企業、保護者の方々、また現役大学生等、350名を超える方々で研究発表会は盛会裡に終えることができました。ありがとうございました。
10月30日(水曜) 3年 理科「風やゴムのはたらき」(7時間扱い中の4時間目)
本日も明日の大田区教育研究推進校教育発表会に向けて「ゴムの力の大きさを変えると、物を動かすはたらきはどのように変わるのだろうか」について考える標記事前授業が行われました。前時の(「風の力」)を受けての本授業での先の問題を考え、予想を個人で考えてからグループ内で意見交換をしました。「物を動かすはたらきは大きくなるだろう」「ゴムを伸ばして縮めると手が痛くなるから・・・」「ゴムを伸ばすと勢いがつくから・・・」「ゴム飛行機は遠くに飛ばせるから・・・」これらの予想をもとに次の実験方法を考え、幾つか出た中から正しく測定できる「車」を選びました。
明日は7時間扱い中の5時間目で、体育館で実際に「車」を走らせて実験を行います。
10月29日(火曜) 1,2,3年 「ひかりのプロジェクト作品作り」
大岡山北口商店街振興組合のSDGs推進イベントの一環で、本校では1,2,3年が標記制作をもって参加します。「ひかりの実」とは、果実袋にクレヨンで「笑顔」を描き、中にLEDの小さな光を入れて膨らませる作品のことで、京都のアーチスト高橋匡太氏によるアートプロジェクトです。制作に取り掛かった児童は、「去年もやった!」とにっこりして指でグットサインを送ってきたり、「お母さんの笑顔にしよう。」「キャラクターものはダメだと言われたけど、アンパンマンみたいになっちゃった。」と友達と話したり、作品を見せ合ったりしていました。作品は12月1日(日曜)から12月25日(水曜)まで昨年度同様、駅前ロータリーにある桜の木に展示予定です。
10月28日(月曜) 1年 生活科「かぜとなかよし」
本日も10月31日(木曜)の大田区教育研究推進校教育発表会に向けて「かぜでうごくおもちゃであそぼう」について考える標記事前授業が行われました。研究発表会ではSC科(サイエンスコミュニケーション科)と他教科との関連も明確にし、1年生では生活科と2年生では算数科とそして3年生以上は理科の授業も行います。
前時では提示したもの(スズランテープ、ポリ袋、紙飛行機、紙コップカー、風車、風輪等)で風を利用して遊び、それぞれの動きを「ひらひら」「ヒュー」「スー」「くるくる」「ころころ」等の言葉にたとえ、今日は体育館で思う存分遊んだ後に「気づいたこと」と「これから遊んでみたいこと」について考え発表しました。
「気づいたこと」
・横から扇いでみると変な動きになる(速くなる)
・紙飛行機は上に向けて投げるとよく飛ぶ
・ビニル袋を持って走るより、扇風機で“囲んだ”時の方が空気がたくさん入る
・風を送る向きを変えると、回ったり回らなかったりする
・紙コップカーは風を当てる向きでスピードが変わった ・・・・・・
「これから遊んでみたいこと」
・ティッシュの空き箱でスポーツカーを作りたい
・紙飛行機をもっと高く飛ばしたい
・トラックや飛行機を作りたい
・ペットボトルで潜水艦のようなものを作りたい ・・・・・・
次時はいよいよ発表会当日。風で動くおもちゃ作りを行います。
10月25日(金曜) 2年SC科「キリンはかせになろう」
本日も10月31日(木曜)の大田区教育研究推進校教育発表会に向けて「体の一部が長い動物は、何か理由があるのだろうか」について考える標記事前授業が行われました。まず、10月3日(木曜)SC科見学での写真から上野動物園の見学を想起して学習を深めました。
9種類の動物の体の長い部分(足、くちばし、舌、首、尻尾、胴体・・・)に着目し、キリンの学習で得た知識で各児童が選んだ動物の学習予想を立て、予想の意見交流を行った後に指導者から配信された「オクリンクプラス」を使っての資料(動画、事典等)を使って、その動物の長さの理由を考えました。
10月24日(木曜) 読み聴かせ
1年1組 「おかしとおうちくれませんか?」 「てんてんきょうだい」
1年2組 「らくごえほん「てんしき」」 「どうぶつ勝負はっけよい」
2年1組 「子どもを守る言葉「同意」って何?」 「YES,NOは自分が決める!」
2年2組 「おちばのプール」 「どんぐりころころ そのあとは・・・」
3年1組 「おおきくなりすぎたくま」 「ねえ、どうれがいい?」
3年2組 「おふろだいすき」 「字のないはがき」
4年1組 「でんせつのじゃんけんバトル」 「そそそそ」
4年2組 「おうちりくじょうグランプリ」
5年1組 「宇宙人っているの?」
5年2組 「綱渡りの男」 「すごいね!みんなの通学路」
5年3組 「いつもちこくのおとこ~ジョン・パトリック・ノーマン・マクヘネシー~」
「もののけしょくどう うらめしや」
6年1組 「わたしのまちです みんなのまちです」 「あんぱんまん」
6年2組 「ながみちくんがわからない」
10月24日(木曜) 1年SC科「くるくるかざぐるま」
本日も10月31日(木曜)の大田区教育研究推進校教育発表会に向けて「丸型の工作用紙を使ってよく回る風車を作ろう」の標記事前授業が行われました。まず、前時までの学習のまとめ「よく回る風車のコツ」をもとにどのように紙に切込みを入れて折るかを考えました。
「丸い形だから、扇風機みたいな形の羽にしたらいいと思う。」
「昨日成功したやり方で、羽を“上下上下”にしたらいいと思う。」
中には発表を促されて発表しようとしたら、考えが変わっていた児童もいました。
各自で作った風車を送風機に向けると「予想通り!」「すっごい回った!」「渦巻になってる!」等の声があがりました。実に様々な形の風車が出来上がりましたが、以下のような風車も回っている様子を見て、作った児童がニンマリとしていました。
・切込みを入れた後に、しっかりと折り込まない平板な風車
・軸を立てて、羽を横にして皆とは違う向きに回す風車
また、細かい折り込み方をしたり、羽の大きさを変えたり、切込みの間をテープで留めて調整したりして何回も作って工夫を重ねる児童たちもいました。
今日は午後から、来年度入学予定児童の就学時健康診断が行われました。風車を作っていた児童たちも1年前は・・・
10月23日(水曜) 4年SC科「飛べ!水ロケット」
本日も10月31日(木曜)の大田区教育研究推進校教育発表会に向けて「水ロケットをより遠くへ飛ばすためには、とじこめる空気の量をどうすればよいだろうか」について考える標記事前授業が行われました。まず、実験中の事故を防ぐために安全のきまりを確認しました。
・防護メガネは、一部ではなく、全員が使用すること
・ロケット発射は皆に声をかけてからカウントダウンすること
・飛ばしたロケットを再度スタート位置に戻すときは、理科室前を通り一方通行で行うこと
そして水の量は200mlにして空気の量を変えたロケットを3回ずつ飛ばしました。実験は飛距離を測定する児童、タブレットに記録入力する児童と分担して学習を進めました。そして容器からの水漏れ、ロケットに装着したおもりの離脱等の不具合が生じたり、実験結果が予想と異なる数値となったりする場面がありましたが、その1つ1つに対応し、また考えを巡らし学習を深めていました。
不安定な天候の中、雨天時の対応として雨合羽を準備していましたが、児童たちはそれらを使用せずに学習を終えることができました。
10月22日(火曜) 5年 SC科「プラスチックと私たちの生活」
10月31日(木曜)の大田区教育研究推進校教育発表会に向けての標記事前授業が行われました。「プラスチックはなぜこれほどまでに使われているのだろうか」について考える授業、またその授業を受けて「プラスチックの使用にはどのようなメリットやデメリットがあるのだろうか」について考える授業の2つの授業を検証しました。まずは先の問題について個人の考えをそれぞれ付箋に書き出し、それをもとにグループで学習ボードの「ピラミッドチャート」にメリットやデメリットそれぞれの“順位付け”を考え、最後に各グループの“最上位”一番大切なことを発表しました。担任からは事前に「この学習にはきちんとした答えはなく、考えの根拠をしっかりと表現できることが大切」と伝えられていましたが、児童たちのグループ活動の中では様々な声が聴かれました。
「そうか・・・すっごく納得した!」「このメリットとこのデメリットは繋がっているな」「海の生き物のことを考えると・・・」「今の私たちの生活の中からプラスチックのない生活を考えると・・・」等々
授業後に参観した教員を中心に、今後指導内容に修正を加え発表会の準備が進められていきます。
10月21日(月曜) 6年 毛筆書写「友情」
10月2日(水曜)に3年の毛筆書写について掲載しましたが、今日は週はじめ1,2校時に行われた標記授業についてお知らせします。学習のめあては「筆順と点画のつながりについて気を付けてかこう」で、特に「情」の立心編の2つの点の長さ、大きさ、バランスに気を付けるように、また「友」でも全体の字形が正三角となり、3つの払いの先が正三角形の一辺に揃うようにと指導がありました。1校時は2枚の半紙に練習し、続いて清書に移りました。1枚目の練習では半紙に自身で直したいところを赤鉛筆で記入し、それをもとに近隣の児童と話し合う時間も設けられました。「ここは狭く」「ここはもっと長くしたほうがいいよ」「真っすぐに」「そろえて」・・・2枚目の練習に入るときには改めて姿勢を正すように言われ、緊張した面持ちで丁寧に筆に墨を含ませ、筆を立て、力の入れ方に気を付けて作品を仕上げていきました。
10月21日(月曜) 全校朝会「スポーツの秋」
先週までは、夏のような暑さでしたが、今朝は少し寒いくらい、涼しい季節になりました。スポーツの秋です。
今年6月に行ったスポーツテストの結果です。
男女とも、練習に取り組んで本番を迎えた「反復横跳び」と「50m走」は、全学年で、東京都の平均を上回りました。また、ほとんどの学年で「体力合計点」も上回っていて、清水窪のこどもたちの体力が東京都を上回っている状況が分かりました。
来年も、体力テストでも良い結果が残せるよう頑張りましょう。
晴れた日は、外に出て積極的に運動しましょう。なわとびや走ることを通して体力を高めましょう。
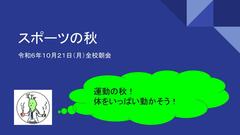


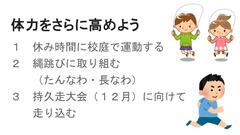
10月20日(日曜) 2024清水窪 秋祭り(ミニ縁日)
PTAサポセン主催の標記イベントが行われました。今回は“イベントチーム”が主催し4月の新入生イベント、先月の夏イベント同様、児童たちを大いに楽しませました。会場は体育館のほか家庭科室、理科室も使用し、卒業生のお手伝いもあり、どこも盛況で廊下には行列ができて児童たちは順番が待ちきれない様子でした。
ヨーヨーつり、スーパーボールすくい、1円玉おとし、射的、つめほうだい、おかしつり、カップでゲット、輪投げ・・・昨年度好評だった“大人用” つめほうだいは今回も実施、射的では昨年度の反省を生かして弾一つ一つに紐を付けて飛び散らないように工夫していました。
「サポセン」はサポーターズセンターの略称で、イベントチームのほか、広報チーム、校外チーム、総務チーム、会計チーム等に分かれ、本校の教育を支えています。
10月18日(金曜) 4年 音楽「旋律の特徴を生かして歌いましょう」
まず「ゆかいに歩けば」の3番でアルトパートに主旋律がつられることなく「滑らかに」歌えたと評価を受けた後、本日の練習課題曲の「とんび」を歌いました。1回目「とんび」の歌唱ではとんびが鳴くところで自然に強弱をつけて歌えていましたが、今日はそれを意識して「形」にしようと授業が進められました。後半はグループに分かれ、特にとんびが鳴くところの強弱のつけ方を話し合い、練習を重ねました。グループ毎でまとめられた「思い」が生み出されているかが大切であり、どのような工夫を加えてもよいと伝えられると、こどもたちは話し合いを重ね、また歌唱練習を何回も繰り返しました。どのグループも息の使い方や声の出し方に気を付けて真剣に、またいきいきと活動しました。グループ毎の発表会では、拍手を受けたらお辞儀を返すことも指導され、最後に自分の考えなどを書き込んだ教科書をタブレットで写真に撮り、振り返りの言葉とともに「オクリンク」機能を使ってタブレットからそのまま提出して授業が終わりました。
10月17日(木曜) 1年生 生活科見学(多摩川台公園)
1年生は、秋をさがしに、電車に乗って多摩川台公園に行きました。
大岡山駅から電車に乗り、多摩川駅で下車。そこから徒歩で、公園に向かいます。
公園には、たくさんのドングリが落ちていました。中には、100個以上拾った子もいました。
ほかにも、色づいた木の葉や松ぼっくり、キノコなど、たくさんの秋を見つけました。
広場では、みんなで楽しく遊びました。
公園内や電車内のマナーもとても立派な1年生でした。
今後の生活科の学習では、今日見つけた秋のものを使って、おもちゃなどを作り、遊びます。








10月17日(木曜) 登校~休み時間
本校には飼育小屋があり、委員会の児童たちが登校時刻前から始業間際までウサギ(ハル)の世話をしています。また児童の中には自宅で飼育している虫を大事そうに抱えて登校してくる児童がいます。休み時間になると、校庭ではドッジボール、バスケットボール、鬼ごっこt等の集団遊びそして10月11日(金曜)に紹介した“短なわ”をする児童のほか、アマゾンジャングル、鉄棒、登り棒等の遊具で一人、また少人数で遊ぶ児童の姿が見られます。さらに校庭の端には、飼育かごや廃材のプラスチィックパック等を持って植込みや池の辺りに目を凝らす児童たちも多く見られます。1番の人気はダンゴムシ。「こどものダンゴムシがこんな大人になったんだ!」と小さな自然を再現した飼育かごの中を見せてくれたり、掌に握られたペットボトルのキャップに詰まったダンゴムシを見せてくれたりしました。他にもカマキリやバッタ、アリ、アゲハチョウ、青虫などの幼虫、カナブンの羽等を大切に持って歩く児童たちもたくさんいます。午前中に「秋さがし」で多摩川台公園に出かけた1年生が昼休みには元気に外に出てきました。その中で飼育箱の中のものを全て出している児童がいたので声をかけると「この幼虫を逃がすんだ」とのこと。「どこに逃がしたらいいかな?」と声をかけると思い立ったように走って行きました。現在本校の校庭脇植込みには赤いヒガンバナが咲き終わり、黄色のキンモクセイが満開に咲き誇っています。
10月16日(水曜) 2年 体育「ひょうげんあそび」
教室から係を先頭に整然と体育館に移動し、授業が始まりました。準備運動では短縄も使用して汗をかきました。30秒一斉跳びの前回し跳びでは、7名程の児童が1度も縄に引っかかることなく跳びきりましたが、後ろ回しとびでは15秒程で全員が引っかかっていました。「前(回し)跳びなら自信があるのにな」「グーパー跳びのコツを教えて!」「二重跳び出来るよ。見てて!」と様々な声が届きました。標記の学習ではまず、発表グループ毎の練習から始まりました。
・動作の確認 ・動く方向の確認 ・力加減の確認 ・(手を繋ぎ、離す)タイミングの確認 ・会場(体育館)の使い方の確認 ・・・・・そして、グループ毎に皆の前で発表を行いました。
(1)修理の必要なメリーゴーラウンド (2)ボーリングゲーム (3)けいさつ (4)カメの散歩(5)虫取り (6)アザラシ (7)コーヒーカップ (8)踏切を通る車と電車
発表が終わるたびに大きな拍手が起こりました。後日、発表会の様子は動画鑑賞をして振り返りをします。
10月15日(火曜) 4年 SC科「飛べ!水ロケット!」
10月31日(木曜)の大田区教育研究推進校教育発表会に向けての標記授業が行われました。
今日はどの水ロケットの玉がより遠くまで飛ぶか順番を考え、確かめるという課題を立てて授業が始まりました。比べたのは(1)空気のみ(2)水のみ(3)水、空気の順(4)空気、水の順の4つでした。最初にタブレットにまとめた個々人の考えを発表し、次に4人組でホワイトボードにそれらをまとめました。この学習は本研究の「対話2」に当たり、こどもの相互の言葉や絵図等を通した科学的な思考や表現の交流を通して科学的な概念形成へつなげてました。その後実験を行い先の考えを確認、修正、訂正しました。また実験での水ロケットの発射位置や到達地点等の条件制御は各グループで決めていました。「1m50センチメートルくらい・・・」「・・・くらいじゃだめだよ」「10センチメートル!」「落ちただけだから0センチメートルだよ」教室はこどもたちの活気ある声がしばらく止みませんでした。
10月11日(金曜) 5年 SC科見学「城南島海浜公園・葛西海浜公園」
5年生のSC科では、「プラスチックとわたしたちの未来」の学習しています。お茶の水女子大学の里 先生から、海洋プラスチックについて、事前に調査方法を教えてもらい、今日は東京湾の2か所で調査を行います。
まず初めに来たのは、城南島海浜公園のつばさ浜です。各グループで、バットの中に入れた砂の中に、プラスチック片が、どのくらい採取されたか、3地点で3回ずつ調べました。緑色や 赤色の小さなプラスチックがいくつも見つかりました。調査した後は 浜辺の掃除 ビーチ クリーニングをしました。
昼食後、今度は葛西海浜公園に向かいました。レンジャーの木村先生から、浜辺で見られる生き物、ごみの様子と生き物に与える影響、ラムサール条約について、公園の清掃活動についての話を伺いました。そして、個々の砂浜でも、海洋プラスチックが、どのくらいあるのか、3地点で3回ずつ調べました。
熱心に調査をし、くたくたでしたが、最後まで頑張れた5年生でした。今後のSC科の学習がさらに深まることでしょう。
調査用具を貸してくださり付き添ってくださった、お茶の水女子大学の里先生、一日ありがとうございました。








10月11日(金曜) 2年 生活科「町たんけん」
大岡山北口商店街8つの店舗を訪ねて標記の学習をしました。9月に商店街通りを全員で歩いて外観等について見学し、自分でより深く知りたい、学びたいと思ったお店を絞り、今日はグループに分かれて「たんけん」しました。出発前に「・・・ヤだな・・・」と呟いていた児童がいたので話を聞くと「質問が上手にできるか心配だから」ということだったので励まして学校を出ました。今回はお店のたんけんをするということで、各看板を目敏く見つけて友達に教えたり、匂い、香りに敏感に反応したりする児童たちの声が続きました。「このお店で1番高いものは何ですか。」という質問がたびたびで聞かれましたが、ある店では今までは見た目の美しさに価値が置かれていたものが、機能性(軽さ、柔らかさ等)になってきたという説明を聞いて皆一生懸命にメモを取っていました。「何種類魚の売っているんですか」という質問の説明では「今は、秋刀魚やイカ・・・」との回答に、季節によって違いがあることも学習していました。
商品に触れないようにそろそろと静かにお店を後にするグループがあったり、「2年生とは思えないー話の聞き方が上手ですね。」とお褒めの言葉をいただいたりしました。
本学習にあたり15名もの多くの保護者の方々にご協力を得て、安全指導、学習態度の見守り等をしていただきました。ありがとうございました。
10月10日(木曜) 6年 家庭科「ミシンでソーイング」
この「ミシンを使って作ってみよう」という単元では、まず(1)「布について知ろう」で編んである布とフェルトについて知り(2)「製作計画を立てよう」で“マイバック”“マイ弁当バッグ”“ナップザック”から製作したいものを選んで計画を立て、本日の(3)「製作しよう」に至りました。3つとも(1)脇を縫う(2)しつけを取る…までは同じですがその後が製作するものによって変わるので多くの協力が必要となりました。「ミシン点けっぱなしにしないで!」「握りばさみは使った後にキャップをすること!」「アイロンは・・・」等の事故けが防止の声がたびたび聞かれる中、「行きまーす!」と言って隣席の児童に目配せしたり「うまいかもー」と独り呟いたり、「私もそうならないように気をつけなくちゃ」と話す声が聞こえてきました。児童たちは縫い方等を教え合ったり、使い終ったミシンの片づけを手伝ったり落ち着いた、また和やかな雰囲気の中で授業が進んでいきました。この学習は再来週まで(あと4時間)続きます。
5,6年の家庭科の授業では、保護者の他、清水窪応援隊、児童民生委員等多くの方々が授業をサポートし、一人一人の児童に合った丁寧な指導を行っていただいています。本当にありがとうございます
10月 9日(水曜) 3年 算数「かけ算のひっ算」
前時の復習では、学習したことを「かける数」「かけられる数」「積」という言葉を使って説明できることを確かめてから本時の学習に入りました。「1枚23円の画用紙を3枚買うと代金は…」という問題に対して学習の見通しを立てました。「かけ算」「数直線」「たし算」そして「さくらんぼ」という意見が出ると教室は暫く静まりましたが「ああ、1年生でやったー」「なるほどー」という声があがりました。そして学習のめあてが板書され、それぞれの考えをノートにまとめるときに「わからないときは手を挙げて」と指示されると、今日はティーム・テーィングのため2名の教員でこどもたちに応えて、後に児童同士の教え合い活動でさらに学習したことの理解を深めました。
習熟度別算数指導を2学級2グループ(5年生は3学級3グループ)で行ってきましたが各学年とも次学習単元(3年生は「わり算や分数を考えよう」)からは、各学年担任と少人数算数指導教員の2学級3グループ(5年生は3学級4グループ)で指導を行っていきます。
10月 8日(火曜) 1年「たんなわタイム」 1年体育「たんなわ」
2週にわたって短なわ週間が始まりました。今日は雨天のため体育館で1年生が朝の時間を使って汗をかきました。前まわし跳びでは「1回旋1跳躍」よりも「1回旋2跳躍」のゆっくりとした跳び方をする児童が多くいましたが「リズムよく」「脇を締めて」という指導の下、片足跳びやあや跳びに進んで取り組む児童の姿も見られました。途中の水飲み休憩時に「上手く跳べた?」「思うように跳べた?」と聞くと、ほとんどの児童が笑顔で小首を傾けていました。縄の長さは各家庭で調整してもらうようにとの話がありましたが、突然「先生、跳べる?」と短なわを渡され、「縄が短すぎるね。」「どうやったら跳べるかな?」と話しながら止む無く跳んでみせると、その児童も続いて前まわし跳びを見せてくれました。
短なわ運動は体育の時間にも行っています。学習カードに合わせて練習が始まり、様々な跳び方の説明の中、「先生できる?」「やってー」という声があがりました。練習タイムになると、教わった駆け足跳びを自分なりに工夫して続けて跳んだり、「グーパー跳び」「グーチョキ跳び」を向かい合って複数名で楽しんだりする姿が見られました。
10月 7日(月曜) 全校朝会 5,6年 ベストサイエンス日記紹介
・「炭酸水の泡は何でできているのだろうか」(お店でメロンソーダを飲んで)
・「イライラについて」(イライラの原因から4つの怒り)
・「サボテンの育て方について」(サボテンを買ってもらって)
・「石灰化上皮腫」(半年間の通院を通して)
・「音の研究」(ワイングラスを使って)
5、6年各学級の代表児童が校長室からオンラインで上記の発表を行いました。最後に校長から5人それぞれに講評を行い、本校の研究で取り組んでいる「実証性」「再現性」「客観性」の大切さについての話もありました。本校では2年生以上が日々の生活の中で気になった科学について調べ、自分の考えや感想を書く「サイエンス日記」に取り組んでいます。3学期には2年生の発表を予定していますが、タブレットのクラスルームにもアップロードして大勢の児童たちの日記を書く上での参考にできるようにしています。
10月 5日(土曜)学校公開 引き渡し避難訓練
学校公開2日目。土曜日であり、引き渡し訓練もあるということで大勢の方々にご来校いただきました。曇天の不順な天候の中、急遽授業場所・内容を変更したり、一部参観者参加型の授業となったり、参観者に向けての発表をしたりする学級が多くありました。ご協力ありがとうございました。引き渡し訓練は東京に警戒宣言(近く発生する大地震を予知し、警告することで被害を最小限に抑えることを目的とした防災措置)が発令されたことを想定して実施しました。昨年度までは体育館で児童の引き渡しを行ってきましたが、今年度からは各教室での引き渡しとしました。
10月 4日(金曜) 学校公開 道徳授業地区公開講座
明日まで学校公開が行われる中、今日は6校時目に道徳授業地区公開講座が行われました。参加者は児童(3年から6年)、保護者、そして併行して行われていた学校運営協議会の委員の方々で、講師は「8・12連絡会」(日航ジャンボ機墜落事故)事務局長の美谷島邦子さんでした。公開講座に先立って5校時には全学級で今年度の本校の重点項目である「生命尊重」に関する「特別の教科 道徳」の授業を様々な指導資料をもとに行いました。
〇教員の授業の工夫―
・導入の工夫「生」という字を含む熟語からの連想 ・場面絵活用 ・電子黒板活用
・発問等の短冊活用 ・デジタル教科書の活用
〇児童発言等
・「生きているって何だかいいね。」という感じをもつことの良さ
・生きているということのすごさ ・命―自分の大切なもの ・命は自分に喜びをくれる
・楽器に命を吹き込み、最後に最高の演奏をー限られた命の中で ・・・・・
〇保護者・地域 感想
・こどもたちの悲しみを一緒に助け合っていける大人になっていきたい
・今日の授業があったことをお願いだから中、高校生になっても思い出してほしい
・5校時の授業とのつながりもあり、自分事として考えることができたと思う
・「生きている」という当たり前のことを気づかせてくれた
・こどもたちが長時間の話に静かに集中して聞いていて素晴らしかった ・・・・・
10月 4日 (金曜) サイエンス朝会「カラフルな水の層」 (比重)
水にごま油を入れると、ごま油が上に浮いてきます。6月のサイエンス朝会で紹介した油と水の性質によるものです。なぜ、油が上になるのかは、比重に関係しています。水の重さを基準として、軽いと比重が小さい、重いと比重は大きいと言います。油は、水に比べ軽く、比重が小さいのです。そのため、水より上に油が浮くのです。
この、比重の性質を使うと、食塩水でも同じような現象が見られます。
まず、水100mLに対して食塩20g溶かしたもの(濃い食塩水:青く染めました)と、水100mLに対して食塩2g溶かしたもの(薄い食塩水:黄色く染めました)を用意します。濃い食塩水を先に入れて、薄い食塩水をその上にそうっと入れると、青い層と黄色い層に分かれました。これは、薄い食塩水が濃い食塩水よりも比重が小さいためです。しかし、先に薄い食塩水を入れて、濃い食塩水を入れると、すぐに混ざってしまい、層ができません。これは、濃い食塩水が、重いため、下の薄い食塩水のほうに流れていき、混ざってしまうためです。
この性質を利用して、さらに濃い食塩水(水100mLに対して食塩30g溶かしたもの(とても濃い食塩水:赤く染めました)、水100mLに対して食塩20g溶かした食塩水(青く染めました)、水100mLに対して食塩2g溶かした食塩水(黄色く染めました)で、層を作ってみました。
砂糖水でも同様にできそうです。おうちでも試してみましょう。
10月 3日(木曜)2年 SC科見学 上野動物園
2年生はSC科で「キリン博士になろう」に取り組んでいます。昨年度のサイエンスフェスティバルで2年生(現在の3年生)の発表を受けて凡そのイメージをもち、先週末行った上野動物園動物解説員とのオンライン授業を通して様々な疑問をもちました。
・どのくらい目が見えるのか?・・・「目の大きい動物は目がいい。」「キリンは体長4~5mで視点が高いから遠くまで見通せる。」
・どのようにして寝るのか?・・・「肉食動物襲来を警戒して、相当安心感がない限りずっと立っている(赤ちゃんキリンを除く)
・角があるわけは?・・・キリンのオス同士のメスをめぐる戦いのため 等々
上記の疑問に対する解説を受ける前にキリンをしっかりと観察し、ワークシートにスケッチや気が付いたことを書き込みました。
・「草を食べるときは口を横に動かしている・・・今、33回・・・・・60回・・・」
・「草を食べているときに舌が見えたよ。黒くて筋が入っていたよ。」
・「おしっこするところを見たよ。尻尾をあげてジャーと・・・音はしなかったけど・・・」
他にも今回の見学は「長い部分のある動物」に目を向けて見学をしようというめあてもありました。しおりに書かれた「長いぶぶんをもつどうぶつリスト」を見ながら「今のところ・・・“3つ”見た!」「コツメカワウソが見られなかった!」「わー、近くで見るとデカい!」の声が。一方“ホオアカトキ“が1度絶滅したかと思われたが、今では600羽まで回復したと担任から話があった時は周囲の喧騒をよそに児童たちはしんと静まり聞き入っていました。
10月 2日(水曜) 3年 毛筆書写「土」
前回「二」で横画のかき方を学びましたが、今日は標記の字でたて画のかき方を中心に学習が進められました。動画で「トン・スー・トン」のリズムでかくお手本が示されると、イメージしたことを動作で表す児童たちがいました。そして始筆の筆の入れ方、終筆での筆の紙からの離し方等気づいたことを発表し合い、皆で確かめました。練習が終わり、いよいよ半紙に向かおうとするときには「よし、いくぞ!」という声が聞こえてきました。しかし始筆の筆の向きに気を付けていると、筆を寝かせたような筆遣いとなるため、「筆は立てて」「筆は紙に垂直に」と担任が繰り返して指導していました。小筆で名前をかいて仕上げますが、画数の少ないひらがなでかく児童が多く「ひらがな、難しいー」と言いながら取組んでいました。同時間に5年生も毛筆書写を行いました。「読む」というひらがなの入った2文字の学習で漢字や仮名の大きさに注意してかきました。
10月 1日(火曜) 6年 薬物乱用防止教室
本校学校薬剤師を講師として標記教室を行いました。まず(1)「薬とは」で薬は3種類(内服薬、外用薬、注射剤)に分けられ、主作用、副作用を鑑み血中濃度が丁度よい範囲となるようにその量や回数が決められていることから個々人に処方される理由について考えました。(2)「お酒について」では飲酒が法律で20歳以上と決められている理由を脳の発達と合わせて考えました。(3)「タバコが体に悪いわけ」ではタバコが200種類もの有害物質を含み癌発生の倍率が高まることを知りました。そしてタバコを5本、20本と吸った時の汚染度を水溶液で示すと黄色から茶色と変化したとき、喫煙する人としない人との肺の色の違いが示されたときに体育館は「えっ・・・」という静かな声だけが響き、顔を見合わせる姿があちらこちらで見られました。最後に薬物乱用防止についての動画を観て、1回でも乱用となり1度壊された脳は2度と修復されることなく、また止められることなく別人のようになるーとの話がありました。中でも友達や先輩から薬物(大麻)使用を促される場面が繰り返し映し出されると児童たちの姿が静止画像のように見えました。
後で話を聞くと(3)のタバコ喫煙経験者が薬物(大麻)使用へ移行しやすく、最近問題視されているオーバードーズが心配であるとのことでした。
9月30日(月曜) 2年 体育「表現遊び」「ボール投げゲーム」
時折雨が降り、涼しさと蒸し暑さが交互に感じられる不順な天候の1日でしたが、5校時目は屋内外で体育が行われました。体育館に入ると児童たちは係りの児童たちを中心に整列をさせて静かに担任が来るのを待っていました。そして「いろいろな生き物の動きを体で表そう」という目当てを示し、壇上と向かい合わせでフロアから見上げる児童たちとの表現遊びが始まりました。まず、教師と同じ方向に動く運動、次は教師と反対方向に動く運動・・・初めは「右」「左」「前」・・・と掛け声に続いて動きを楽しんでいましたが、掛け声がなくなると難易度が増したのか思わず声が出たり笑顔が出たり・・・次は教師が用意した画用紙を破いたり、丸めたり、ピンと張ったり・・・破った紙を2枚、3枚と合わせたり重ねたりする様子を体で表現しました。最後に音楽に合わせてやると告げると「楽しすぎる!」「イエーイ!」という声が聞こえてきました。「動物」「虫」「海の生き物」―こどもたちは走り回ったり、肋木につかまったり、2人組、3人組となったりと思い思いに表現をしていました。次回は、友達の動きをタブレットPCに録画し、表現の工夫を確かめ合います。
9月27日(金曜) 6年 とうぶ移動教室(3日目)
いよいよ最終日の朝が来ました。天気予報は下り坂ですが、なんとかもってほしいです。
部屋の片付けをしっかりと済ませ、古民家ともお別れです。閉園式では、お世話になった宿舎の方へお礼の気持ちを伝えました。
雷電くるみの里でお土産を買いました。決められた金額の範囲でお土産を真剣に選んでいました。でも最高のお土産は楽しく過ごせたことのお土産話かもしれませんね。
松井農園に着きました。
今日は、紅玉、アルプス乙女、シナノピッコロ、秋映、シナノドルチェ、シナノプッチの6種類の収穫体験と試食ができました。グループごとに収穫し、すべての種類のリンゴの味比べを楽しみました。リンゴをたらふく食べ、そして、お弁当も食べ、東京に戻ります。
全行程無事終了。天候にも恵まれ、本当に最高の移動教室になりました。
施設の皆様、バス会社様、計画や世話をしてくださった先生方、準備を整えてくださった家族の皆様、そして、楽しく過ごした仲間に感謝ですね。













9月27日(金曜) 1年 図工「こすりだしからうまれたよ」
身の回りにある凹凸を探し出して紙にこすり出す学習から始まりました。児童たちは手や体全体を使ってクレヨンやパスを動かし、立てたり寝かせたりすることを繰り返して様々な表現をしていました。昨日、校庭で行った学級ではまさにパスを立てたり寝かせたり
して紙にこすり出す活動の中で「みんな同じ模様になった!」「(石畳では)こんな模様になった!」「(号令台の上では)あまり模様がうまく出ない。」と様々な声が聞こえてきました。中には包み紙を全て剥がしてクレヨン全体を寝かせきれいに模様を写し取っている子がいてその様子を見て「そうか、ゆっくり、そっとやったらいいんだ!」との声も聞こえてきました。
今日行ったクラスは雨のため校舎内で活動。昨日こどもたちが収集していた葉っぱや板、木の皮、プラスチック片等の中で石に紙を押し付けてこすりだして見せると「ダンゴムシみたいだ!」の声が。活動前にどんなものをこすりだそうかと聞くと「段ボール」「虫かご」
「階段」「上履きの裏!」「PCタブレット保管庫」「地面」「鍵盤ハーモニカケース」・・・
「『プチプチ』なら家にある!」「そうか、これは家でもできるね!」と話が膨らんでいきました。教室内での学習から廊下、階段、昇降口と活動が広がると思わず小走りをしたり、スキップをしたりして「こっちの方が広くてやりやすいよ。」「この奥も入っていいですか?」「出た!こんなふうになったよ。」等々こどもたちの声も弾んでいました。この後、クレヨンやパスから生まれる模様や形や色にを使い工夫して絵にしていきます。
9月26日(木曜) 6年 とうぶ移動教室(2日目)
移動教室2日目を迎えました。夜明け前は小雨模様でしたが、雨が上がり、外で朝会です。今日のハイキングに備え、ラジオ体操でしっかりと体を動かしました。今朝の朝食もしっかりと食べました。
午前の活動は、飯盒炊飯です。食後に学園周辺を散策し、腹ごなしです。学園の庭には秋桜がきれいに咲いていました。天気も次第に晴れてきました。
いよいよ飯盒炊飯です。「ミスターカレー」「ごはん魂」「チームカレー」「オムライス」「TKC」「たきこみごはん」のチームに分かれ、火起こし担当、カレー担当、飯盒担当がそれぞれの役割を果たし、チームで美味しいカレーを作りました。どのチームも手際が良く、10時30分にできあがった班もありました。どのチームのカレーもとても美味しそうです。教員チームのカレーは財満先生が担当。とても美味しかったです。片付けにも丁寧に取り組みました。
午後は、池の平湿原のハイキングです。校長と担任が5月に実地踏査に出かけたときは、霧に包まれ、何も見えなく、とても幻想的な風景でしたが、今日は、視界が開け、眼下には小諸市・上田市などの町並みがくっきりと見えました。清々しい気候で、大自然を思いっきり満喫しました。
宿舎に帰り、夕食、入浴です。一日の疲れを癒やしました。
そして、今夜の最終イベント、花火です。一人5本ずつの手持ち花火と、林先生作成の仕掛け花火、ナイヤガラに大いに盛り上がりました。入浴中は雨でしたが、雨はすっかり上がり、星空が見えていました。流れ星を見た人もいます。いい夢を。おやすみなさい。
























9月26日(木曜) 2,5年 歯磨き指導
本校歯科校医先生、衛生士、計4名の方々に標記の指導を行っていただきました。校医先生からは先週17日(火曜)の体育・健康教育地区公開講座の「口呼吸」から「鼻呼吸」をすることによって「ばい菌の体内侵入を防ぐ」という復習から本日のテーマとなっている虫歯についての話に入って行きました。虫歯の原因がプラークと呼ばれるものでばい菌(ミュータンス菌)の塊(1gに1憶個)であり、甘いものが口に入ると働きだすことや「歯石」となると、歯ブラシでは除去できないということを学びました。最後に「同じことを続ける力」(毎日歯ブラシを等)「決められたことを守る力」(おやつは決められた時間に等)をつけてほしいとの話の後、歯磨き指導が始まりました。歯科衛生士の方々は、机間巡視しながら「力を入れすぎずに、やさしく」という言葉を繰返し、個々に丁寧な指導をしてくださいました。
〇児童たちの学習の振り返り
・自分にはいないと思っていたのに、ばい菌が口の中にいっぱいいてびっくりした
・ちゃんと歯を磨かないとダメなことがわかった
・ばい菌の正体がわかった
・歯磨きはブラシを細かく動かすのがいいことがわかった
・歯の磨き方がこんなに大変だとは思わなかった ・・・
本日の指導は2、5年生対象に行われました。児童たちには「小学生のお口の健康について」というパンフレットが配られ、今日学習したことを家庭に伝えてほしいとの言葉がありました。
9月25日(水曜) 6年 とうぶ移動教室(1日目)
今日から、6年生のとうぶ移動教室が始まります。
校庭で出発式が始まったころは曇天でしたが、僅かに日が差すと冷涼な風が和らいできました。昨年度の移動教室の時と同じように「自分のことは自分で」「思いやり、優しさをもって」「ルールやマナーを守って」と校長講話がありました。そして大勢の保護者、教職員、児童たちの見送る中、バスは予定より少し早めに、まずは長野・小諸城址公園に向かいました。
バスは順調に進み、車窓からは妙義山や浅間山が見えました。車内ではレクリエーションやカラオケで楽しみました。
小諸城址・懐古園で美味しいお弁当を食べた後はグループ散策。秋の心地よい天候の中、城趾の雰囲気を大いに楽しみました。
大田区休養村とうぶに到着です。開園式を行い、支配人や宿舎の皆様にあいさつをしました。
宿泊場所は、男女別の古民家です。みんなワクワクしています。
宿舎では、まず、レクリエーションをしました。チーム対抗食事版カップバレーボール大会が行われ、オムライスチームが優勝しました。そして、王様ドッジボールを楽しみました。
夕食は、ハンバーグ定食です。みんな残さず食べました。食欲旺盛です。
キャンプファイアーでは、火の神「チクリンハナッペ(竹林華っぺ)」が登場し、勇気の火、健康の火、友情の火、メリハリの火を授かりました。燃え上がる炎の下、ゲームやダンスを楽しみました。最後は「大切なもの」の歌で締めました。
金原温泉(ナトリウムー塩化物・炭酸水素塩弱アルカリ温泉)で疲れを癒やした後、古民家に戻り、ジュースで乾杯。一日お疲れ様でした。






















9月25日(水曜) 4年 道徳「絵はがきと切手」(信頼、友情)
初任者研修で、5年担任が標記授業を行いました。扱った資料は、料金不足の絵はがきを送ってくれた友人に、事実を伝えるかどうか悩む主人公を通して、友達とのより良い関わり方について考えるというものでした。今回は「互いに理解し、信頼し合おうとする判断力を育てる」と、信頼ということに重きを置いて授業を進めました。はじめは「2人には信頼関係がある」「後で知ったら怒ると思う」「信頼と嫌だなという気持ちが入替る」等、ほとんどの児童がー友人に料金不足のことを教えるーとしていましたが、授業が進むにつれて「教える」と「教えない」のちょうど中間の気持ちに変更する(黒板の児童氏名マグネット移動)児童が多く出てきました。それでも「教える」「教えない」とはっきりと自身の考えを示した児童が3名いました。そして「授業を通じてこの学級の皆が信頼関係で結ばれていることが分かった」という言葉で締めくくりました。
9月24日(火曜) 3年 国語「ローマ字を学ぼう」
ローマ字は生活のいたるところで見かけるもので、学習で多用するタブレットPCでも 各キーの表示が大文字のためか、小文字を理解することが難しいようです。特に「n」「r」「h」、「b」「d」「p」等の区別が曖昧で書き誤ることが多いそうです。
今日はかなりの枚数のワークシートを書いたので、途中で肩や首、腰等のストレッチ体操や水飲み休憩をはさみ、学習を進めていました。最後にパソコン入力の仕方について聞くと7割がローマ字入力、ひらがな入力が1割程、あと、分からなくなったときは音声入力や手書き入力をするとのことでした。
9月20日(金曜) 避難訓練
授業中に家庭科室から火災が発生し、延焼の恐れがあるとの想定で校庭に避難した後、北千束児童公園(第二次避難場所)に避難する訓練を行いました。連日の猛暑から訓練前の休み時間には児童に水分補給を呼びかけ非常放送を流すと、全校児童集中して放送に耳を傾けているのが伝わってきました。第一次避難場所の校庭に集合するときは口をハンカチで覆うことになっていたためか私語は皆無でしたが、校外の第二次避難場所に避難するときも私語はなく、路側帯に沿って整然と移動することができました。上空は大きな雲に覆われWBGT31℃(危険)を下回る27.4℃(警戒)となり、帰校後の中休みは昨日に続いて外遊びができました。
9月19日(木曜) 4年 社会科見学
平成17年に下水処理場から水再生センターと改名した森ケ崎水再生センターでの4つの働き(役割)、中央防波堤埋立処分場ではごみの減量・リサイクル( 3R )で自分に何ができるかを考えてこようと伝えて学校を出発しました。森ケ崎水処理センターではアニメ動画“下水道の大冒険”を観て、その後職員から施設見学に先立って動画学習の振返りをしました。油が水と混ぜる実験ではすぐに固まる様子に「早!」「えっ!」という言葉が漏れてきました。そして実際に「沈砂池」「第一沈殿池」・・・と巡り、24時間、365日管理されていることを学びました。見学が終わり、玄関ロビーで全員が戻るまで待つ間に児童一人一人に団扇のプレゼントがありました。すると説明、誘導をしていただいた6名の職員の方々に児童たちが頂いた団扇で扇いでいる微笑ましい姿が見られました。また職員の方々からは児童たちの見学態度についてお褒めの言葉を頂きました。大森海苔のふるさと館前庭での昼食を挟んで午後は中央防波堤最終処分場を見学しました。まず施設内で「23区のごみと資源の流れ」について、1971年の「ゴミ戦争」を跨いでの「歴史」についても触れ、「物を持たない暮らし」「暮らしの中からごみを出さない工夫」から3Rの大切さに触れていきました。説明が終わり会場を移動するときに壁面に掲示された資料に見入り、一生懸命にメモを取る児童の姿が見られました。その後バスに乗って各施設や処分場を見学して回り、東京湾では最後の埋立処分場となる「新海面処分場」に向かって皆で声をそろえて「ごみを減らすぞー」と叫びました。1時間以上の車窓見学を終える直前に質問タイムがありました。僅か5分程の時間に「サンドイッチ工法が30Mと決まっている理由は?」「サンドイッチ工法では土の代わりに砂や砂利ではいけないのか?」「(処分場埋立の障壁となっている)航路の変更はできないのか?」「地震への対処は?」・・・等積極的な質問が出されました。学習したことは早速明日から各学級で新聞等にまとめ等で振返ります。
9月18日(水曜) 2年 道徳「やめなさいよ」(善悪の判断)
初めに「良くないと思ったことを注意したことがある人」と問うと、学級の3分の2ほどの児童が手を挙げました。弟が椅子に乗っていたのを見て―友達が人の名前を使ってふざけていたので―下校時に遊具のところで遊んでいる人がいたので―と様々な発言があった後に「第14回 道徳『やめなさいよ』」と板書し、今日の資料が提示されました。そして資料を読み終わると「(みんなの前で注意した私は)どうして胸がどきどきしたのだろうか」「『やめなさいよ』と言った私の気持ちはどのようなものだったのだろうか」という問いに児童たちはノートにペンを走らせました。2つ目の問い(発問)では友達が書いたノートを離席して読んで回り、「いいね」とサインし、後でサインした人を皆に紹介し、紹介された人がその考えを発表しました。最後に説話として「(担任名)ちゃんの話」が始まると児童たちの集中度が一気に上がり、話が合わると教室は質問の嵐でした。
9月17日(火曜) 体育・健康教育授業地区公開講座
講師紹介後「ドリブルは力強く!失敗しないと上手くならない!」と教わり、数名の児童とともに試技を行い、児童8名対ヴィッキーズ3名でミニゲームを行いました。観戦していた児童たちはプレーヤーの一挙手一投足に目を輝かせ、両チームともシュートが放たれるたびに、体育館は歓声と拍手で満ち満ちていました。児童たちの興奮が収まらないまま、講師(本校歯科校医の関根先生)の話が始まりました。プロ選手は一様に歯を食いしばらずに、口元の力を逃がすようにしてプレーをし、呼吸は鼻から行っていることを顎や鼻腔の構造から解説し、これらのことを意識し改善して大成した例も紹介されました。そして3,4時間目は5,6年生が学年ごとにヴィッキーズのコーチから実技指導を受けました。5年生の一部児童がヴィッキーズ応援ラジオ番組のインタビューを受けて、プロの選手と授業ができた喜び、プレーの楽しさを伝えていました。そして皆がバスケットボールに興味をもったと笑顔でこたえていました。
9月14日(土曜)15日(日曜) 夏イベント企画 学校おとまり会
この企画は清水窪PTA夏イベント実行委員会が主催して実施されました。まず体育館での開会式後、校庭に出て水遊びをしました。「降り注ぐ水をキャッチしろ!水くみびしょ濡れ競争」では各学年2チームを作って対抗戦を行なったり、校庭全面を使っての水鉄砲の打ち合い(水の掛け合い)を行ったりと皆びしょ濡れになり、一部で「(水を)掛けるなよ!同じチームだよ!」という声を何度か聞きましたが多くの笑顔が見られました。夕方になり、1年生から4年生が帰宅すると、10数名の卒業生たちがお手伝いにやってきてくれました。体育館では寝床のテント設営-その方法を教わり、テント、敷マット等を手分けして運び、早いグループは5分程で完成していました。その後は夕食。お代わりのために配膳台のある1階家庭科室近くの昇降口と2階体育館の階段を行き来する児童が絶えませんでした。その後、肝試し、校庭でのキャンドルサービスと続き、夜はなかなか寝付けずにテントの外に出て車座になって話し込んでいるグループがいくつもありました。
翌朝は起床、ラジオ体操後、朝食の乾パンを食べ、テントの撤収、テントの防災倉庫への搬出、一晩を過ごした体育館そして校庭の清掃等をして解散をしました。本企画では実に多くの保護者の方々、卒業生、そして地域の方々のご協力を得て無事にまた楽しく終えることができました。ありがとうございました。
9月13日(金曜) ふれあい給食
近隣4つの自治会から30名程が来校し、各学年学級の児童たちと会食を行いました。まず、図書室で待機している方々を児童たちが迎えに行きました。低学年の教室を覗くと児童たちの視線が扉のガラス越しに集まり、お客様の来訪を心待ちにする気持ちが伝わってきました。お客様が教室に入ると拍手が起こり、それぞれの名札が置かれた机に案内されました。会食中には質問タイムやクイズタイムが用意され、次第に和やかな雰囲気を作っていきました。
9月12日(木曜) 5年 社会「水産業のさかんな地域」
7時間扱いのうちの2時間目の授業で、前回の学習を受け今日はカツオ漁を取り上げて水産業に関わる人がどのようにして魚を獲るか、という学習問題に取り組みました。まず資料を基にカツオ漁は2つの方法があることを知り、その理由について各々のメリット、デメリットを考えて学習のまとめをしました。この授業では大田区指導課の初任者教員研修担当の先生を講師に招き、授業後の指導を受けました。講師からは2つの課題があげられましたが、こどもたちが課題に積極的に集中して取り組み、学級の雰囲気も良く、落ち着いて学ぶ姿勢が身についているとお褒めの言葉をいただきました。
9月11日(水曜) 休み時間(WBGT31℃以上のためうち遊び)
外遊びができなくても、1年生はアサガオの水やりを日々忘れずに行っていました。流しの水を出して涼んでいたり、廊下の夏休み自由研究作品を見て話をしたりする児童もいましたが、ほとんどの児童は教室や図書室で静かに、また賑やかに和やかに過ごしていました。学級担任の周囲に集まって何やら楽しそうに話をしたり、ブレイクダンスのステップを教わったり、教室後部に大勢座り込んで担任から教わってカードゲームをしたりする児童もいました。またタブレット学習をしたり、やり残した学習生活カードに取り組んだり、読書をするなど一人で黙々と取組む児童たちもいました。6年生の教室を覗くと教室後部に集まり楽しそうにゲームのようなものをやっている様子がうかがえたので声をかけると「床のタイルを使うゲームです。自分たちで考えました!」と笑顔と元気な声が返ってきました。
9月10日(火曜) 1年いろいろなおとをふいてみよう
鍵盤ハーモニカの音の出し方を工夫して、いろいろな音を見つける学習をしました。
高い音(キー、ピー)、低い音(船の出航の音)、真ん中の音、1、2、3つの鍵盤で、強弱、長く伸ばして、短く切って、白鍵のみ、黒鍵のみと様々な音を出してみました。中には1音1音を区切らず、流れるように滑らかに音階を移動させる奏法の“グリッサンド“を紹介する児童もいました。しかし、ピアノとは構造が違うため、もしもこの奏法をやりたいときには掌を返して爪で優しく行うことを約束すると、皆ゆっくりと丁寧に鍵盤ハーモニカを扱っていました。次回は、ドとソを中心に皆同じ音でそろえて吹く学習を行うことを伝えていました。片付けでは、まず吹く口をハンカチに叩きつけるようにしてホースの手入れをし、鍵盤は専用のクロスで拭っていました。中にはしまった鍵盤ハーモニカのケースも丁寧に拭いている児童もいました。
9月9日(月曜) 3年 自転車教室
大田区交通安全指導担当、田園調布警察署員の方々にお越しいただき、標記教室を実施しました。2学期が始まってからも暑い日が続き、本日もWBGT(暑さ指数)が基準値を超え全校が内遊びとなる中、3年生は体育館で学習を深めました。講話や動画視聴が中心となりましたが、自転車に乗った職員とともに、児童たちも左右左右右後ろの安全確認を何回も練習しました。動画ではドライブレコ―ダーの映像を各所で用いたり、ヘルメット着用の安全性を実験して確かめたり、また最後には学習したことをクイズ形式で振返ったりしました。
▼自転車は軽車両だから道路の左側を走行し、右折する場合は交差点で二段階右折しなければならないこと、信号機は歩行車用ではなく車道の信号機を見て走行しなければならないとの説明があった時には驚きの声が上がり、今まで理解できていないようでした。
▼また歩道は歩行者のためのもので、自転車走行は時として止めなければならないという説明、右折、左折、停止の合図の仕方の説明では皆、真剣な表情になっていました。
9月9日(月曜) サイエンス朝会「鏡の中の数字」(反射)
2学期初めのサイエンス朝会は鏡を使った実験です。
デジタル時計を鏡に映すと、8:28が85:8と、よくわからない時刻が表示されました。鏡が文字を反転して映しているからです。
鏡に映すと、2は5に、3はEに見えます。
2桁になるとどうでしょうか。18は81になりました。
では、25はどうなるでしょう。
なんと、52ではなく、25になります。これは、十の位の数字が一の位に、一の位の数字が十の位の数字に、左右の数字も反対に表示されるためです。
つなげてみると2525となっているではありませんか。
今週も、2525(ニコニコ)と楽しく学校生活を送りましょう。
おうちでも、鏡にいろいろなものを映して試してみましょう。
9月6日(金曜) 読書タイム
1学期は10回の読書タイムがあり、今日は2学期のその初回でした。昨年度の「児童・生徒の読書の状況に関する調査」によると区内小学校児童の1か月の平均読書冊数が12.33冊とありました。1か月に1冊の本を読んでいることになりますが各家庭でお子さんは如何程本を読んでいるでしょうか。
夏休みは学年によって違いがありますが、2冊から5冊以上の読書が課題となりました。同じ作者の作品を2冊読むようにと条件がある学年、また読書の記録をつけたり、読書感想文の書き方用ワークシートを書かせたりする学年もありました。今週各学級では読書感想文作成のために早速、読書感想文を書くと決めた本やワークシート、タブレットパソコン等を使って学習を進めていました。
9月5日(木曜) 5,6年 水泳記録会
1,2校時、5年生、3,4校時、6年生の水泳記録会が行われました。1,2階廊下には数十名の保護者の方々の姿が見られました。競技が始まり、緊張してスタート位置に向かう児童たちにプールサイドから声援が響き、泳ぎ終わるたびに温かい拍手が送られました。最後の学級対抗のリレーでは両学年とも白熱した競泳となり、大いに盛り上がりました。中休みは校庭のWBGTが基準値を超えて全校内遊びとなりましたが、プールサイドは基準値を下回り、児童たちの待機場所等を日蔭にするなどして予定通り実施しました。
9月4日(水曜) 夏休み自由研究発表
4年生各学級で標記発表会が行われました。一人ずつ発表する様子を観ていると、緊張感やわくわくとする気持ちの高揚感が伝わってきました。冊子や画用紙、模造紙にまとめたり、調べたものを入れたケースや作った立体作品を示したり・・・質問、賞賛が出る中、担任からの助言、支援、評価を受けて発表を終えると皆安堵の表情を見せていました。
全校児童の作品を見て回ると・・「海水の塩分の変化をー」「プラスチックと海洋汚染―」「擦り傷、蚊に刺されたらー」「日やけじっけんー」「空気抵抗―」「おきなわ魚ずかんー」等サイエンススクールらしい!表題が多く見られましたが他の幾つかの作品名を紹介します。
「恐竜王国福井県勝山市に行ってきた!!!」「僕のダニアカデシア」「これが世界のお金だ!」「夏のストレッチ大さくせん」「ふうせんガムでギネスにちょうせん」「じぶんのぬけがら」「犬を飼う前に絶対見てほしい」「外来生物を救いたい!!」「墨汁つけて!大ピンチ」「世界の森でおきていること」・・・
夏休み自由研究作品を9月9日(月曜)から9月13日(金曜)の15時15分から16時30分までご覧いただけます。受付を通り、来校証を身に付けて入校してください。
9月3日(火曜) 4年 プール納め 4,5,6年発育測定
雨雲が迫る中、4年生は早くもプール納めを行いました。児童代表の言葉等を通してこの夏の自身の水遊びや水泳に対して安全に過ごすことができたことに感謝し、学年の指導が始まりました。まず、バディーで人員確認をしてから、水慣れ(シャワー、水中リズム運動)を経て泳力検定を行いました。
一方、高学年は保健室で発育測定を行い、測定に先立ち養護教諭が、よい排便のための生活習慣と10月の「目の愛護デー」についての指導をしました。よい排便のためには食物繊維を多く含んだ食品、発酵食品等の摂取、適度な睡眠、運動により体調も良くなり、学習意欲、学力増進に加え肌つやもよくなること、また「目の愛護」のために、その構造を理解して目の休め方について学びました。5年生の指導を一緒に受けましたが、「5年生の就寝時刻は、9時半頃が理想的」という言葉の時のみ少々ざわつきましたが、他はずっと話に聞き入り掲示資料に見入っていました。
9月2日(月曜) 始業式~
校長講話で夏季休業中のわくわく教室において、のべ1000名を超す児童の参加があったことが伝えられると皆驚きの表情となりました。そして児童一人一人が一回りも二回りも大きくなったという話もあり、式後、会場に残った6年生を前に担任と管理職が集まると再度その話題が出ました。児童代表の言葉では5年生3人が2学期に頑張りたいことを発表しました。5年生、高学年として丁寧に学校生活を送りたいということ、そして2学期の水泳記録会、持久走大会、こどもまつり、SC科学習に対する自身の思いや決意が述べられました。特にSC科では2学期に学習する内容からSC科見学での学習の視点を定めて期待を膨らませたり、夏休み中に水泳や持久走の練習をしたりするなど、自分の立てた目標に対する決意の固さが伝わってきました。
また、本日はWBGT(暑さ指数)が基準値を超えたため、中休みは内遊びとなりました。