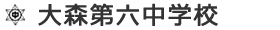ダイアリー
更新日:2026年2月4日
- 令和7年11月
- 令和7年10月
- 令和7年9月
- 令和7年6月
- 令和7年5月
- 令和7年4月
- 令和7年3月
- 令和7年1月
- 令和6年12月
- 令和6年11月
- 令和6年10月
- 令和6年9月
- 令和6年7月
- 令和6年6月
- 令和6年5月
- 令和6年4月
1月24日 大岡山駅前花壇整備
晴天が続く中、植物にとっては枯れないための水やりが必要で、この日は水やり部隊を編成しました。また、ヤブランが茂っているため、根本付近から葉を刈り取りました。この日は新年初めての花壇整備ということもあり、商店街様からいつもより多くお菓子が振舞われました。また、NPO花とみどりの街づくりの牧野さんが駅前の花壇に実ったレモンから作られたジャムを持参され、それをクラッカーに乗せて振舞われました。とても美味しくいただきました。
11月24日 大岡山駅前花壇整備

好天の下で、落ち葉を広い、色とりどりの花を植えました。
11月1日 文化祭
11月1日(土曜)文化祭を実施しました。1年生にとっては初めての行事なので、 練習段階ではどのクラスも手探り状態からスタート。学年練習では、他のクラスの歌声を聴き、もっと頑張ろう!とお互いに良い刺激を与えあっていました。満を持して迎えた当日、大勢の観客の前で緊張しつつも、一生懸命歌っている姿が素敵でした。先輩たちの歌を聴くことも勉強になったことでしょう。来年、再来年に向け、もっともっと成長していくことを楽しみにしています。
2年生は昨年の経験を踏まえて、クラス紹介は堂々と、歌声にも迫力が増しました。実行委員も1年生をリードしました。
3年生にとって中学校生活最後の文化祭は大成功で幕を閉じました。魂の籠もった 3年生の歌声、3年生の生徒が脚本を書いた演劇部の劇「秘密レスト ラン『ほうか』」、最高に盛り上がった吹奏楽部の演奏には、3 年生の ダンス部隊も加わって素晴らしいステージとなりました。
文化祭は多くの人々の協力の上で成り立っています。文化祭実行委員は、クラスをまとめるだけでなく、係に分かれて準備をし、当日まで活躍しました。看板制作、めくりプロ制作、司会、照明、観客の誘導など…。美術部は、舞台上の装飾看板を制作し、演劇部や吹奏楽部は、舞台発表で練習の成果を発揮して盛り上げました。放送委員も、機器の整備など裏方仕事に従事してくれました。PTA の方々は、受付や誘導を担当してくださいました。各学級でも、指揮者、伴奏者、クラス紹介者、BGM 奏者、パートリ ーダーなどが役割を全うし、そして一人一人が、自分のパートを練習して歌いきりました。みんなで力を 合わせて大きな行事を成し遂げました。
10月22日~10月24日 1年生菅平移動教室

根子岳と四阿山を背景に集合写真
1年生が菅平高原で移動教室を実施しました。行程中は雨に降られず、特に2日目は晴天に恵まれました。1日目の軽井沢クイズウォーキングや2日目の菅平高原ハイキングで自然を堪能するとともに、レクレーションで交友を温めました。3日間を通して互いに思いやりをもって過ごす姿が多く見られ、成功裡に終えることができました。
10月19日 大岡山駅前花壇整備
10月とはいえ、暖かな陽気の中で、雑草取りなど、花壇の手入れを行いました。
9月28日 大岡山駅前花壇整備

ようやく朝夕は涼しくなった秋晴れの下、17名の農援隊員が大岡山駅前の花壇整備に取り組みました。花壇に生い茂る雑草を取り除きました。
9月17日 道徳授業地区公開講座

5時間目の道徳の授業を公開しました。すべての学年が生命の尊重の内容項目で日常の生活を振り返りました。その後、昨年度まで小池小学校の教員を務めていた東京都教育庁指導企画課人権担当指導主事の伊藤 育美先生を講師にお迎えして教員、保護者、地域の方で協議会を開催しました。伊藤先生や地域の方からは、真剣に学ぶ生徒の姿を褒めていただきました。
9月12日 洗足池公園清掃
1100学級、2100学級、3100学級のボランティア生徒が早朝、洗足池公園を清掃しました。
9月10日 大田区連合陸上競技大会

駒沢オリンピック公園競技場で「第78回大田区立中学校陸上競技選手権大会」が行われました。自ら希望して参加した選手たちは、猛暑の中の練習を経て大会に臨みました。全力で応援やプレーをし、それぞれの練習の成果を残して満足そうな様子が見られました。
9月4日 ブックトーク
昼休みに、図書委員によるブックトークを実施しました。7月に図書館から紹介している3年図書委員の「おすすめ本」を実際に見せながら、あらすじやおすすめのポイントを紹介してくれました。




6月4日 運動会
5月31日(土曜)に予定されていた運動会ですが、雨天のために順延に順延を重ね、6月4日(水曜)にようやく実施することができました。3年生にとって中学校生活最後の運動会が中止になってしまうのではないかと不安に思っていた生徒もいたようで、水曜日に実施できることが分かったときはとても安心していた様子でした。
早朝7時半からのグラウンド整備も、3年生が積極的に動いてくれたおかげで、計画通りに開会式を行うことができました。準備から競技、片付けに至るまで、一生懸命に取り組み、3年生らしさを見せてくれました。
第1学年の生徒は中学校初めての運動会。1人1人が中学生らしく、真剣に取り組むことができました。招集場所に自分たちで遅れずに集合したり、係の仕事で活躍したり、1つ1つの競技に熱心に参加し、応援し、悔しがり、喜ぶ姿は多くの人の心を動かしました。
5月30日 校内清掃
雨のため、1400学級、1500学級、3400学級のボランティア生徒が7時40分に集合し、8時まで洗足池公園清掃の代わりに校内清掃を行いました。
5月25日 大岡山駅前花壇整備
前日から雨模様で当日実施できるかどうか心配でしたが、朝方雨も上がり、42人の生徒がボランティアに参加してくれました。今回は、先月雑草取りをした花壇に、花の苗を植える活動でした。百日草やペンタスなど、花の特徴や苗の植え方などをNPO法人大田・花とみどりのまちづくりの方々に教えていただき、みんなで手分けして丁寧に植え、花にかからないよう注意しながらたっぷりの水をあげました。大岡山駅前に立ち寄る機会がありましたら、是非六中生も植えた可愛い花を楽しんでいただけたらと思います。
5月23日 洗足池公園清掃
1200学級、2200学級、3200学級のボランティア生徒が午前7時40分に校門前に集まり、午前8時まで洗足池公園を清掃しました。
5月16日 洗足池公園清掃
5月16日洗足池公園清掃
1100学級、2100学級、3100学級のボランティア生徒が午前7時40分に校門前に集合し、午前8時まで洗足池公園を清掃しました。
5月14日 修学旅行3日目
14:30古川駅に到着し、到着式で添乗員、看護師、カメラマンの方々にお礼を述べ、15:30やまびこ60号に無事に全員乗車しました。

到着式

新幹線乗車

雄勝ローズガーデン
9:25雄勝ローズガーデンに到着しました。津波の被災の後に一本のバラを植えたことから始まり現在、英国式のローズガーデンにまで整備され復興の象徴となった庭を観賞した後、雄勝体育館で元雄勝小学校教員の徳水博志さんから震災に備えるお話しを六中の附近の状況をふまえていただきました。

雄勝道の駅

雄勝体育館

徳水博志さんの震災講話

昼食のお弁当
6:30起床、7:15朝食、8:20荷物積み込み、8:30出発です。

朝食メニュー

朝食会場

荷物積み込み

出発
5月13日 修学旅行2日目
21:15係会の後、部屋で伝達し22:00就寝です。

食事係

入浴係

美化係

室長

オクトパス君絵付け体験
20:00オクトパス君の絵付け体験を行いました。
19:00夕食

夕食メニュー(アオサの味噌汁が付きます)

夕食会場

入館式
17:10宿舎に到着し、入館式を行い入室しました。
15:00から東日本大震災遺構大川小学校で被災児童の保護者の方から、同じ悲劇を繰り返さないために、川津波の威力と適切な避難行動についてお話しいただきました。

大川小学校伝承館

大川小学校校舎

13:15南三陸さんさん商店街でお土産を買い、ソフトクリームを食べました。

南三陸さんさん商店街
ハンバーグ弁当
12:00東日本大震災津波伝承館の講演で地元の食材で作られたオーガニックのハンバーグ弁当を食べました。
9:45陸前高田に着き、東日本大震災津波伝承館、松原、奇跡の一本松、陸前高田ユースホステル、気仙中学校を見学しました。

東日本大震災津波伝承館

防潮堤の上を歩いて奇跡の一本松に向かう

21気仙中学校

気仙中学校の中

8:10宿舎の方にご挨拶して出発しました。

朝食メニュー
6:20に起床し、7:00から朝食を全員食べました。

朝食会場3・4組

朝食会場1・2組
5月12日 修学旅行1日目
21:00から係会を行いました。その後、各部屋で伝達、就寝準備、22:00就寝です。

室長

食事係

美化係

保健・入浴係

合唱練習
2日目、3日目の震災講話の後、感謝と応援と自分たちも頑張る気持ちを伝えるために六中平和の歌の合唱を無伴奏で行うために19:45からロビーで練習しました。
18:30から1・2組と3・4組に会場が分かれて夕食です。

3・4組夕食会場

夕食メニュー

入館式

宿舎の支配人様からご挨拶いただきました。

宿舎到着
16:15宿舎に到着し、ロビーで入館式を行い入室しました。

厳美渓
厳美渓をガイドの方の案内で散策しました。

中尊寺金色堂
国宝第一号の中尊寺金色堂の前で集合写真を撮りました。その後、境内を参観しました。
平泉レストハウスの平泉文化史館の中で餅がメインの昼食をいただきました。

昼食会場

昼食

一ノ関駅到着
11:23一ノ関駅に到着し、バスに乗車。11:40出発しました。

新幹線乗車
8:40新幹線やまびこ53号に乗車し、8:45定刻通り発車しました。

出発式
集合時間前に当日欠席者1名を除いて全員が集合し、予定通り7:30から出発式を行いました。
5月2日 洗足池清掃
1300学級、2300学級、3300学級、生徒会執行部のボランティア生徒33名が午前7時45分に正門前に集合し、午前8時まで洗足池公園の清掃活動を行いました。
4月27日 ガーデンパーティー

生徒会執行部はじめボランティア生徒44名が洗足池公園の桜山で「ニギニギパラダイス」というアトラクションコーナーを設けて、小学生児童をもてなしました。内容は水風船に適量の片栗粉を入れて、感触を楽しむものです。各生徒は呼び込みや列の整備、受付、案内、計量、運搬、接客の係の仕事をとおして児童をもてなし、児童が楽しむ姿にやりがいを感じたようです。
4月25日 洗足池清掃
1200学級、2200学級、3200学級のボランティア生徒と生徒会執行部の33名が午前7時45分に正門前に集合し、午前8時まで洗足池公園の清掃活動を行いました。
4月21日 シビック・アクション
シビック・アクションの第一回目の活動を行いました。昨年活動した2、3年生のグループが、1年生に学習の成果を発表しました。1年生たちもうなずきながら話を聴いたり、クイズに参加したり、積極的な様子でした。シビック・アクションとは、他者と協働し、社会に働きかける行動」のことです。本校では、令和4年度から学年を越えた縦割りグループ で、シビック・アクションに取り組んでいます。SDGsに関連する社会問題について調べ、問題解 決のためにできることを考えます。社会へ働きかける方法を模索して実行するという経験は、グル ープで協力するからこそできる、シビック・アクションの醍醐味です。 例えば昨年度は、「大田区の貧困問題を食料で解決しよう」というテーマで学習したグループが ありました。本校生徒に呼び掛けて余剰食品を集め、蒲田の社会福祉協議会まで届けました。寄付した食品は、こども食堂で使われます。グループの生徒たちは、社会福祉協議会の方から直接お話 を聞き、この問題をより身近に感じることができました。こども食堂は大田区発祥と言われており、 区内に多数設置されています。地域に貢献することで、地域社会の一員としての意識も高まりました。このような体験は、シビック・アクションのような機会がないと、なかなかできないことだと思います。 近年では、一部の大学入試で、社会問題の解決に関する実践経験を問う小論文が出題されることもあるようです。シビック・アクションを通して培われる力は、社会から求められていると言える かもしれません。
4月19日 大岡山駅前花壇整備

穏やかな晴天のもと芝桜が可憐なピンク色の花を咲かせる中で、今年度初めての大岡山駅前花壇メンテナンスを行いました。新1年生の参加者が約半数を占めた農援隊75名とOB、清水窪小学校の児童がNPO大田・花とみどりのまちづくりの方々にご指導いただきながら雑草取りやごみ拾いを行いました。終了後はいつものように商店街の方々からお菓子や飲み物がふるまわれました。
4月18日 離任式
6校時に体育館で離任式が行われました。今年度離任された先生のうち、柴崎先生、五十嵐先生、内海先生、平田先生、長尾先生、生沼先生、若尾先生がいらっしゃいました。委員会や部活動等でお世話になった生徒が代表でお礼の言葉を読み、花束と共に皆で書いたメッセージ カードを渡しました。 これまでの感謝の気持ちを伝え先生方とお別れする、よい式にすることができました。
4月18日 洗足池清掃
今年度の第1回洗足池清掃を行いました。1100学級、2100学級、3100学級と生徒会のボランティア生徒が7時40分に集合し、8:00まで清掃活動を行いました。
4月10日 新入生歓迎式・部活動説明会
新入生歓迎式は吹奏楽部の伴奏、生徒会役員の先導で新入生が入場した後、生徒会から校舎案内や学校生活をスライドや動画を使用して分かりやすく説明しました。途中、ボラピーも登場し和やかな雰囲気を醸し出しました。また、委員会の説明を各委員長が行いました。最後に校歌と六中平和の歌を歌唱披露し、新入生お礼の言葉で会を閉じました。
部活動説明会では、各部活動が実演を交えながら熱く勧誘していました。
4月8日 入学式
4月7日の始業式は3年生123名、2年生117名が進級し、4月8日の入学式では147名の新入生を迎えて、全校生徒387名で令和7年度がスタートしました。
多くのご来賓、保護者の方々に参列いただき、伝統の校旗入場で厳かに始まり、初々しい新入生と2・3年生の落ち着きのある態度で、立派な式となりました。
式辞の一部をご紹介します。
「(前略)本校は教育目標として『気品のある生徒』『実力のある生徒』『健康の優れた生徒』を掲げています。校歌の歌詞を見てみると、『気品』は1番に『気高き心』、『実力』は二番に『まことのちえ』、『健康』は三番に『青竹のごとすこやかに』と示されています。
始めの『気品』とは、着飾ることなく、内面の美しさが表れる様子です。そのために必要となるのは『利他の心』です。例えば自分の利益になることよりも、人の助けになることを常に考える。例えば、挨拶を大切にすることで、された人の心が救われる場合もあります。
二番目の『実力』の意味は、単に知識や技能を身に付けるだけでは足りません。身に付けた力を、地域や広く社会が抱える課題の解決に役立てることができるようになって、はじめて『実力』と言えます。
三番目の『健康』は、幸せな生活を送るために心と体の健康は欠かせません。そのために適度な食事と運動と睡眠の三つを大切にするように心掛けてください。
これらの教育目標の下、SDGs、この言葉は皆さんも耳にしていると思いますが、2030年までに持続可能な社会をつくるために、本校はユネスコスクールとして、特に、気候変動や食糧問題、自然災害、そして平和の問題に向き合い、より多くの人に影響を与える行動を考え、試みることをとおして、多様性を知り、責任性を養い、創造性を培います。
そして、教職員と上級生は、皆さん一人一人の学校生活が楽しく充実したものとなり、入学して良かったと思えるように、サポートします。(後略)」
3月19日 卒業式
令和六年度 卒業証書授与式
式辞
洗足池の草花が彩を増し、季節は春へと移り変わろうとしています。
卒業生の皆さん。ご卒業おめでとうございます。
今日は皆さんの門出を祝う気持ちとともに、一抹の寂しさが胸に湧いてきます。これはともに過ごした在校生と教職員一同の気持ちであり、特に三年生を担当した先生方はひときわ強く感じていることだと思います。
思い返せば、皆さんの入学式は全員がマスクを着用し、新入生とその保護者の方々、教職員だけで執り行いました。五月に行われた運動会は六種目で午前中に終了しました。十月の文化祭は、合唱を学年毎に発表し、他学年は各教室でリモートにより鑑賞しました。演劇部と吹奏楽部の発表のみ部員の保護者の皆様に体育館で鑑賞いただきました。このようにまだまだ制約の多い年でした。
二年生になり、後輩を迎える入学式は残念ながら二年生のみリモートによる参加となりました。しかし、五月には新型感染症は五類となり、運動会は七種目で午後まで実施となりました。文化祭も生徒全員が体育館で一同に会し、他学年の歌声や吹奏楽部の演奏、演劇部の演技を直接見聴きすることができました。また、後期生徒会、専門委員会では、三年生から引き継ぎ、諸活動の中心となりました。
そして迎えた三年生。まさに六中の顔として、すべての行事や活動を先頭にたって引っ張り、伝統を継承し、新たな伝統を作り上げました。その姿は、立派で頼もしいものでした。
今、皆さんは、これから進む進路を自らの力で切り拓きました。しかし、それは、GOLEではありません。これからも地域社会から世界まで目を見開いて、持続可能な社会をつくるために、自分が果たせる役割は何かを考え、そのために必要は力を着けるための新たな学びの出発点に立っているのです。是非、君たちが六中で重ねた努力を、これからも大切にして、明るい未来社会をつくる担い手として諦めず大きく羽ばたいてください。
花向けに渋沢栄一の学問の師で富岡製糸場の初代場長などを務めた尾高惇忠の言葉を送ります。
本は、読みやすいものから読め、難しい漢書に取りついてもいきなりは理解できない。わからない本と睨めっこしていることは、死んだ文章と向かいあっていることになる。そんな無駄なことをする必要はない。本の意味がわかるようになるのは、何といっても人生経験を豊かにしなければ駄目だ。だから、若いうちは自分が面白いなと思う本から読み始めた方がいい。ただ、漫然と読んでは駄目だ。自分の生き方に照らしあわせて、なるほどな、と感ずるような読み方をしろ。そうなると知らず知らずのうちに、読書力が増して、難しい本も読みこなせるようになる。つまり文字を、読み手の肥料として活用しなければ、本などというものは何の役にも立たない。とにかく、何でもいいから片っ端から多くの本を読め。
終わりになりましたが、保護者の皆さま、これまでお子様を慈しみ、育てられ、今日の日を迎えられ、喜びもひとしおのことと思います。改めておめでとうございます。そして、これまで本校の教育にご理解、ご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。これからも変わらずご支援賜りますよう、お願い申し上げます。
また、ご来賓をはじめ地域の皆様にも、日ごろのご支援・ご協力に心より厚く感謝申し上げ式辞といたします。
令和七年三月十九日
3月14日 三送会
6時間目に三送会を実施しました。1年生は語りと合唱、2年生は寸劇を交えた3年生にまつわるエピソードを披露しました。また生徒会からは、3年生の先生方からのメッセージを交えた動画の披露がありました。最後に3年生から歌とメッセージのプレゼントをもらいました。また、卒業制作として取り組んだステンドグラス調の「ユネスコスクール」の看板も披露されました。その看板を見て、在校生から思わず「すごい・・・」との声がもれました。そのあとに披露された合唱もさすがは3年生の歌声で、会場を盛り上げました。
3月13日 普通救命講習
午前中、体育館において普通救命の技術を身に付けることで、不測の事態において自分たちに出来ることを知り、生命尊重意識を高めることを目的に普通救命講習を実施しました。各クラス6班に分かれて練習用AEDと人形を用いて、東京消防庁田園調布消防署警防課救急係、東京消防庁田園調布消防署消防団員、公益財団法人東京防災救急協会の方々にご指導いただきました。
3月10日 卒業記念講演会
講師に登山家の三戸呂拓也さんをお招きしてメッセージをいただきました。高校の山岳部から憧れの植村直己さんの母校、明治大学の山岳部へ。3・4年生の時、部長に。1年のうちの100日を60キロの荷物を背負っての合宿を行い、常に死と隣り合わせの中で抱く責任と不安。リーダーにはリーダーの役割、サブにはサブの役割、補欠には補欠の役割があり、チームワークというものは一人ひとりがその役割を全うすること。そして互いを尊重することから作られることを実感されたそうです。
大学卒業後も山登りを続け、そのために長期の休みが可能な様々な職種に就かれました。野外体験インストラクター・スキー教室インストラクター、山登りガイド、山小屋への荷揚げ、山岳TVカメラマン等など。これらの体験を通して、「一つのことを長く続けることには価値がある」「頑張れば誰かが見ていてくれる」「何かに向かって努力していれば、たとえその目標が達成できなくても、その努力はどこかで自分に還元される、無駄な努力なんてない」ことを実感されたそうです。
2008年のヒマラヤ遠征では、先発隊が雪崩に巻き込まれ全員亡くなるという体験をし、その報告会で「おまえはよく帰ってきた」「亡くなった人の分まで生きてほしい」との言葉をいただき、「皆、誰かに支えてもらって生きている」「辛いことも苦しいことも生きているからこそ」「培ってきたものが0になっても、明日・将来は1になる」と思ったそうです。
最後に「人生にはいろいろな選択肢がある。どれが正解かはわかならい。大事なのは、自分で決めて自分の責任で前に進むこと」「やろうと思えば何でもできる。やろうと思って努力すれば叶う夢もある。みんなは可能性の塊だ。今日も明日もこれからもずっと、明るく元気に生きていきましょう」との言葉を贈られました。
3月8日 学習成果発表会
1年間の総合的な学習の時間で取り組んだ内容の成果報告及び、シビック・アクションの発表会を行いました。
第1部の総合的な学習の時間の舞台発表では、「多様性を知る(1年生)」「責任性を養う(2年生)」「創造性を培う(3年生)」のテーマに沿って各学年の学級委員が発表しました。発表者は冬休みから原稿やスライドの準備を進め、昼休みや放課後など時間を見つけて練習を重ねました。
第2部では、今年度のシビック・アクションの成果発表やイベント・講座などを実施しました。2年生は10月末に3年生からチームを引き継ぎ中心となって活動を続けてきました。
3月6日 テキサスA&M大学訪問

テキサスA&M大学から教育分野の6名の教授が8日間の日程で教育の視察に訪日され、その視察先の中学校として唯一本校が選ばれました。3年生有志により本校の特色ある教育をスライドとともに紹介しあたと、校内を視察され、最後に研究主任の庭野先生から現在進めている教育研究についてご紹介しました。対応した生徒・教職員とともに、視察の際に英語で説明した生徒たちに感謝の言葉をいただきました。
1月30日席書会
大田区立中学校28校の代表生徒が池上会館で一堂に会し、半切りという大きな紙に課題の言葉を書き上げました。各校の代表生徒で会場はまさに立錐の余地もない状態の中、六中代表の3名の生徒は約2時間集中し、しっかり書き上げました。
1月26日 大岡山駅前花壇整備

冬晴れの澄んだ空のもと、今年の活動が始まりました。今回は、全員がはさみを持ち、フサフサに広がった斑入りヤブランと伸びたい放題に伸びきって枯れたススキを根元から刈り取りました。思った以上にやりがいがあり、4か所の花壇はすっきりしました。3年生は都立高校推薦入試当日でしたが、私立高校の推薦入試合格者の皆さんが駆け付けてくれました。「できることをできるときに」というボランティア精神を発揮してくれました。
1月24日 1年生百人一首大会
5回に渡ってクラスで練習してきた成果を発揮する場となりました。練習では「源平戦」という形式を覚えることから始まり、札の並べ方、同時に取った時やお手付きをした時などの確認事項を覚えました。それぞれが「この札は絶対に取りたい」という目標をもって練習に励み本番に臨みました。
1月15日 小中一貫教育の会
本校と小池小学校、赤松小学校、清水窪小学校で各教科等の一貫教育の実践的な研究を進めています。キャリア教育では、中学校1・2年生がそれぞれの小学校6年生とグループを作り、働くことについて意見交換しました。
12月24日 2年生レク大会
学級委員が企画・運営にあたり、クラス対抗の「王様だれだ(王様ドッジボール)」と班対抗の「知恵の輪クロスワード」で競い合いました。
12月23日 1年生レク大会
8人の学級委員が企画、運営を担い、リーダーとしての責任をしっかり果たしてくれました。学年全員が協力し、楽しく活動に参加し、学年全体の絆を深める2時間となりました。スポーツ鬼ごっこ、借り物競争、二人三脚リレー、ドッジボールを楽しみました。
11月12日 連合学芸会音楽の部
アプリコ大ホールで、連合学芸会音楽の部が開催されました。本校は、2・3年生有志により合唱曲「chessboard」を熱唱しました。
10月27日 千束地区スポーツ祭り
洗足池公園グランドで千束地区スポーツ祭りが開催されました。生徒会役員の生徒が実行委員として、会場づくりや招集のお手伝いをし、野球部生徒がボール送りのアトラクションの運営を行いました。また、綱引きやリレーで石川台中学校の生徒と競い合い、楽しい時間を過ごしました。
10月27日 おおお知るまちプロジェクト
大岡山北口商店街で「大岡山の好きを発見する七日間」というイベントが 開催され、令和5年度の平和問題チ ームと令和6年度の科学チームの代表生徒が発表を行いました。 イベントを主催した「おおお知るまちプロジェ クト」は、東京科学大学(旧東京工業大学)の建築 学系の学生によって運営されている学生団体です。 昨年度のシビック・アクションで、東工大とのコ ラボレーションをしたいと考えていた平和問題チームの希望をかなえるために、学生団体の皆さんが商店街でのイベントに招待してくださいました。当日はイベントを知っていて来てくださった方だけでなく、買い物に来た地域の方も足をとめてくださり、六中生の取り組みに耳を傾けてくださいました。 発表時間の枠にゆとりがあるとのことで、今年度の科学チームからも1グループ発表をさせていただきました。
10月26日 文化祭
「奏音~成長の先に~」のスローガンのもと、文化祭を開催しました。たくさんの仕事を責任をもってやり遂げ、大成功に導いてくれた実行委員の皆さん、ありがとうございました。またクラスの伴奏、 指揮、パートリーダー、クラス紹介や BGM、ポスター作製などに関わり、クラスの合唱のためにたくさんの人が頑張りました。全校生徒が集まっての開催はコロナ禍以降初めてでしたが、どのクラスの合唱も心を込めて歌の意味を聞く人に伝え、合唱とはこんなに素晴らしいものだということを自分たちも、そして聞いている人にも感じてもらえることができました。また午後の演劇部の舞台は、40 分間という長さの劇でしたが、みんなを引き付け、時に笑いを誘う楽しい劇でした。迫力がありテンポの良いせりふ回し、見事でした。吹奏楽部の演奏は 18 人という人数とは思えないほどの迫力のある演奏で、みんながよく知っているナンバーで盛り上がりました。アンコールでは盛り上げダンスの6人も加わり、体育館が一体感に包まれました。
10月19日 大岡山駅前花壇整備 募金活動
いつもご指導いただいているNPO法人大田・花とみどりのまちづくりの牧野さんから、能登半島の仮設住宅を訪れ、花の苗植えと種まき活動をされたこと。そして「花を咲かすことは、心の花を咲かすこと」とのお話がありました。
花壇整備後、大岡山駅頭と北口商店街等で2回目の能登半島災害義援金募金活動を行いました。道行く方々が足を止めてご協力くださいました。集まった76,160円を日本赤十字社を通して送金いたしました。
10月16日17日 2年生家庭科出前授業
日本毛織株式会社(通称:ニッケ・NIKKE)が提供する、教育支援プログラムとして体験型出前講座を実施いただきました。サステナブル素材としても注目されるウール素材の特性について、実験で体験すると共に 「持続可能な開発のための2030アジェンダ」 と「持続可能な開発目標」(SDGs)に向け、課題と取り組みについて考える講座です。多くの学校制服に使われているウール素材にどのような可能性があるのか?と生徒にとって身近なアイテムから環境問題を考えるきっかけとなると同時に、 きれいに長く使うための日常のお手入れ方法を学ぶいい機会になりました。
10月11日 後期生徒総会
6校時に後期生徒総会を実施しました。今回の議題は前期の活動報告及び後期の活動方針案の承認です。各委員会の活動について、様々な質問や意見が出ました。自習室を整備してほしい、ボラピー掲示板の内容を確認しやすくしてほしい、学校図書館の蔵書についてなど、自分たちがより快適に学校生活を送るために必要な、前向きな要望がたくさん出ました。身近なことに関心をもって、自分たちの暮らしをよりよくするために動くことができる力は、今後社会に出た時にも必要になってきます。後期の委員会活動は2年生が中心となって活動しますが、3年生の力も借りながら、より発展させることができるとよいです。
10月3日 ゴーヤカーテン撤去、芝桜植え
6月21日に設置し、夏休みを含めて毎日水やりをして、つるや葉の成長に目を輝かせ、小さな実を発見して大喜びした、そんなゴーヤカーテンを撤去しました。また、芝桜の苗を体育館脇と下校庭と中校庭の間の斜面に植えました。来春に可憐なピンク色の花びらが咲き誇るのが楽しみです。
9月29日 大岡山駅前花壇整備

試験前の忙しい中、14名の生徒が参加しました。
9月25日 1年移動教室3日目

松井農園でリンゴ狩り
移動教室最終日、昨日と同じ7時起床。天気は晴れ。7時25分から朝食、8時20分体育館で閉校式。三日間お世話になった宿舎の方にお礼の言葉を述べました。8時45分宿舎出発。
朝食のメニューは ヒレローストポーク、ポテト、ミニグラタン、菅平高原のグリーンサラダ、ミニトマト、クロワッサン&バターロール、メイプルマーガリン、リンゴジュース、コーンクリームスープ、アロエヨーグルト でした。
9時40分懐古園到着。小諸城址の庭園や動物園を30分間、散策しました。10時30分懐古園出発。
10時50分松井農園到着。社長さんからリンゴについてお話を伺い、1・2組は昼食を食べ、お土産を買ってからリンゴ狩り、3・4組はその逆で行動しました。リンゴ狩りは6種類のリンゴを味わいました。
弁当は メンチカツ、チキンステーキ、厚焼き玉子、ポテトサラダ、煮物、焼売、ウインナー、ご飯、梅、胡麻、さくら漬け、ソース でした。
従業員の方のお話では、松井農園にはおよそ2000本のリンゴの木が栽培されており、3月に白い花が咲くそうです。花は1か所に10個咲き、そのうち5個を摘みます。残りの5個が実になると、そのうちの4個を摘んで残りの1つを最後まで育てることで美味しいリンゴになるそうです。とても手間のかかる仕事で、お話を聞いた後食べたリンゴはより一層美味しく感じました。
13時05分松井農園出発、14時25分に上里SAで休憩、お土産を買い、帰路につきました。先々で交通渋滞に巻き込まれ、学校前到着は予定より1時間30分遅れて18時になりました。

3日目朝食

閉校式

懐古園 三の門

懐古園 入場口

懐古園 天守台から

懐古園 黒門橋
9月24日 1年移動教室2日目

根子岳山頂
晴天、気温10℃の朝です。
7時に起床、7時30分から朝食です。
朝食のメニューは厚焼き玉子とポロニアハムスライス、黒酢肉団子、大葉で包んだ白身フライ、菅平高原のグリーンサラダ、カレー風味の海苔、ささがきごぼうのきんぴら、ご飯、味噌汁、リンゴジュース です。
8時20分にバスに乗車し、菅平牧場へ、8時58分から5人のガイドの方々の案内で登山開始。11時45分に生徒104名が根子岳山頂に到着しました。集合写真を撮影後、お弁当を食べました。14時48分に菅平牧場に到着。ガイドの方々にお礼を述べてから、バスに乗車して15時に宿舎につきました。根子岳山頂は快晴で、雲海と山脈の素晴らしい景色を堪能しました。
お弁当のメニューは白身フライ、厚焼き玉子、焼売、ミートボール、ウインナー、梅おにぎり、鮭おにぎり、昆布おにぎり でした。
16時から1・2組と3・4組でレクレーションとキーホルダー作りを交互に実施しました。
18時30分、夕食
夕食のメニューは グリルチキン温野菜添え、カニクリームコロッケ、菅平高原野菜のグリーンサラダ、ミネストローネ、ご飯、ショコラケーキマンダリンオレンジソース でした。

2日目朝食

菅平牧場へバスに乗車

途中の展望台からの眺め

山頂で食べたお弁当

3・4組スポーツ鬼ごっこ

1・2組キーホルダー作り

3・4組キーホルダー作り

1・2組スポーツ鬼ごっこ

2日目夕食

2日目夕食の様子
9月23日 1年移動教室1日目

三芳パーキングエリア
雨模様の中、各教室で出席確認を行い、8時15分から放送で出発式を行いました。その後、中原街道に停車しているバスに乗車し、先生方の見送りの中で8時45分にバスは発車しました。
途中、10時15分に三芳パーキングエリアに立ち寄り、12時20分に軽井沢駅前の矢ケ崎公園に到着しました。
クラス写真を撮影後、昼食、1時から班別に旧軽井沢銀座でウォークラリーを行いました。
全員が予定した15時までにゴールし、15時15分に矢ケ崎公園を出発して宿舎に向かいました。
17時に宿舎の菅平高原ホテル柄澤に到着、17時15分に体育館で開校式を行いました。
18時夕食 メニューは「牛ステーキ、サーモンカルパッチョ、シーザーサラダと揚げ物2種(エビ、タラ)、オニオンスープ、ご飯、紅茶シフォンケーキ」
19時45分に宿舎から歩いて星空観察を行いました。山崎先生が説明している間は雲の中でしたが、宿舎に戻る途中で空が晴れ、綺麗な星空を観ることができました。
20時30分に係会、21時に部屋会議、21時30分に消灯です。

矢ケ崎公園で昼食

ウォークラリー大会の前

夕食

夕食の様子

星空観察出発前

保健食事係会

レク係会

班長会

美化・入浴係会
9月14日 地球温暖化防止授業
地球温暖化防止授業
3・4時間目、体育館において気象予報士の依田司さんを講師に迎えて、地球温暖化防止授業を行いました。依田さんはテレビ朝日の朝のニュース番組「グッドモーニング」で天気予報を行うなど著名な方です。依田さんは区内の中学校出身で、現在大田区地球温暖化防止アンバサダーを務められ、毎年区内の小中学校それぞれ1校ずつ訪問されて講演活動を行っています。授業の冒頭ではテレビで拝見する語り口で2100年の夏の天気予報を紹介されました。全国津々浦々最高気温が40℃を超える予報に、深刻な未来を想像します。その後、様々なデータから、CO2の増加と気温の上昇はリンクして、かつ右肩上がりであること、気候変動に対する日本人の意識が諸外国と比べて低いことなどを知りました。そして、六中の活動を評価いただき、六中生への期待を込められました。また、各自の将来像や、気候変動に対する政策などについて、ランダムに指名され、受け答えする生徒に依田さんから温かい言葉をいただきました。
9月6日 生徒会立会演説会
立会演説会
6時間目、体育館において生徒会選挙立会演説会が開催されました。立候補者・応援演説者ともに舞台で堂々と演説する姿は大変立派でした。
9月4日 道徳授業地区公開講座
命の授業
5時間目は各クラスにおいて、生命尊重に関わる道徳の公開授業を行いました。6時間目は体育館において、助産師雑賀明美さんを講師に迎え、3人の娘さんを育てたご自身の経験も踏まえて「命」についてのお話を伺いました。「三億個の精子が協力かつ競争しながら卵子を目指し、たった一つが卵子に到達する」「地球上に命が生まれて38億年、一人ひとりが38億年分の『いのち』を繋げる人である」「一つしかない命、一度きりの人生を大切に」「幸せはいつも自分が決める」さらに「生まれたときの話を聞きましょう」「命のバトンを渡す準備をしましょう」「ライフプランをデザインしましょう」「たくさんの人と出会いましょう」との呼びかけもありました。
7月13日 3年学校防災学習
災害発生時、まず自分の命を守り、次に身近な人を助け、さらに避難所の運営など地域に貢献できる人材 を育てる防災教育に基づき、 災害発生時において、「中学生として出来ること」への対応力を養い、防災における「自助」「公助」の身構え、心構えを持たせることを目的に3年生が学校防災学習を実施しました。
災害時の「食」 について東京都栄養士会の高山はるかさん。避難生活時の「体・運動」についいて 日本体育大学大学 運動生理学研究室ゼミ生の磯野未歩さん・山瀬花さん。災害発生時の「人の運搬」について 田園調布消防署雪谷出張所の消防士の方々と、田園調布第9消防団員の皆様。中学生として災害時に必要な知識と その実践のヒントについて 日本防災士会東京都支部長の大林一洋さんにそれぞれご指導いただきました。
7月4日 1年社会科見学
1年生が社会科見学として江東区有明にあるSMALL WORLDSと、そなエリア東京を訪問しました。SMALL WORLDSでは、SDGsについて、カードゲームで理解を深め、その後、ミニチュアの世界を楽しみました。そなエリア東京では、大地震発生後の様子を実物大のジオラマ展示で体感したり、展示物で避難生活の知恵を学んだりしました。
6月1日 運動会
6月1日(土曜)、天気に恵まれ、運動会を実施することができました。ど の競技でも、出場するクラスメイトを全力で応援しており、団結力が一気 に高まったように感じました。勝敗がつく場面では、悔しい思いをする場面もありましたが、1日を通してたくさんの笑顔が見られ、生徒達の表情 から“やりきった”“充実した”といった様子がみてとれました。 当日にむけてたくさんの準備を重ねてくれた運動会実行委員の皆さんありがとう。
5月20日 ホタル放流式
今年も横浜ホタルの会の丸茂さんにホタルの赤ちゃん幼虫をいただきました。自然科学部の生徒が毎日水を取り替え、シジミを与えて、5齢まで育てた幼虫を、地域の子供たちとともに、洗足池に放流しました。平成25年に始まり、環境保全の一翼を担うとともに、文化の継承や地域のつながりに貢献している活動です。7月上旬にはホタルが飛び始めることでしょう。
5月20日 シビック・アクション
6時間目に今年度第1回目のシビック・アクションを実施しました。1年生の各教室で、2・3年生が昨年度の活動を紹介しました。
5月18日 大岡山駅前花壇整備

これから夏に向けて咲く花を新しく植えました。色とりどりの花が花壇を明るくしてくれています。
また、大岡山北口商店街振興組合様から農援隊の帽子を寄贈いただきました。ありがとうございます。
修学旅行

14時10分 一ノ関駅に到着し、解散式を行いました。
14時51分 予定どおり、やまびこ60号に乗車しました。
東京駅には17時24分到着予定です。
改札を出て、丸の内南口地下広場で解散します。
12時40分 昼食(鶏のハラミ焼き、天ぷら エビ キス オクラ、おくらメカブ和え、あわび茸しぐれ煮、フルーツ、つぼ漬け、ごはん、みそ汁)



12時10分 猊鼻渓舟下りを楽しみました。



7時50分 朝食(国産米ひとめぼれ、味噌汁 とろろ昆布 みつ葉、香物、赤魚西京焼き、たらこ、ひじき、ポテトサラダ、目玉焼き、ウィンナー、ベーコン、海苔、納豆、枝豆わかめ中華、オレンジジュース、フルーツカクテル)

6時30分 1日晴れの予報です。
5月10日 修学旅行3日目
21時10分 係会

食事係

美化係

入浴係

室長
20時 クラス毎にグループに分かれて、修学旅行の体験のまとめを話し合いました。

18時30分 夕食(銀鮭南蛮漬け、季節のお造り4点盛、豚の角煮、メカジキフライ、夏野菜サラダ、ふかひれ焼売、白ご飯、香物、蛤のお吸い物、イチゴ ケーキ)

15時30分 グループ別に気仙沼市内の見学 Aグループは気仙沼市立新月中学校を訪問し、交流会を行いました。それぞれの学校の特徴を紹介したあと、グループ別に懇談した後、話した内容を全体で共有しました。閉会では六中は「六中平和の歌」を合唱し、新月中学校は校歌を斉唱しました。最後に六中から、六中の活動をまとめたポスターを新月中学校にプレゼントしました。新月中学校の熱烈な歓迎に改めてお礼申し上げます。





13時20分 気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館を見学しました。震災の映像を鑑賞したあと、グループ別に語り部の方の案内で震災当時のまま保存されている旧気仙沼向洋高校校舎を見学し、最後に2011年3月22日に行われた階上中学校卒業式の卒業生代表の言葉の映像を鑑賞しました。見学後の想いを各自が付箋に書き残しました。

12時50分 岩井崎散策





11時50分 ワタミオーガニックランドで昼食(南部どり味噌漬け、ごはん、生野菜 ベビーリーフ、加熱野菜 なす ピーマン パプリカ 椎茸、しば漬け)

9時20分 陸前高田の高田松原津波復興記念公園に到着しました。東日本大震災津波伝承館や奇跡の一本松を見学しました。

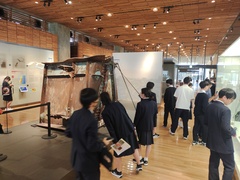

6時50分 朝食(国産米、味噌汁 ワカメ 渦巻麩、香物、紅鮭、笹かまぼこ、しそ巻き、サラダ、卵焼き、シャキシャキ肉団子、海苔、納豆、彩りごぼう、リンゴジュース、季節のフルーツ)

ホテルから見える気仙沼漁港
6時起床 今日の天気は午前中曇り、午後3時から晴れの予報です。
5月9日 修学旅行2日目
20時15分 気仙沼の伝統芸能 虎舞 を鑑賞しました。目黒のさんま祭りでも披露されたそうです。


18時30分 夕食(カツオのみぞれ煮、季節のお造里4点盛り、メカジキの煮付け、フカカツ タルタルソース 生野菜 ポテトサラダ、茶碗蒸し、白ご飯、香物、ふかひれスープ、季節のフルーツ オレンジ・キウイ)


16時45分 サンマリン気仙沼ホテル観洋に到着。入館式を行った後、各部屋に入室しました。


14時30分 厳美渓に到着。自然の景観の雄大さに歓声を上げました。



12時50分に中尊寺に到着。記念写真を撮影後、金色堂や国宝館などを見学しました。

12時10分一ノ関駅に到着、岩手県北バスに乗車し、中尊寺に向けて12時25分出発しました。

9時40分 新幹線に乗車しました。
5月8日 修学旅行1日目



予定時刻の5分前には129名全員が集合し、出発式を行いました。天候は雨の予報と違い、明るい曇り空です。
4月28日 ガーデンパーティー
洗足池公園で開催されたガーデンパーティーに生徒会の呼びかけで集まったボランティア生徒がゴムフーセンに片栗粉と水を入れたおもちゃを作る催しを「にぎにぎパラダイス」と名付けて行いました。大勢の子供たちが楽しく参加しました。
また、吹奏楽部がプリンセスメドレーなどを演奏し、盛り上げました。
4月20日 大岡山駅前花壇整備
気持ちの良い風が吹く中、大岡山駅前花壇メンテナンスが行われ、67 名もの生徒が集まりました。 北口商店街の方や地域の方、いつもお世話になっている大田区基盤整備課の方、「花とみどりのまち づくり」の方々と一緒に花壇をきれいにしました。去年植えた芝桜がとてもきれいに咲いていました。(3年学年通信より)
4月19日(金曜) 離任式
3月に5人の先生方が異動されました。そのうち、2人の先生が離任式に参加しました。それぞれ部活動でお世話になった生徒から感謝の言葉を伝え花束を贈呈しました。お二人の先生からは心温まる思い出話と、新たな学校の様子を教えていただきました。最後に校歌を合唱し、拍手で見送りました。
4月11日(木曜)新入生歓迎式、部活動説明会
歓迎式では、新入生に六中のことを知ってもらい、早く学校生活に慣れても らうため、生徒会が中心となっていろいろな準備をしました。 部活動の紹介では、2分という短い時間の中で活動の様子や特色が伝わるよう、部活ごとにいろいろな工夫が見られました。新入生達も目を輝かせな がら、楽しそうに発表を見ていました。
4月9日 入学式
ご入学おめでとうございます。
待ちに待った今日という日。
今、みなさんの目の前に
無限大の可能性が広がっています。
夢と希望を胸に
自分の一歩を
確実に記していきましょう。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ