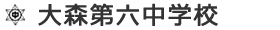生活指導
更新日:2025年4月2日
・危機管理マニュアルを整え、適切に運用するとともに、必要に応じて危機管理マニュアルの見直しと内容の改善を行う。
・全教育活動を通して、小中一貫教育のスタンダードに基づく生活指導の充実に努め、基本的生活習慣の確立と規範意識の高揚を図り、礼儀正しい生徒を育成する。
・自主的、自発的な活動を通して、自らの行動に責任をもち、社会性を備えた生徒の育成を図る。また、生徒の主体的な参画により、学校のきまりの見直しを進める。
・学校のきまり(いわゆる校則)のホームページ掲載を通して、広く保護者・地域からの知見を求め、校則の点検・見直しを進める。
・標準服の選択制を通し、TPOに合った標準服の着用を意識させることで、判断力を培う。
・学ぶ喜びや学び続けたいという意欲を育て、豊かで健全な生活を営む生徒の育成を図る。
・安全・防災・防犯教育に関わる指導及びセーフティ教室、交通安全教室、薬物乱用防止教室を開き、一人一人が自他の生命を尊ぶとともに、 外部講師を活用したがん教育の推進を含め、生涯にわたり安全で健康な生活を送ろうとする意欲と実践的態度の育成を図る。
・2月、6月、11月のこどもの心サポート月間における学級集団調査(WEBQU)などを活用した相談活動を行う。また、スクールカウンセラー、学校特別補助員、特別支援教育コーディネーター等を活用し、相互の校内における連携を深める。第1学年ではスクールカウンセラーによる個別の全員面接を実施する。
・不登校対策年間計画を活用した「居場所づくり」・「きずなづくり」を意識した不登校対策を行う。また、登校支援員、登校支援アドバイザ―の活用、学校組織体制での取組、関係機関との連携、学びの多様化学校分教室「みらい学園」との連携を充実させることで、学校生活への不適応や不登校生徒及び全ての生徒、一人一人の実態に応じた個別の相談や支援に取り組む。
・家庭・地域と連携した生活指導の中で、地域活動への参加を促し、社会の一員としての自覚を育成する。
また、関係諸機関と密接に連携する。
・学校いじめ防止基本方針をもとに、いじめに関するアンケートを各学期1回以上実施し、自殺、いじめ等の問題行動の未然防止、早期発見、早期対応を行う。また重大事態の疑いがある事案については教育委員会への速やかな報告を徹底し、学校いじめ対策委員会を中心に組織的に対応する。その他の問題行動が発生した場合についても、学校全体で対応を迅速、確実、継続的に進め、根本的な解決を目指す。事案に応じて問題行動対応サポート専門員、生活指導支援員、生活指導補助員、学校危機対応支援専門員の活用や、関係機関と連携するとともに、生活指導に対する教職員のさらなる意識向上を目指す。
・夏季休業中の面談等を利用し、生徒一人一人の生活の実態を把握するほか、長期休業中及び長期休業明けの生活を心配なく送れるよう、ICT機器を有効活用してコミュニケーションを図り、相談しやすい雰囲気づくりと指導を心掛ける。