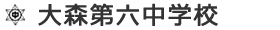10月 給食
更新日:2025年11月14日
10月31日
ベーコンピラフ 牛乳 ポトフ スイートポテトアップルパイ
六中図書館コラボ給食5日目です。今日は、「大草原の小さな家」シリーズ「農場の少年」という本の中から、「アップルパイ」の登場です。給食では、「紅はるか」という品種のさつまいもを使って「スイートポテトアップルパイ」にアレンジしています。
紅はるかは、さつまいも本来のおいしさに蜜を加えたかのようなスイーツ並の甘みが特徴で、そのまま食べてもおいしいく食べることができますが、素材本来の甘味を生かすことができるので、お菓子作りになどにも向いている品種のさつまいもです。パイ生地にさつまいもとりんごを合わせた甘いあんを乗せ、生地で包んでオーブンで焼いて作りました。
「農場の少年」の中では、とてもおいしそうに描写されていますが、給食のスイートポテトアップルパイも作中のアップルパイに負けないぐらいおいしく出来上がりました。
10月30日
豚キムチ丼 牛乳 揚げ餃子 参鶏湯風スープ
六中図書館コラボ給食4日目です。今日は、加藤シゲアキ著の「オルタネート」より、「餃子」と「参鶏湯」の登場です。給食では、「揚げ餃子」と「参鶏湯風スープ」にアレンジしています。
作中では、餃子に白菜の漬物が使われているのにちなんで、給食でも、揚げ餃子の餡(あん)には白菜を使って作りました。一般的には餃子の餡には白菜よりもキャベツのほうが使われることが多いですが、白菜はキャベツに比べて繊維がやわらかいため、ひき肉によくなじみ、一体感のある餡を作ることができます。
参鶏湯は、高麗人参やにんにく、ナツメ、栗などを一緒に煮込んで作るスープです。給食では食べやすいようにシンプルな味付けにしてあります。
今日は、六中図書館コラボ給食4日目の献立の紹介でした。
10月29日
のりバタートースト 牛乳 ビーフシチュー コールスローサラダ
六中図書館コラボ給食3日目です。今日は、朝井リョウ著の「星やどりの声」より、作中に登場する、喫茶店「星やどり」の人気メニュー「のりバタートースト」と、名物メニュー「ビーフシチュー」を再現した給食です。
のりバタートーストは、のりとバターを使っただけのシンプルな料理ですが、のりの風味とバターの塩味が意外にも相性が良く、おいしく食べられます。
ビーフシチューには牛肉を使っていますが、給食では牛肉をめったに使うことは無いので、珍しい献立になっています。もしかすると、今年度最初で最後の牛肉の登場になるかもしれません。
10月28日
ごはん 牛乳 鶏肉のトマトチーズ焼き ベーコンと野菜のソテー
六中図書館コラボ給食2日目です。今日の給食では、阿部暁著の「パラスター Side 宝良」より、作中に登場する、「鶏肉のチーズ焼き」を献立に取り入れました。朝からたんぱく質がしっかり摂れる鶏肉のチーズ焼きは、主人公が朝食に選んだメニューです。
鶏肉には、たんぱく質が多く含まれているほか、免疫機能が向上するビタミンAや、糖質、脂質やたんぱく質をエネルギーに変換してくれるのを助けてくれるビタミンB2が含まれています。
チーズにはたんぱく質、脂質、ビタミン、ミネラルがバランスよく含まれていて、特に成長期に最も必要なカルシウムが豊富に含まれています。
給食では、作中に登場する、「鶏肉のチーズ焼き」をアレンジして、疲労回復に効果的なビタミンC、老化を抑制するビタミンE、生活習慣予防に効果的なリコピンなど、様々な栄養成分が豊富に含まれているトマト類を加えて「鶏肉のトマトチーズ焼き」を作りました。
10月27日
小松菜ペペロンチーノ 牛乳 ミートボールのトマト煮 果物(みかん)
今週から六中の図書館とコラボレーションした、六中図書館コラボ給食が始まります。1日目の今日は、如月かずさ著の「給食アンサンブル2」に登場する、トマトソースのミートボールにちなんで、ミートボールのトマト煮を献立に取り入れました。
給食のトマトソースのミートボールを食べながら、慣れない料理でキャラメルソースのように甘い、友達の作ったミートボールの味を思い出すという場面で登場しています。
主食では、小松菜をたっぷりと使ったペペロンチーノを作りました。
小松菜はアクが少なく食べやすいのが特徴で、給食でもよく登場する食材です。みなさんの成長に大切なカルシウムや鉄も多く含まれています。
今日は六中図書館コラボ給食第1日目の紹介でした。
10月24日
チリビーンズライス 牛乳 ジュリエンヌスープ 果物(柿)
チリビーンズライスは、アメリカ南部の郷土料理で、テキサス州では「州の料理」に指定されているそうです。
炒めた肉と野菜に、トマトやチリパウダーなどのスパイス、そして豆を入れて煮込んで作る料理で、チリパウダーのピリッとした辛さと独特な香りが食欲を増進させてくれます。
アメリカでは金時豆や赤いんげん豆といった豆類を使って作られますが、今日の給食では大豆を使って作りました。肉や魚と同じぐらい質の良いたんぱく質を含んでいるのは、植物の中では大豆だけです。大豆が苦手なでもおいしく食べることができると思うので、まずは1口食べてみてください。
10月23日
ごはん 牛乳 厚焼き卵 大豆とじゃこの揚げ煮 キャベツのみそ汁
大豆は、歴史の長い食べ物です。日本には、縄文時代に伝わっていたことがわかっています。日本では、大豆を豆として食べるだけでなく、みそやしょうゆ、豆腐や納豆などの原料としても使われていて、日本の食生活には欠かせない存在です。
さらに、大豆には、たんぱく質やカルシウム、鉄や食物繊維など、みなさんの成長に欠かせない栄養素がたくさん含まれています。
今日の給食では、大豆と小魚を油で揚げて、あまからいタレにからめた「大豆とじゃこの揚げ煮」を作りました。
10月22日
ガーリックトースト 牛乳 コーンシチュー ツナサラダ
にんにくは、古代エジプト時代から食用されていたといわれるほど古くからある食材です。エジプトのピラミッドを建設した労働者たちが疲れをとるために食べていたといわれ、疲労回復に強い効果があります。独特のにおいがあり苦手な人もいるかと思いますが、このにおいの元は「アリシン」といって、にんにくの疲労回復の効果を含んでいる成分です。
にんにくの国内での主な生産地は青森県で、7割以上が青森県で生産されています。今日の給食でも青森県産のにんにくを使ってトーストを作りました。
10月21日
だいこんは、消火に良いことでも知られている野菜です。だいこんには、でんぷんを分解する「アミラーゼ」が含まれおり、食物の消化を助け、胸やけや胃もたれを防ぐ効果があります。だいこんおろしやサラダのように生で食べるのが効果的といわれており、胃もたれしやすい揚げ物や、脂の多い魚に大根おろしが添えられているのは、おいしいだけでなく、理にかなった食べ方ともいえます。
今日は、だいこんおろしを使ったポン酢ダレを、さばにかけました。給食では衛生面に考慮して、生ではなく加熱して作りました。
10月20日
野沢菜ごはん 牛乳 山賊焼き からし和え 油揚げとじゃがいものみそ汁
寒さが厳しい長野県では、冬になると田畑から青物が取れなくなるため、晩秋になると、大量に保存用の漬物を仕込んでいたそうです。そのなかでも、「野沢菜漬け」は長野県を代表する漬物の1つであり、信州の冬には欠かせないものだといわれています。今日の給食ではごはんに野沢菜漬けを混ぜ込んであります。
つづいて、主菜の「山賊焼き」についてですが、長野県の中信地方で広まったといわれており、料理名に「焼き」とありますが、油で揚げて作る料理です。揚げ物なのに料理名に「焼き」と付くのは不思議ですが、これは昔、油が貴重だったため、少量の油で揚げ焼きにして作られていたためだといわれています。ほかにも色々な説があるので気になる人はぜひ調べてみてください。
10月17日
さんまのかば焼き丼 牛乳 ゆかり和え 豚汁
さんまは秋にとれる代表的な魚で、形が「刀」に似ているためことから、「秋」の「刀」の「魚」と書いて「秋刀魚」と呼ばれるようになりました。
さんまに含まれる油は、お肉と違って体の中にたまらない油で、ドコサヘキサエン酸とエイコサペンタエン酸という脳の神経を活性化させ、記憶力をよくしてくれたり血液をサラサラにしてくれて生活習慣病の予防に役立ってくれる成分を含んでいます。その他にも、カルシウムの吸収を助けてくれるビタミンDや貧血予防に役立つビタミンB12、血管が硬くなるのを防いでくれるビタミンEなど、体に良い成分がたくさん含まれています。
10月16日
四川豆腐丼 牛乳 辣白菜(ラーパーツァイ) わかめと卵のスープ
今日の副菜は、辣白菜(ラーパーツァイ)といいます。ラーパーツァイは、中国の四川省(しせんしょう)という地域の料理のひとつで、酸味と辛味があとをひく味付けです。四川省の料理は「四川料理」と呼ばれ、中国の料理の中でも辛味が特徴的だといわれています。その理由として、四川省は湿度の高い地域であることから、辛いものを食べて汗を流し健康を保つためだという説があります。辛い食材の代表格の唐辛子には「カプサイシン」という成分が含まれており、発汗を促す効果があります。
給食では、辛味は控えめにして食べやすくなるよう作りました。
10月15日
ミルクパン 牛乳 サーモンフライ ジャーマンポテト コンソメスープ
コンソメとは、「完成された」という意味があるフランスの伝統的なスープです。日本ではよく、「ブイヨン」と混同されるそうです。ブイヨンとは、肉と野菜を数時間煮出した汁のことで、スープや煮込み料理などを作る際にベースとして使われる、「出汁」のことをいいます。コンソメはそのブイヨンに、肉・野菜・調味料などを加えて作るスープのことをいいます。給食でもコンソメスープはよく登場していますが、グザイによって同じコンソメスープでも味が違うので、味わってみてください。
10月14日
ごはん 牛乳 里芋と海苔のコロッケ 野菜のごま和え 豆腐のみそ汁
さといもの歴史は古く、日本にやってきたのは、稲作が始まる前の縄文時代といわれています。「さといも」という名前は、山でとれる山芋に対して、里で育つ芋だから「里芋」とつけられたのだそうです。さといもは成長すると、親芋を中心に、そこから分球して子芋ができ、子芋から孫芋が分球していきます。このことから、さといもは子孫繁栄の食べ物とされ、お正月や節句の料理には欠かせない食材となっています。このように、昔から日本の食文化になじみがあるので、さといもを使った郷土料理もたくさんあります。
今日の給食では、さといもを使って和風のコロッケを作りました。
10月10日
わかめごはん 牛乳 鮭の南部焼き じゃがいものきんぴら 小松菜のみそ汁
わかめは、昔から日本で食べられてきた食材です。ミネラルがたくさんある海の中で育つので、わかめ自体にもミネラルがたっぷり含まれていて骨や歯を作るカルシウム、体の中の余分な塩分を外に出してくれるカリウムなどが多く含まれています。
北は北海道から、南は九州まで、日本のいろいろな海岸でとることができます。
今日はわかめを乾燥させた、炊き込みわかめを使って作った、わかめごはんを献立に取り入れました。
10月9日
しょうゆじゃこごはん 牛乳 肉じゃが みそ汁
肉じゃがは、肉と野菜を煮込んだ料理です。肉は、関西では牛肉、関東では豚肉が使われることが多いようです。
家庭料理として代表的な料理ですが、肉じゃがの歴史は古く、すでに明治の終わりの海軍の料理教科書には、肉じゃがに近い料理のレシピがあったそうです。ビタミンをたくさん含み、栄養豊富な料理として広まりました。
ビタミンCは熱に弱い栄養素ですが、じゃがいもに含まれるビタミンCはでんぷんに包まれているため熱に強く、調理をしても壊れにくいといわれています。ビタミンCは免疫力を高めてくれる効果があるので、しっかり食べて元気に過ごせるようにしましょう。
産地:豚肉(茨城)、にんじん(北海道)、たまねぎ(北海道)、じゃがいも(北海道)、さやいんげん(山形)、ごぼう(青森)、だいこん(北海道)、小松菜(埼玉)
10月8日
ツナサラダトースト 牛乳 オニオンドレッシングサラダ ミネストローネ
たまねぎは、日本では古くから、北海道、大阪府、兵庫県でよく作られていました。戦後に食が洋食化したことによって、たまねぎの消費が多くなり、それにともなって、栽培面積が急増しました。
色々な料理に使われているたまねぎですが、古代エジプトではピラミッドを作った人たちの疲労回復のスタミナ食として食べられていたといわれています。
今日の給食では、たまねぎを使ったドレッシングを作りました。
産地:キャベツ(群馬・長野)、にんじん(北海道)、きゅうり(岩手)、たまねぎ(北海道)、しょうが(高知)、にんにく(青森)、じゃがいも(北海道)
10月7日
キムチラーメン 牛乳 海苔ナムル コグマドーナッツ
今日の給食のコグマドーナッツの「コグマ」とは、韓国語で「さつまいも」のことをいいます。
さつまいもは、焼き芋に始まり、おかずからお菓子までと様々な調理法で食べられています。
ビタミン類が豊富に含まれているほか、食物せんいも多く含まれていて、おなかの調子を整えてくれるのにも役立ちます。
今日の給食では、蒸してつぶしたさつまいもを生地に練りこみ、油で揚げてさつまいものドーナッツを作りました。
産地:豚肉(茨城)、鶏卵(青森)、しょうが(高知)、にんにく(青森)、もやし(栃木)、長ねぎ(青森)、にら(栃木)、にんじん(北海道)、だいこん(北海道)、小松菜(埼玉)
10月6日
あぶたま丼 牛乳 けんちん汁 お月見団子
今日は十五夜です。十五夜は、秋の夜空の美しい月をながめて楽しむ、風流な行事です。秋の空は澄んでいるので、この時期の月は1年の中で最も明るく、美しく見えるといわれています。
また、十五夜は食べ物の収穫を祝う日でもあります。旬の里芋や、収穫したお米で作った団子をお供えし、ススキを飾って、たくさんの食べ物を恵んでくれる自然に感謝の気持ちをあらわしてきました。
今日の給食では十五夜にちなんで、里芋を使った「けんちん汁」と「お月見団子」を作りました。お月見団子は給食室のみなさんがひとつひとつ丁寧に作ってくださいました。
産地:鶏肉(国産)、鶏卵(青森)たまねぎ(北海道)、にんじん(北海道)、長ねぎ(青森)、糸みつば(千葉)、ごぼう(高知)、だいこん(北海道)、えのきたけ(長野)、さといも(埼玉)、万能ねぎ(福岡)
10月3日
かてめし 牛乳 みそポテト つみっこ
今日は埼玉県の郷土料理を紹介します。
「かてめし」の「かて」はとは「糧(かて)」のことで、食物を意味します。昔、お米は貴重な食べ物だったため、季節の野菜や山菜、きのこなどを混ぜて、量を増やして食べていたことから、この名前がついたといわれています。
「つみっこ」は、小麦の栽培が盛んだった埼玉県ならではの郷土料理です。「つみっこ」とは、「つみとる」という意味の方言で、小麦粉と水を練った生地を、つみとるようにちぎって鍋に入れて作ります。
「みそポテト」は、農作業の合間の軽食として食べられてきた郷土料理です。じゃがいもに甘辛いみそをからめて食べるみそポテトは、現在でもおやつやおつまみなどとして親しまれています。
今日は給食で埼玉県の味めぐりでした。
産地:鶏肉(国産)豚肉(茨城)、にんじん(北海道)、さやいんげん(青森)、ごぼう(群馬)、だいこん(北海道)、ねぎ(青森)、小松菜(埼玉)、じゃがいも(北海道)
10月2日
ごはん 牛乳 高野豆腐と野菜の上揚げ煮 キャベツとじゃがいものみそ汁
高野豆腐は、豆腐を凍らせ低温で熟成し、その後、乾燥させて作られる日本の伝統的な保存食です。一般的には木綿豆腐で作られた高野豆腐が知られています。大豆の栄養素がギュッと詰まっていて、たんぱく質や脂質、ミネラル、ビタミンなどがたくさん含まれている栄養が豊富な食材です。
今日の給食では高野豆腐を使った主菜を作りました。
産地:鶏肉(国産)、じゃがいも(北海道)、ピーマン(岩手)、赤ピーマン(高知)、にんじん(北海道)、たまねぎ(北海道)、キャベツ(長野)
10月1日
キャロットライスのクリームソースかけ 牛乳 フレンチサラダ 野菜スープ
にんじんは、和食・洋食・中華、どの料理にも合う野菜です。「カロテン」という成分を多く含んでおり、にんじんがオレンジ色なのは、このカロテンによるものです。カロテンのほかにも食物せんいを多く含んでいます。にんじんは体に良い成分をたっぷり含んでおり、料理に彩りを与えてくれるため、給食にもほぼ毎日登場しています。今日の給食では、ホワイトソースをキャロットライスにかけて食べる料理を献立に取り入れました。にんじんが苦手な人でも食べやすくなっていたのではないかと思います。
産地:鶏肉(国産)、にんじん(北海道)、たまねぎ(北海道)、しめじ(長野)、しょうが(高知)、ほうれんそう(栃木)、キャベツ(長野)、きゅうり(岩手)、小松菜(埼玉)